記事・インタビュー
独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター 院長
下村 登規夫
医師になるには、多くの関門がある。最終的には、国家試験に合格しなければ、医師にはなれない。医師になっても、臨床医として一人前になるためには、研修を完遂しなければならない。
私はほぼ30年以上臨床一本でやっている。専門が神経内科なので、外科的処置は内視鏡的胃ろう造設術くらいである。主に診療する疾患は、頭痛・めまいなどの一般的疾患から、疲労を主訴とする疾患、神経難病まで様々である。
近年では、神経難病の患者さんを診察する機会が格段に増えている。私たちは新潟県上越市の病院であるが、東京からの患者さんも多数ある。遠方より紹介されて来られる患者さんもある。私は仕事柄、コラムを多数書いてきたので、医師の役割について考える機会が比較的多いほうだと思う。
DNR(Do Not Resuscitate:過度の延命治療をしない)という言葉がある。この言葉の解釈も難しいが、私は現病により、生命的に危険が及んだ場合と考えている。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者が肺炎で血液酸素濃度が下がった場合、迷わず抗生剤の投与を行うであろう。この場合の肺炎は抗生剤の投与で改善が望めるからである。ALSに合併した肺炎だから抗生剤投与はDNRに反する、という考えもあるだろう。しかし、投薬のみで救うことができれば救命に躊躇する必要はない、と考えている。難しい決断だが、DNRの参考にして頂きたいと思う。
患者を助けたいと願うことは、医師として当然のことである。しかし、「死」に向き合うのも医師の役目である。私は、以前より「死は絶対に果さなければならない義務である」と幾度となく述べてきた。この義務からは逃れることができない。しかし、この義務を遂行するために方法を選択する権利は有している。このように考えると、先の震災などで亡くなられた方々はこの権利を遂行できなかった、と言うべきであろう。医師は、死を前にして役立つ存在となるためにすべきことがある。私はこう考えながら、常に患者さんに接するように努めている。特に難病患者に接する際、その疾患のために患者が死に直面している場合などである。このような時、医師は自分の無力さを思い知らされる。どうしても助けることができない時、私はその患者さんのベッドの傍らに立っているだけで、何もできないと知っていながら、心臓の鼓動を聴診器で聞き、呼吸音を聞き、酸素濃度を測定し、血圧を測定しようとする。
医学的にみると測定しているだけで、救命行為をしているわけではないということは十分に理解している。それでも、ご家族の方からは、「先生に診てもらってよかった」とよく言われる。ただ側に立っているだけで、家族は安心感を覚えているのかもしれない。このような時、私は医師の役目を知らされたと思うのである。つまり、いざという時(患者が死に直面した時)、医師はただ側にいるだけでいいのかもしれない。それが医師として重要なことなのだと再認識させられる。
この考えは、外科治療や薬物治療などを否定するものではない。あくまで、「死」に直面した場合のことを述べたまでだ。だが、それ以外にもこのような状況を感じることがある。外来患者にせよ入院患者にせよ、いろいろな患者がいるのは当然である。それぞれの立場や生活習慣などがその人の人となりを作り出している。そのようなことを理解して、患者に対面することは重要である。
しかし、すべての患者についてこのような情報が捉えられているわけではない。だからこそ、常に患者に対する丁寧な応対が重要となる。医師は確かに診断・治療をして患者を治癒に導くことができる。それは時に成功し、時に失敗する。成功した時は自分の腕前だと言い、うまくいかなかった時にはこういう事もあると納得する。しかし、実は、医師は患者の治癒力を引き出す手伝いをしているだけなのかもしれない。そう考えると、「この先生なら大丈夫」と患者が思うような医師を目指すことが重要だとわかるだろう。医師と顔を合わせるだけでなんとなくよくなった気分になる。患者にこのような感覚を持たせることができる医師は、確かに「ただそこにいるだけでいい」のかもしれない。
これが、医師にできることのすべてとは決して言わないが、大切な一面だと考えている。そして、これこそが究極の医師像の一つかもしれない。
※ドクターズマガジン2014年5月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
下村 登規夫
関連する記事・インタビュー
-
記事

【Doctor’s Opinion】矯正医療をご存知ですか
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】矯正医療をご存知ですか
篠原 幸人
-
記事

【Doctor’s Opinion】医療安全の新たな段階 群馬大学病院医療事故調査報告書が投げかけたもの
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】医療安全の新たな段階 群馬大学病院医療事故調査報告書が投げかけたもの
長尾 能雅
-
記事

【Doctor’s Opinion】選択ということ
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】選択ということ
山中 寿
-
記事

【Doctor’s Opinion】医療の立ち位置
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】医療の立ち位置
方波見 康雄
関連カテゴリ
人気記事ランキング
-

【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
- ライフスタイル
- お金
医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
-
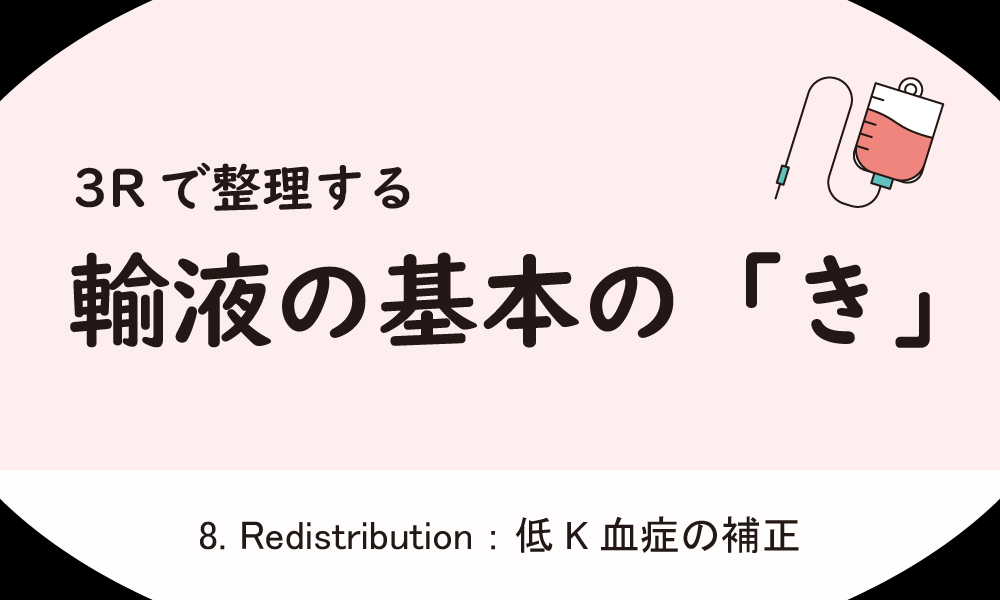
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
- 研修医
- 専攻医・専門医
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
柴﨑 俊一
-

【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
- 研修医
- 学習ツール
【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
福島 通子
-

海外で医師として働くためのステップ
- ワークスタイル
- 海外留学
海外で医師として働くためのステップ
-
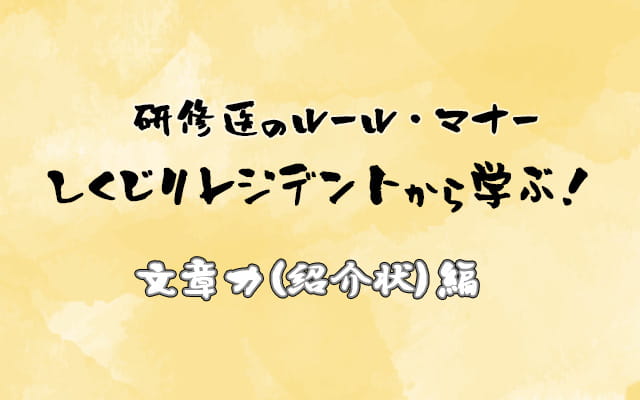
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
- 研修医
- ワークスタイル
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
三谷 雄己【踊る救急医】
-

食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
- Doctor’s Magazine
食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
名郷直樹、五十嵐博
-

海外の医師免許を取得する方法
- ワークスタイル
- 海外留学
海外の医師免許を取得する方法
-

医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
- 研修医
- ワークスタイル
- 常識の非常識
医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
柴田 綾子
