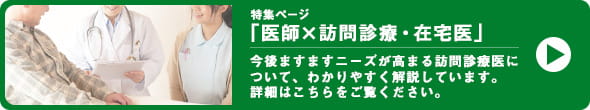記事・インタビュー
三重大学大学院 医学系研究科
地域医療学講座 講師
若林 英樹
私が勤務していた岐阜の「総合在宅医療クリニック」は、医師5人のグループ体制で、患者170人を診療し、年間約70人を自宅で看取っていた。患者も子供世代が介護する方、配偶者が介護する方、一人暮らしの方など、事情はさまざまだ。診療は定期訪問に加え、24時間365日で緊急コールを受ける体制をとっている。多くの患者の家族からは、「こんな医療があるなら、もっと早くお願いすればよかった」とありがたい言葉をいただく。もちろん、病気なので笑顔の時ばかりではないが、このような評価は口コミで広まり、それなりの評価をいただけているのでは、と思っている。
医療者仲間からは「それはさぞ大変でしょう」と言われる。私自身はいくつかの病院に勤務した経験があるが、在宅医療が特に大変だと思ったことはないし、患者や家族の希望に沿って、臨機応変な対応がしやすいことも在宅医療のメリットとして感じるところだ。
在宅療養は、地域の多くの方々が力を合わせ、支援することで成り立っている。ここでは、患者さんの日常をよく知る看護・介護職の存在がカギとなる。家族や近隣の力も大きく、それらの方が健康なまま介護を担えるよう配慮することも医療者の務めとなる。それらの方々と多職種のカンファレンスや勉強会で共に学び、難しい局面では共に悩む。そうしたことで日々チームの力を高めて初めて、質の高いケアと安心を届けることができる。
また、患者が自宅で療養するためには、症状が安定していることが大前提となる。定期訪問で日常的に病状コントロールを行うことが重要で、これによって、休日夜間のコールも最小限に抑えることができる。医師は待機当番制と情報共有をきっちり行うことで、休暇もしっかり取れる。医学、看護、リハビリ、栄養などおのおのが専門技術を研さんし、協働して支援を行う。
自宅で過ごすことの良さについても、述べておきたい。患者は家族と一緒に住み慣れたところで過ごし、好きなものを食べ、夜は静かに眠ることができる。日常生活があることで、必要以上に病気にとらわれることなく、自分らしく過ごすことができる。笑いのある生活があれば、自然治癒力も最大限に引き出される。
とはいえ、在宅療養中は病院での医療が断たれるわけではない。がんの痛み、認知症の周辺症状、肺炎などが重度のときには一時入院加療の選択もある。「痛い、痛い」と患者が言えば、それを見守る家族も苦しくなってしまうだろう。患者や家族の通院負担、対応や食事などの負担等の事情も総合的に考える必要がある。ここでは、在宅医と病院医師とのスムーズな連携が欠かせない。
膀胱がん末期で腹腔内転移がある恒夫さん(75歳・仮名)の場合、退院時には既に「余命1ヶ月」と説明されていた。主介護者である妻の佳代子さんは「最期まで少しでも元気でいてほしい」と願っていた。恒夫さんも「孫と約束した温泉旅行に行きたい」と願っていたが、次第に腹痛や下肢浮腫が悪化し、佳代子さんも対応に苦慮するようになっていた。
私たち在宅医療チームは、週2回の訪問診療、毎日の訪問看護により、症状緩和はもちろん、さまざまな療養支援を行った。病院で緩和的放射線治療を行い、より少ない投薬で症状をコントロールする。放射線治療後3ヶ月間、症状は安定した。旅行までは難しかったが、孫と一緒に好物の刺身を食べることができた。そのころには栄養士と相談し、工夫して作った佳代子さんのみそ汁が恒夫さんの命の源となっていた。
佳代子さんは看護師に相談し、レスキューを調整して使えるようになった。洗髪時には孫が看護師を手伝い、恒夫さんはうれしそうにほほ笑んでいた。
その後、恒夫さんの容体は次第に悪化し、やがて佳代子さん、子供や孫に見守られて永眠した。「最期まで家で過ごせたこと、ありがとうございます。近所の人にも勧めます」。一番つらかったはずの妻・佳代子さんからのありがたい言葉だ。
病院単独ではなしえない地域・家庭で連携のとれた在宅医療、絆、ぬくもりといった「学ぶべき医療の原点」がここにある。高齢多死社会を迎える中で、「在宅医療の大変さ」は非常識になるだろう。
監修:竹村洋典(三重大学大学院 家庭医療学 教授)
※ドクターズマガジン2014年9月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
若林 英樹
人気記事ランキング
-

【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
- ライフスタイル
- お金
医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
-
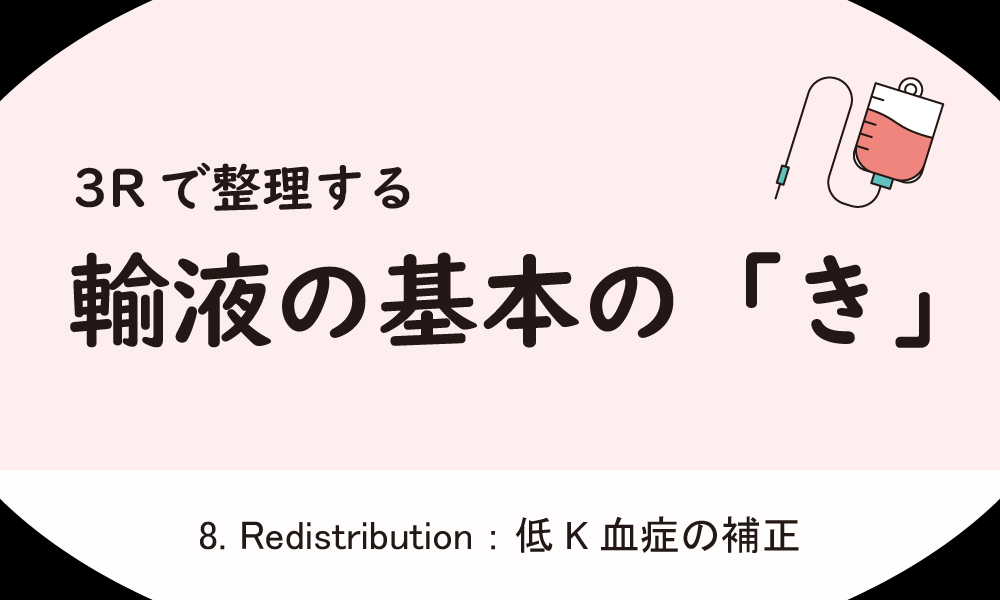
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
- 研修医
- 専攻医・専門医
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
柴﨑 俊一
-

【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
- 研修医
- 学習ツール
【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
福島 通子
-

海外で医師として働くためのステップ
- ワークスタイル
- 海外留学
海外で医師として働くためのステップ
-
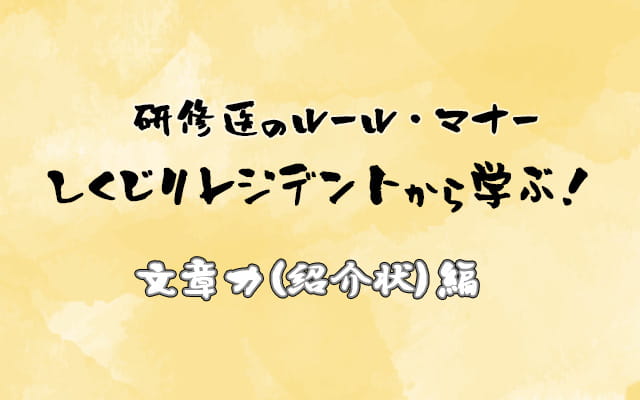
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
- 研修医
- ワークスタイル
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
三谷 雄己【踊る救急医】
-

食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
- Doctor’s Magazine
食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
名郷直樹、五十嵐博
-

海外の医師免許を取得する方法
- ワークスタイル
- 海外留学
海外の医師免許を取得する方法
-

医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
- 研修医
- ワークスタイル
- 常識の非常識
医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
柴田 綾子