記事・インタビュー
山形大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座 教授/日本耳科学会 理事長
欠畑 誠治
スティーブ・ジョブズが「電話を新たに創り直す」と発表したのは、2007年1月9日のことだった。画期的なユーザーインターフェースを持ち、インターネット通信機器でもある電話、iPhone。iPod+Phone+Internet=iPhone。それは、まさに手のひらにのる小さなデスクトップであった。
その操作を可能にしたのはマルチタッチ。物理的キーではなく、タッチスクリーンに「指」を使って入力する。スクリーン上に並ぶアプリのアイコンを「指」でタップし起動させる。そして「指」で画像をピンチして拡大縮小する。今ではみんな当たり前に行っているこの動作。アップルはポインティングデバイスとして「指」を再発見したのだ。
当時の日本では、今ではガラケーと呼ばれるようになった二つ折りの携帯が主流だった。ショートメールが送れて、写メができ、着メロが選べてiモードでインターネット接続サービスの利用ができた。日本の携帯電話ってものすごくクール、だと思っていた。
15年前のあの日以来、iPhoneは世界中のmobil edeviceを変えただけではなく、私たちの生活様式を変え、世界を変えた。
一つの機器の登場により手術手技が変わっただけではなく、手術のコンセプトまでを変えたものに手術用顕微鏡がある。
19世紀末、耳鼻咽喉科業界の克服すべき二大問題は、耳から膿が出て高熱を出し死に至る病と、呼吸が苦しくなり窒息して死に至る病であった。Schwartze が化膿性中耳炎に対する乳突削開術を報告したのが1873年であり、同じ年にあのBillrothが喉頭がんに対して喉頭摘出術を初めて実施した。以来、われわれの先人たちは罹患した部位、臓器を切除あるいは摘出するという外科的方法で命を守ることを可能としてきた。中耳根本手術や喉頭全摘術により生命予後は著しく改善した。『医学・医療の勝利』である。しかし、それは一方では「聴く」「話す」という人間が人間らしく生きていくために重要な機能の喪失を意味した。
『命』と『聴くこと話すこと』、どっちが大事ですか、と問われれば「両方ください」と答えたい。その率直な願いを叶える、叶えるように努力・工夫するのが、その後のわれわれに課せられたミッションとなった。20世紀後半には鼓室形成術、喉頭部分切除術などが開発され機能温存に取り組んできた。
その鼓室形成術を可能としたのが、1951年に開発されたOPMI-1と呼ばれる双眼式手術用顕微鏡である。OPMI-1は十分な光量を持ち5段階に拡大ができ、手術操作に必要なワーキングスペースを有し、頑丈なスタンドと多関節のアームを持つ操作性に優れた光学機器であった。この顕微鏡は、Wullsteinにより他診療領域に先駆けて耳科手術に応用され、機能温存を可能とする革新的な鼓室形成術を生み出すことになる。それまで額帯鏡やルーペを用いて手術が行われていた耳科手術は、「Microsurgeryにより従来の方法ではたどり着けない新たな次元へと到達できた(Wullstein)」。耳科手術に起きた最初のパラダイムシフトであった。
しかし、大き過ぎる成功は時として新たな革新の妨げとなる。その後、Microsurgeryは最も変わっていない手術分野といわれるようになった。顕微鏡は術者に接眼レンズをのぞき込むことを要求し、時として窮屈な姿勢での微細な操作を強いることがあり、肩こりや腕・首・腰の痛みは長時間顕微鏡を使用する外科医の「職業病」といわれるようになった。
近年のHDカメラシステムの革新は、内視鏡を用いた耳科手術EES(Endoscopic Ear Surgery)を可能とし、さらには外視鏡3D Exoscopeの開発につながりEXES(Exoscopic Ear Surgery)を可能とした。EESとEXESは内視鏡や顕微鏡をのぞき込むという軛(くびき)から術者を解放し、「Heads-up surgery」という新たなパラダイムへの道を開いた。「Heads-up surgery」は、対象を大型4Kモニター上に拡大視しながら、人間工学的に優れた姿勢での手術を可能とした。これは術者の疲労や負担を軽減することでより正確で確実な手術へとつながる。さらには、術者と同一の3D術野を助手、看護師、見学の若手医師や学生などと共有できるという点で教育面や安全面などで優れている。さらに「Heads-up surgery」では、ARやMR(mixed reality:複合現実)との融合で、より安全で確実な手術が可能になると考えられる。しかし、それもまた現時点での到達点でしかない。
最新の手術支援機器を取り入れ、対象を明視下において安全で機能的な手術を、術者にも患者さんにも負担を少なく行うことが、私たち耳鼻咽喉科医のブラッドである。
欠畑 誠治 かけはた・せいじ
1981年東京大学理学部中退から東北大学医学部入学、1987年東北大学卒業。耳鼻咽喉科入局、東北労災病院、石巻赤十字病院を経て1994年Yale Universityに留学、2005年弘前大学耳鼻咽喉科助教授、2011年より現職。低侵襲で革新的な経外耳道的内視鏡下耳科手術TEESに取り組み、世界をリードしている。2017年7月号「ドクターの肖像」に登場
※ドクターズマガジン2022年3月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
欠畑 誠治
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
神庭 重信
-
記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
佐藤 理仁
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
山崎 學
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
黒川 清
人気記事ランキング
-
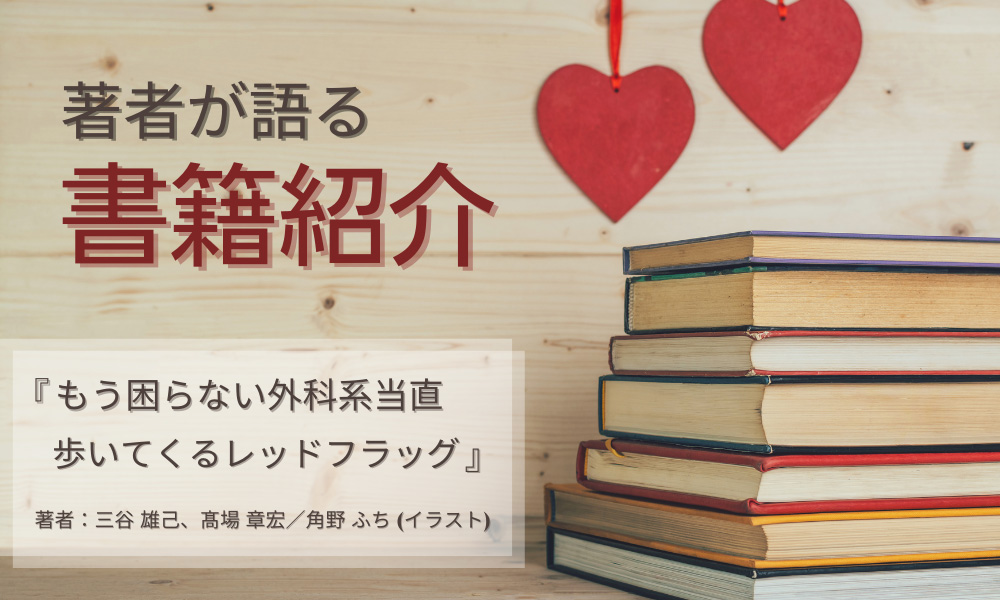
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
三谷 雄己
-
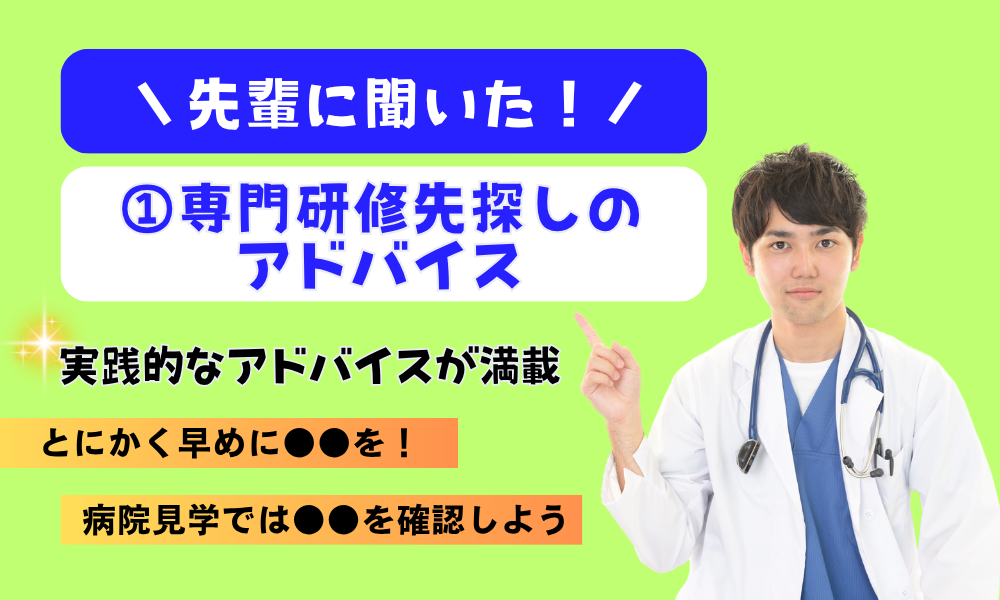
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
-
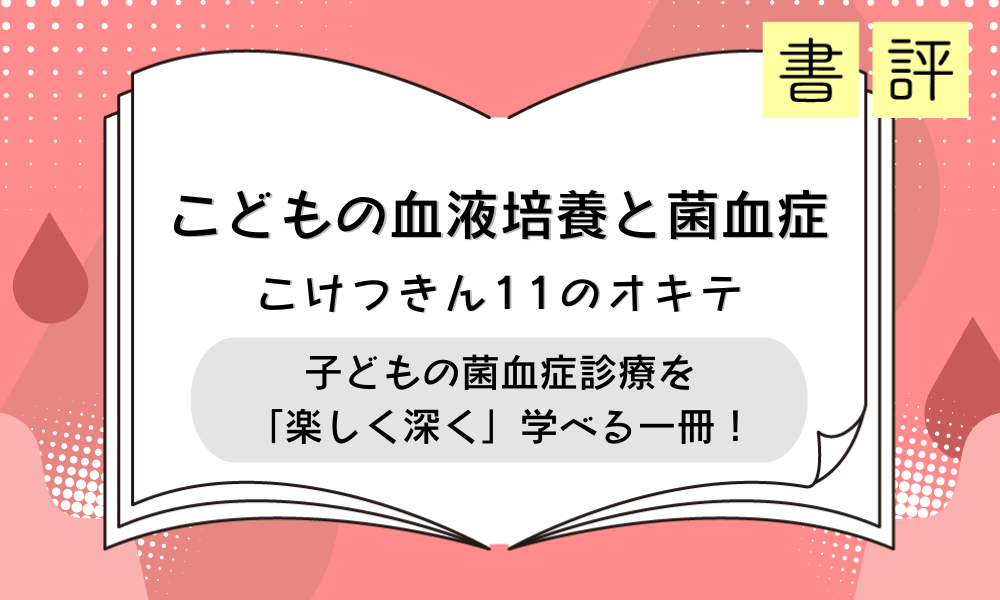
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-
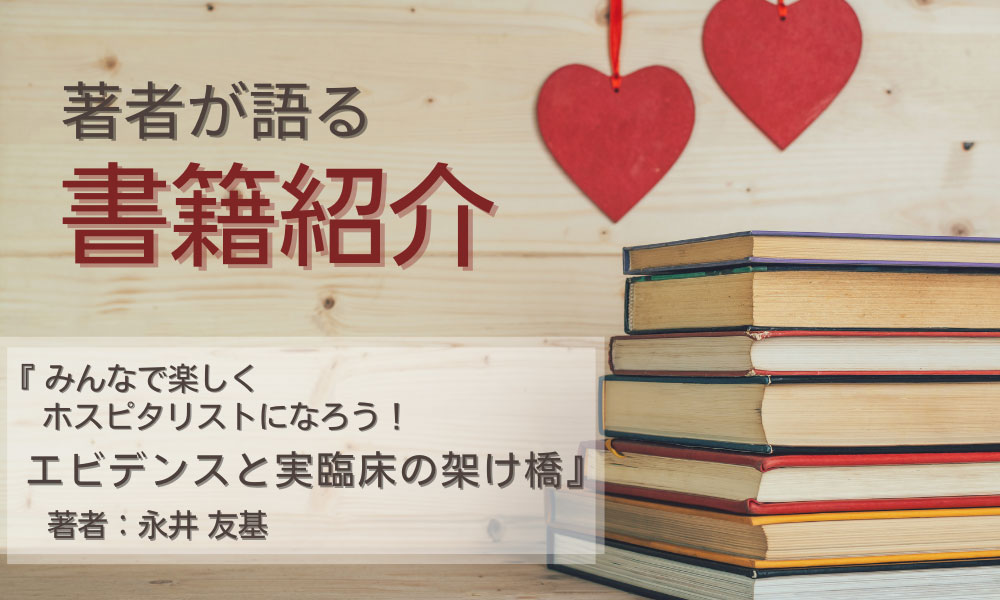
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
永井 友基
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-
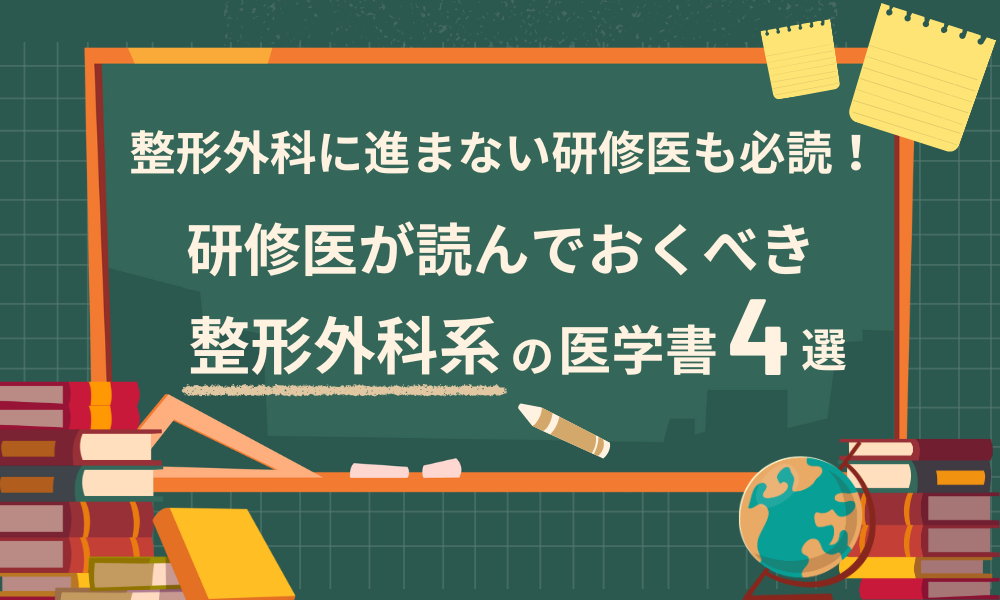
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-
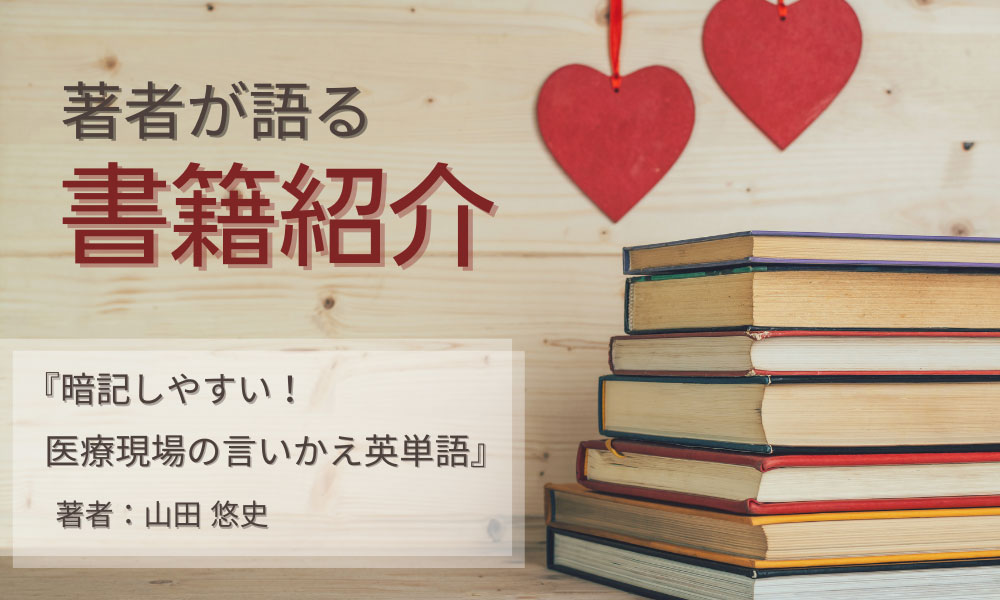
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-
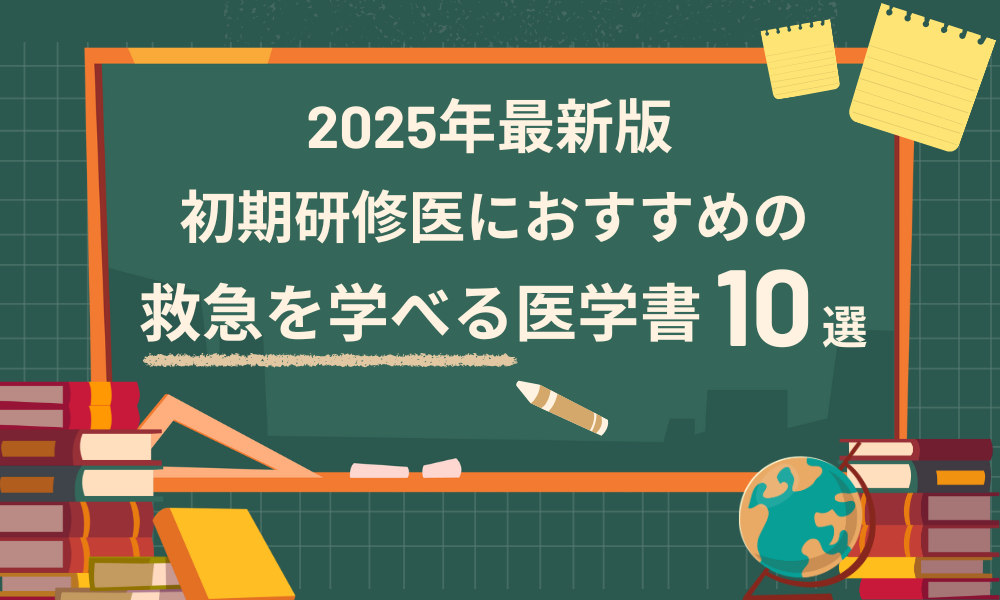
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
