記事・インタビュー
国立療養所邑久光明園 園長
畑野 研太郎
医療は人権を守る行為です。命を守ること、健康をとりもどすこと、可能な限りよいQOLを保つこと、こういった医療の役割は、人が人間らしく生きていくための基であるからです。
しかし残念なことに、結果として医療が人権を抑圧した歴史もまた多く存在します。いま働いている国立療養所邑久光明園は、ハンセン病の回復者のための全国13ある国立療養所の一つです。20年ほど前には約450名おられた当園入所者も現在では約150名となり、平均年齢も60代後半だったものが83歳を超えています。
彼らは、ハンセン病という偏見差別の強い疾患を患ったために、診断された瞬間から「カフカの『変身』の主人公」のように、まるで毒虫になったかのように社会から排除の対象とされたのです。菌を排出しない少菌型の患者でも、「らい予防法」により強制隔離の対象とされるようになったのは1931年のことです。
多くの人々は強制隔離されるにあたり、故郷に残された家族を差別から守るために、戸籍を抜いて入園せざるを得ず、本名を隠し園内名を名のることを強く勧められました。プライバシーのない集団生活で、園内結婚は許可されたものの、女性舎の一室で3組ほどの夫婦が間についたてを立てて夫婦として生活していました。小児期に親から離されて入園した人々も、正式の学校教育は昭和16年になって初めて認められました。
しかしもっと大きな問題は、入所者は、闘病のために療養所に入院させられたにもかかわらず、実際の施設を運営するための業務を、ほぼ自分たちの労働によって行っていたのです。末梢神経障害や視力障害というハンセン病後遺症の障害度は、これらの労働でさらに高度なものとなりました。
この園内作業は時代によって異なりますが、医療・看護業務、亡くなった仲間の火葬場作業まで行わされていました。作業賃は非常に低額(一週間にたばこ二箱程度)でした。まるでナチスの作ったゲットーのようなもので、医療機関の名を冠して行われてきたのです。その後徐々に園内の状況は改善されて行きましたが、「らい予防法」が廃止されるには1996年までかかりました。ハンセン病を患われた方とは、病気という理由で終身刑を受け、人権被害や子供をつくる権利を失い、病気が治った後も社会に帰ることが許されなかった方々です。
また、この病に対する偏見と差別は家族全体が対象となり過酷でした。多くの入所者は家族からも「帰ってこないでくれ。連絡をしないでくれ。」と言われ、亡くなっても骨は故郷のお墓には帰れませんでした。今も園内には納骨堂があり、多くの方はここに眠っています。
なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。ハンセン病療養所も医療機関であり、少なかったとはいえ医療職も仕事をしていました。これらの職員がハンセン病を病んだ人々に強い同情心を持っていたことを疑うことはできません。これらの病をおった人々に社会全体が背を向けていた時代に、中には同情心を持った人がいたことでしょう。
職員たちは、自分の人生をハンセン病をおった人々に寄り添うことに賭けるほど同情心を持っていたのですが、病者の人権を守ることは、結果としてできませんでした。彼らの人権意識は、その時代と社会のスタンダードを超えることができなかったからだと思うのです。同時に、社会の意識が法律で強化され、それ故に偏見差別が強化されることに反対する主体が形成されなかったのではないでしょうか。
今の時代から見返すと、同情心が病者を守るという使命感の裏返しとして強いパターナリズム(それは時代もそうでしたが)の形で発揮されて、本当に病者の思いを受け取って社会を変革する意識には育たなかったためではないかと思います。自らの思い込みによって、当事者の思いを第一にすることがなおざりにされたのではないか思うのです。
いま私たちは、超高齢化した入所者を前にして、入所者の方々の人権を大切にする役割を、具体的にはどのように果たしていけばいいのかと自問する毎日です。何よりも大切なことは、当事者の思いをどこまでも聞く姿勢ではないか、同時に、社会の人権意識を超えた人権意識をつねに求め続けねばならないと考えています。そして、共に生きる者としてこれらの回復者たちによりそって生き続けたいと思いを新たにしている毎日です。
※ドクターズマガジン2013年9月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
畑野 研太郎
人気記事ランキング
-

【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
【2023年最新版】令和の初期研修医1年目におすすめの参考書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
- ライフスタイル
- お金
医師国保のメリットとデメリット、国保との違いとは?
-
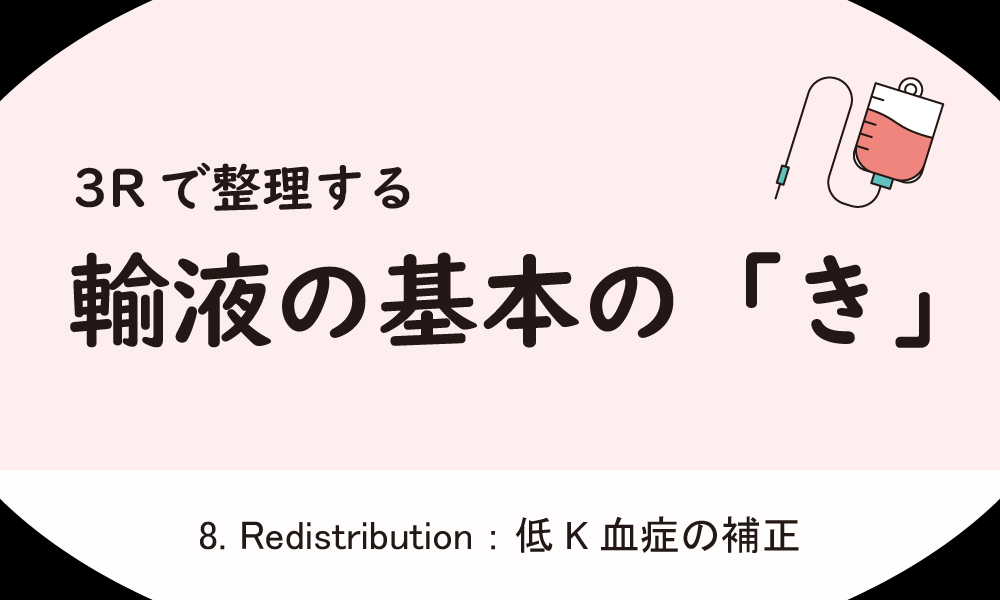
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
- 研修医
- 専攻医・専門医
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低K血症の補正~
柴﨑 俊一
-

【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
- 研修医
- 学習ツール
【医療用語変換を快適に!】医療用語変換辞書“DMiME”の導入を1から解説【画像あり】
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
医師の働き方改革についてよくあるご質問(FAQ)
福島 通子
-

海外で医師として働くためのステップ
- ワークスタイル
- 海外留学
海外で医師として働くためのステップ
-
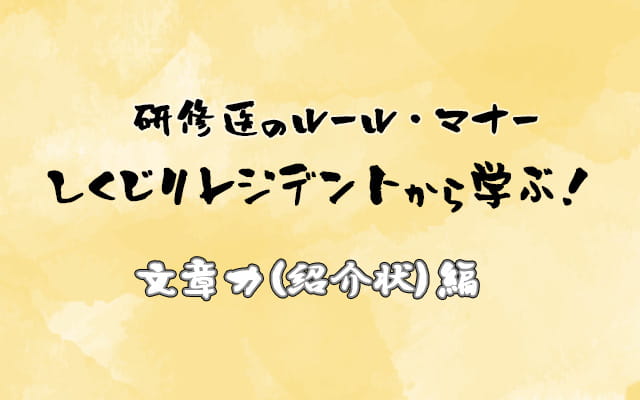
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
- 研修医
- ワークスタイル
しくじりレジデントから学ぶ!研修医のルール・マナー ~文章力(紹介状)編~
三谷 雄己【踊る救急医】
-

食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
- Doctor’s Magazine
食事の再開を遅らせると、下痢が長引く?
名郷直樹、五十嵐博
-

海外の医師免許を取得する方法
- ワークスタイル
- 海外留学
海外の医師免許を取得する方法
-

医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
- 研修医
- ワークスタイル
- 常識の非常識
医学部で教えてくれない労働基準法~働くときに重要な3つのこと~ Vol.1
柴田 綾子
