記事・インタビュー
公益財団法人 朝日生命成人病研究所 所長 兼 附属医院 院長
春日 雅人
私が糖尿病の成因の研究をはじめた1975年は、分子生物学がまさに開花しようとしたときで、以後しばらくは培養細胞に各種遺伝子やその変異体を発現させる研究が盛んでした。1989年に最初の遺伝子欠損マウスの作製が報告され、以後1990年代の後半には遺伝子改変マウスを用いた研究が主流になりました。すなわち、疾病のメカニズムを個体レベルで解析できるようになりました。しかしながら、遺伝子改変マウスを用いた研究が盛んになるとともにマウスを用いた研究の成果をヒトに還元する際の限界も認識されるようになってきました。マウスに関しては遺伝素因ならびに環境要因を均一にして実験を行いますが、ヒトにおいては遺伝素因や環境要因が不均一で多様であり個人によって異なることが明らかになってきました。それではこのように遺伝素因が不均一で、育ってきた環境も多様性に富むヒトについての研究はどうすればよいのでしょうか? その解決策の一つとしては、多くの個体についての情報を扱うことではないかと考えられています。実際私もそのような事例を経験しました。1990年代の後半には、糖尿病でもその候補遺伝子の一塩基が異なるヴァリアント(SNV)について糖尿病の有無でその頻度に差があるか調べる研究が非常に盛んに行われましたが、対象者が何百人というレベルですとその結果に再現性がなかったのですが何千人というレベルで調べると再現性のある結果が得られました。すなわち、糖尿病研究に関しても細胞、マウスの時代を経てヒトのビッグデータを用いて研究できる時代の到来が予想されました。
ヒトのビッグデータを用いる研究の先駆的な例としてゲノム研究をあげることができます。2000年に30億塩基対に及ぶヒトゲノムの配列がほぼ明らかにされ、その中でSNVは現在8000万カ所程度存在すると考えられています。GWAS(ゲノムワイド関連解析)は数千人から数十万人それぞれのヒトゲノム全域を対象に数百万カ所あるSNVについて1カ所ずつ病気の有無でその頻度が異なるかを調べる解析方法です。まさにビッグデータを解析することになりますが、この解析方法が2010年くらいから盛んに行われるようになりました。その要因としては、まずゲノム解析技術の進歩があげられます。それに伴い80万カ所のSNVのタイピングも現在では5000円程度という安価で可能となりました。次にバイオバンクが設立、整備されたことがあげられます。遺伝素因の研究は、自分で検体を集めて解析する時代から、バイオバンクに集められた多数の検体をバイオバンクが解析し、その公開したデータを利用して研究する時代へ変わりつつあります。そしてビッグデータを解析する技術の進歩とそれを担うデータサイエンティストの存在も重要です。
GWAS以前のゲノム研究は、その疾患の原因となり得る候補遺伝子を想定してそのSNVの頻度を調べるという仮説駆動型研究でした。一方、GWASは仮説を立てずにまず網羅的にデータを集めるというデータ駆動型研究です。2型糖尿病でも10万人以上を対象とした1千万カ所以上のSNVのビッグデータを解析して2型糖尿病で統計的に有意に多いSNVが200カ所以上見いだされましたが、個々のSNVがどのような機序で2型糖尿病の発症に関与しているかはほとんどのSNVで不明です。今後、その機序を明らかにするにはそれらのSNVについて仮説を立てそれを細胞、動物モデルなどで検証していく必要があります。
ヒトの遺伝素因ならびに環境要因の不均一性、多様性を考慮するとビッグデータを用いたデータ駆動型研究もこれからの医学研究の一つのありかたと考えられます。そこでは研究の目的に応じて必要な各種のデータを網羅的に独自に入手するか、あるいは公共データベースやバイオバンクから入手し、それらのビッグデータをデータサイエンティストの協力を得て統合・解析し、仮説を生成し、それが正しいかどうかを細胞・マウスなどを用いて検証するという研究の流れになります。文献や自分のデータ、時にはヒラメキなどから仮説を立て、その仮説を細胞・マウスなどで立証することができたらヒトのデータで検討するという仮説駆動型研究によるアプローチも重要であることは今後も変わりません。これからの医学研究はビッグデータに依拠したデータ駆動型研究と仮説駆動型研究が互いに補完しあいながら進展していくと期待されます。
春日 雅人 かすが・まさと
1973年東京大学卒。米国国立衛生研究所、Joslin 糖尿病センターへの留学を経て、1990年神戸大学教授、2004年神戸大学医学部附属病院長、2008年に国立国際医療研究センター研究所長、2012年同センター理事長・総長に就任。2018年より現任。1981年「インスリン受容体のリン酸化」を発見し、世界的に研究が広がった。「ドクターの肖像」2016年11月号に登場。
※ドクターズマガジン2024年11月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
春日 雅人
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
神庭 重信
-
記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
佐藤 理仁
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
山崎 學
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
黒川 清
人気記事ランキング
-
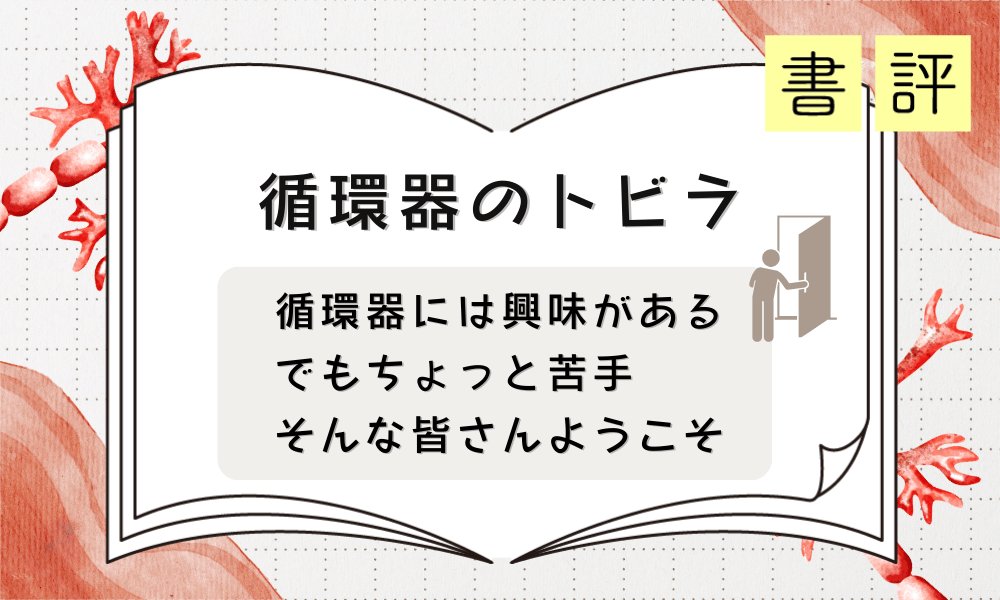
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-
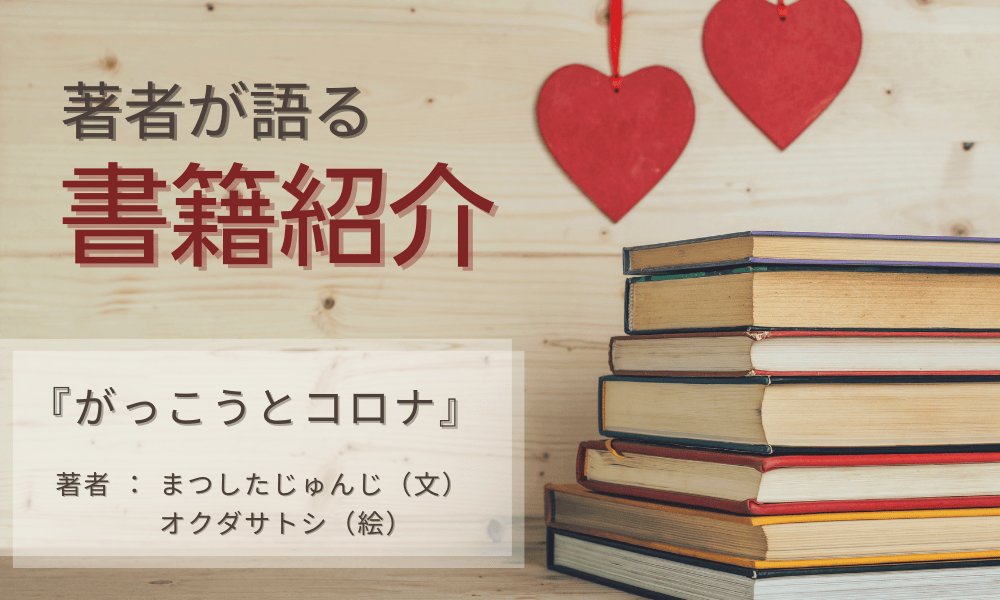
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-
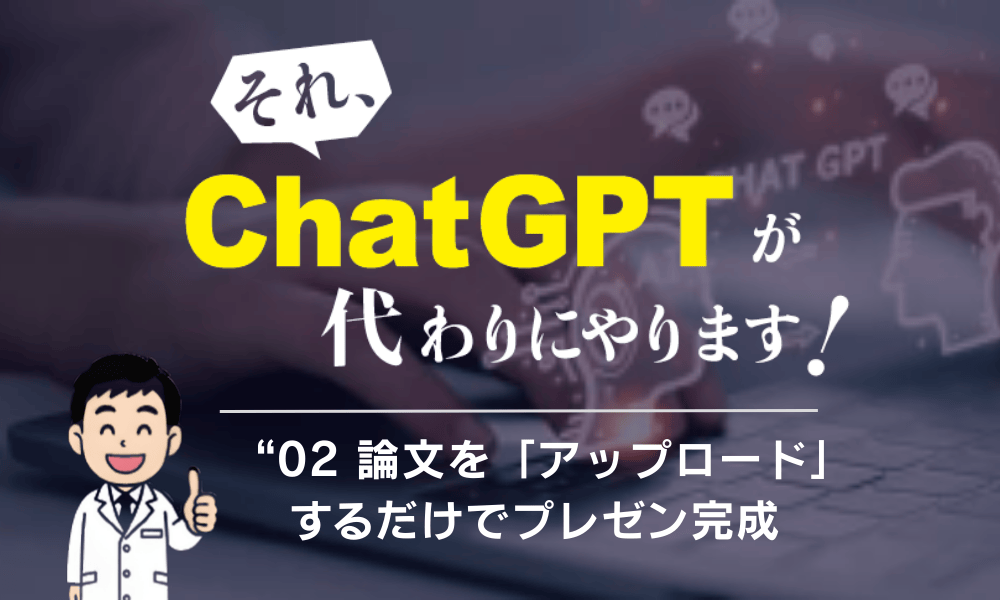
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-
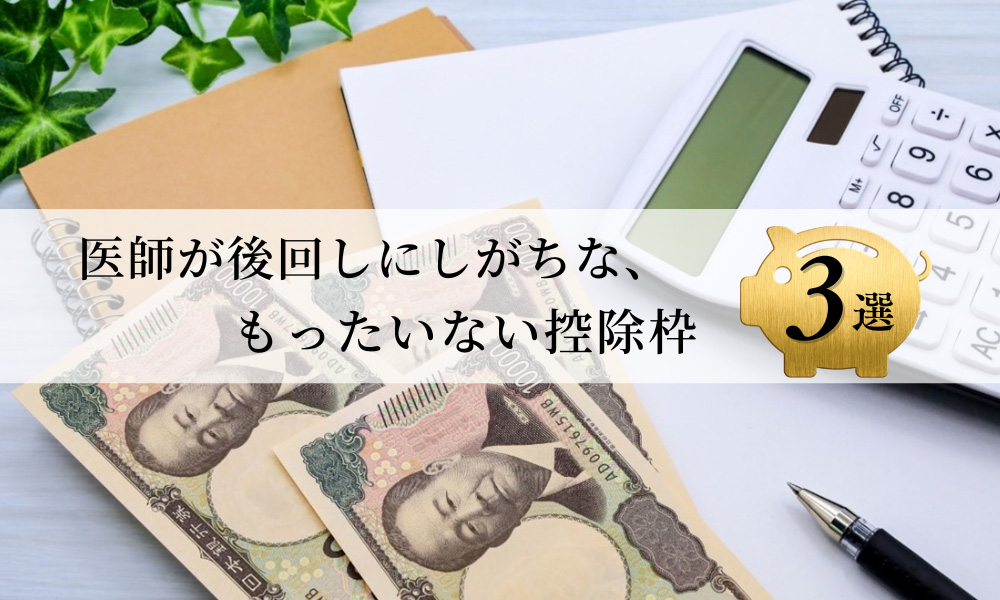
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
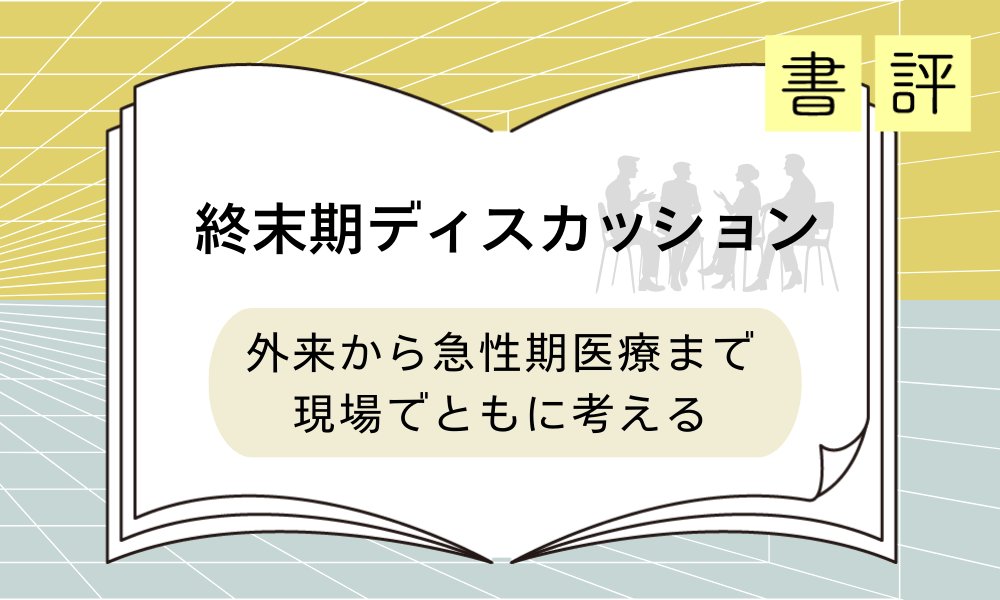
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
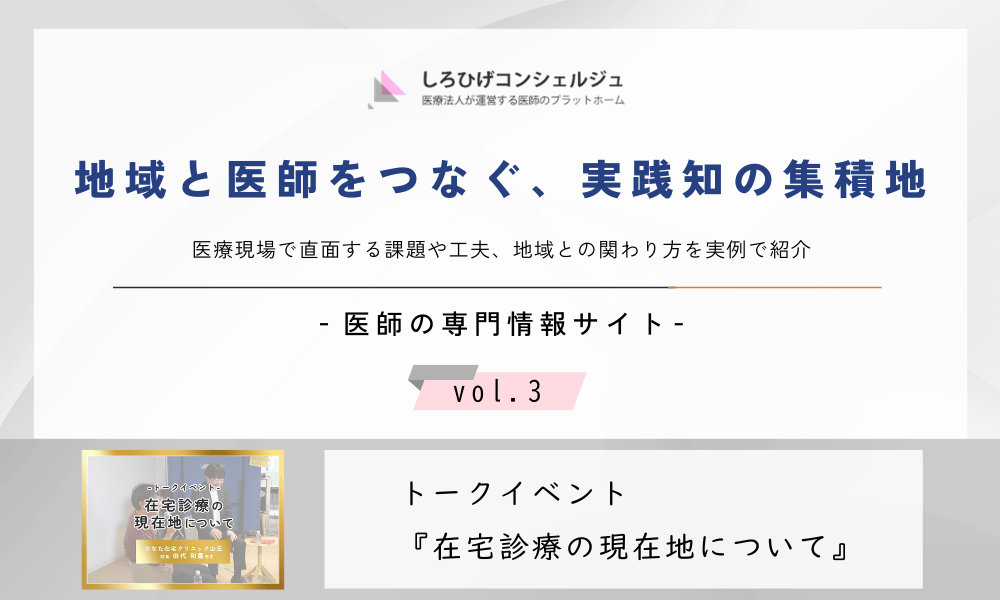
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-
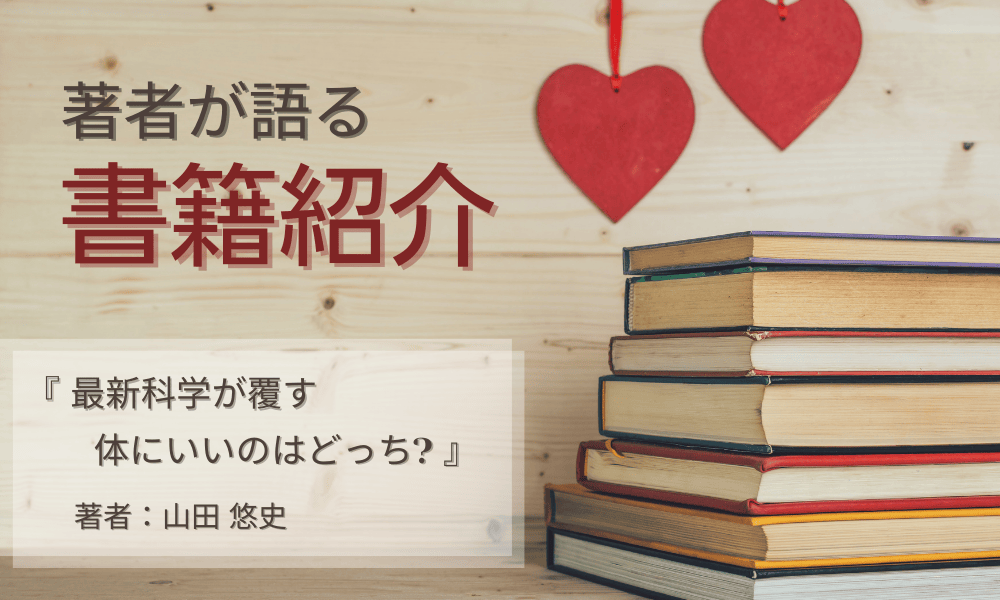
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-
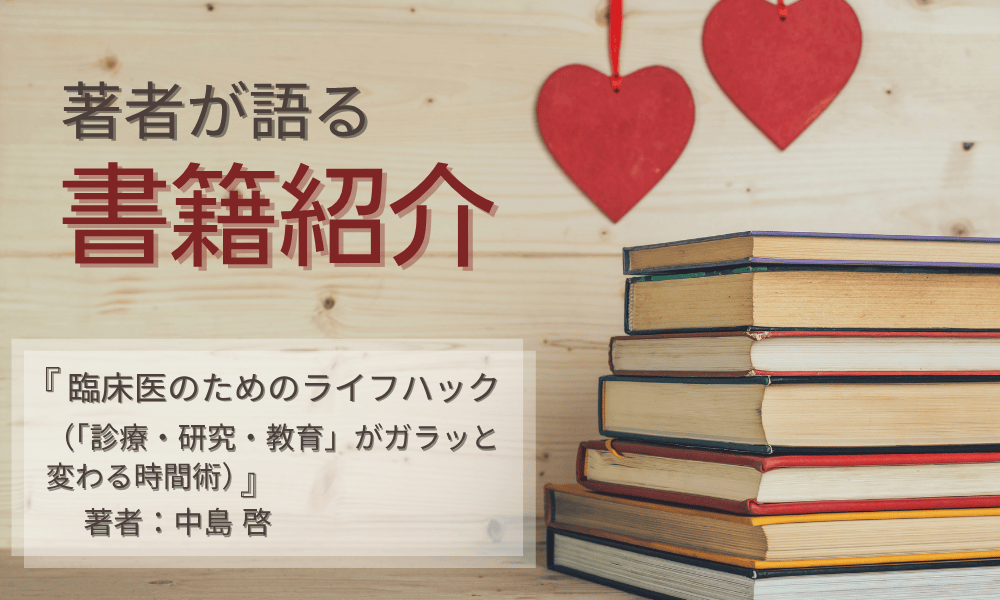
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
