記事・インタビュー

近年、女性医師は増加傾向にあり、医学部入学者の約3分の1を占めるまでになっている。その一方で、未だ女性医師がキャリアを描く際に多様なロールモデルがそろっているとは言い難い。今、最前線で働く女性医師は自らのキャリアや人生をどう描くのかー。バックパッカーを経て医学部に学部編入し、特別養子縁組で親子の縁を持った1歳の子どもを育てながら、産婦人科医として女性の健康支援をする柴田綾子氏。そして、秋田の救急医療を救うため、救急医がたった3人の医局に初めての専攻医として飛び込んだ佐藤佳澄氏。異なる生き方をしてきた2人の女性医師に、それぞれの生き様やキャリアについて思いの丈を語っていただいた。
<お話を伺った方>

柴田 綾子(しばた・あやこ) 淀川キリスト教病院 産婦人科
名古屋大学情報文化学部卒業後、2011年群馬大学医学部を卒業。沖縄県立中部病院での初期研修後、2013年より現職。院内に留まらず各地での後進教育に携わる。SNS やオンラインを活用したセミナーで薬剤師や一般に向けた発信も積極的に行う。主な著書に『女性の救急外来ただいま診断中!』(中外医学社)、『産婦人科研修ポケットガイド』(金芳堂)、『明日からできる! ウィメンズヘルスケア マスト&ミニマム』(診断と治療社)など。『患者さんの悩みにズバリ回答! 女性診療エッセンス100』(日本医事新報社)など。 淀川キリスト教病院の「医師の働き方改革」の推進にも携わる。

佐藤 佳澄(さとう・かすみ) 秋田大学医学部附属病院 高度救命救急センター
秋田大学大学院医学系研究科 救急• 集中治療医学講座 助教。2015年秋田大学医学部を卒業後、2017年に同講座に入局。市中の関連病院などで研鑽を積み、救急科専門医、集中治療専門医を取得。2022年、秋田大学大学院医学系研究科 博士課程 卒業。2022年より現職。血液浄化療法の研究とCase report の執筆・指導に力を入れている。秋田県の救急医療の標準化の必要性を感じ、救急医を志した。2021年には血液浄化の研究に関連し「井上学術奨励賞」受賞、2023年には「第50回 日本集中治療医学会学術集会 若手教育講演部門賞」を受賞した。
3人しかいない救急部医局に初めての専攻医として飛び込んだ

柴田 先生 ︙佐藤先生が救急医療を志した9年前、秋田大学医学部附属病院の救命救急センターには3人しか救急医がいなかったそうですね。
佐藤 先生 :はい、当時の秋田県は極端に救急医が少なく高いニーズがありました。私は大学で初めての専攻医かつ4人目の救急医として、救急医療の世界へ飛び込みました。最初は血液内科を志していたのですが、いざ研修医になってみると、がんの診療よりも体調が悪い人に特化した診療がしたいと思うようになって。そこで救急医を目指し、これまでのほとんどの年月を救命救急センターで働いています。
柴田 先生 ︙私は学部編入で医師になりました。もともとは情報学部に入学し、プログラミングを学んでいたのです。学生時代はバックパッカーで、あちこちの国を回っていました。ところが訪れた発展途上国で、ストリートチルドレンや健康状態が悪化して路肩に座り込む母親などを見て、強い衝撃を受けたのです。そこで、女性を支援する仕事に就きたいと思い、医学部に編入しました。女性支援で最初に考えたのは家庭医だったのですが、実習の時にお産を見て感動し、最終的には産婦人科医を選んで今に至ります。医師になったら女性を支援する仕事をしたり、発展途上国で働いてみたいと思っていましたが、実際に医師になってから海外で活動する医療ボランティアに参加したところ、自分の想像を遥かに超える厳しい世界に驚いたのです。日本の恵まれた環境下で治療することと、水も出ない発展途上国で治療することとではまるで違います。同時に、日本は恵まれているといっても、女性の健康を取り巻く課題が残っていることも見えてきました。今は、日本の女性が抱える課題に取り組むことが私の責務だと思っています。佐藤先生は医師になって、何かギャップを感じたことはありますか。
佐藤 先生 :私は学生時代から、何でもできる医師になりたいと思っていました。ですから、初めはひとつの臓器にとらわれない血液内科を志し、後に救急医を選んだのです。ただ、実際に医師として働き、専門性を高めていけばいくほど、“何でもできる医師”というのは現実的ではないのだと気付かされました。また、自分が3年目の時、すぐ上の先輩は指導医クラスで、年齢が近い仲間がいなかったので、自分自身の方向性や将来を考えるときには葛藤もありました。
柴田 先生 ︙身近にロールモデルがいなかったのですね。どうやってその状況を克服したのですか。
佐藤 先生 :ひとつには今日のようにさまざまな人と話す機会を持つこと、そしてSNSなどを通して幅広い人と関わることで、外に目を向けられるようになりました。それによって、ロールモデルにとらわれないキャリアについて自分なりに考えるようになったのです。
都市部の市中病院と、地方の大学病院が担う役割の違い

佐藤 先生 :柴田先生はずっと市中病院で働かれていますが、その理由はありますか?
柴田 先生 ︙私はもともと家庭医に憧れ、女性診療の中でもプライマリ・ケアをやりたいという思いがありました。そのため、今もずっと市中病院で診療を続けています。初期研修は市中病院の中でも教育的な病院で行いましたが、ベッドサイドでの臨床教育に対する、市中病院の先生のパッションのおかげで今の自分があると感謝しています。一方で、大学病院で働いている先生の学会発表などを見ると、大学が臨床を切り開いていると感じています。私たちは地域の中で日々の診療を行っていますが、大学の先生たちは日常診療の一歩先を作ってくれているのですよね。市中病院だと難易度の高い手術などに対応できないことがあります。そのような時に、バックに大学病院が控えてくれているのは本当にありがたいですね。
佐藤 先生 :確かにそのような役割の差はありますね。私も大学病院で集中治療をスペシャルティとして、白血病の患者さんや造血幹細胞移植後の患者さん、難病で多臓器不全を合併した患者さんなどを治療してきました。そのような患者さんに対応できるのは、大学病院ならではといえます。一方で研究については、地方の大学病院では時代を切り開くとまではいかず、都市部と差があるかもしれません。ただ医局制度が弱まった今でも、大学病院が地域医療を支えている面はあるのだと思います。
柴田 先生 ︙沖縄県で初期研修をした後で、同期が離島の一人医師として赴任し、島の全ての患者さんを診ていく姿に衝撃を受けました。地方では、医師も地域の一部として一体となっている印象がありますね。一方で、医療資源が少ない地域では、医師の責任の重さや診療の幅広さ、求められるものの多さなどを感じます。地方都市のメリットについてはどう思いますか。
佐藤 先生 :医師にとっては、1人の患者さんとじっくり関われる点がメリットかもしれません。私は東京で数カ月ほど初期研修をしたのですが、都市部では本当によく転院しますよね。とくに救命救急センターなど、ある程度回復したらすぐにどこかへ転院していきます。人工呼吸器がついているような患者さんが転院するのを見て、とても驚きました。一方で私たちは、患者さんが集中治療室を出てから回復し、最終的にリハビリのみになるまで、長い間関わり続けます。転院まで60日ほど入院していることもあり、患者さんをじっくり診ていくことができる環境でもあります。これは都市部の病院にはない特徴かもしれません。
小児科や産婦人科は救急医療とのさらなる連携が必要

柴田 先生 ︙佐藤先生は、ダイヤモンド・プリンセス号にも派遣されたのですよね。
佐藤 先生 :1日だけですが、DMATの派遣で行きました。高齢者が多く、併存症もあり、とても感情的になっている人がいるかと思えば、その場に慣れきったりエクササイズをしている人もいたり、何というか異世界のようでした。自分が感染したらどうしようという心理的なストレスも強く、1日で3日分の診療くらい疲れました。ですが、ドアに「Thank you」と貼り紙がされていたり置き手紙があったりなど、極限状態でありながら人の感情の深い部分に触れたような体験もできました。
柴田 先生 ︙救急の先生は災害時など、いつもフロントラインにいますよね。産婦人科医は妊婦さんを診るのでいつも守られ診察しているように感じます。最前線にいてくださる救急の先生にはいつも感謝しています。
佐藤 先生 :柴田先生の著書にもあったと思うのですが、今妊婦さんの数自体が少ないので、災害にしても出血にしても母子の危機的な状況に慣れている医師が少ないことが課題ですね。外科や内科の先生と比べて、産婦人科や小児科の先生とは本当に関わりが少ないので、もっと産婦人科の先生とセッションできることがあればいいのですが……。
柴田 先生 ︙そうですね。産婦人科医は出血には慣れているのですが、バイタルやエアウェイの管理などは慣れていません。その意味では、こちらが出血対応をし、救急や麻酔科の先生にバイタルや気道管理をお願いするなどの連携ができれば、さらに助けられる妊婦さんが増えるように思います。
柴田 綾子、佐藤 佳澄
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Cross Talk】スペシャル対談:総合診療医編<後編>
- 研修医
- ワークスタイル
- Doctor’s Magazine
- 専攻医・専門医
【Cross Talk】スペシャル対談:総合診療医編<後編>
佐々木 淳、加藤 良太朗
-
記事

【Cross Talk】スペシャル対談:総合診療医編<前編>
- 研修医
- ワークスタイル
- Doctor’s Magazine
- 専攻医・専門医
【Cross Talk】スペシャル対談:総合診療医編<前編>
佐々木 淳、加藤 良太朗
-
記事

【Cross Talk】スペシャル対談:アレルギー編
- 研修医
- ワークスタイル
- Doctor’s Magazine
- 専攻医・専門医
【Cross Talk】スペシャル対談:アレルギー編
海老澤 元宏、佐藤 さくら
-
記事

【Cross Talk】スペシャル対談:救急科編
- 研修医
- ワークスタイル
- Doctor’s Magazine
- 専攻医・専門医
【Cross Talk】スペシャル対談:救急科編
志賀 隆、坂本 壮
人気記事ランキング
-

著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
三谷 雄己
-
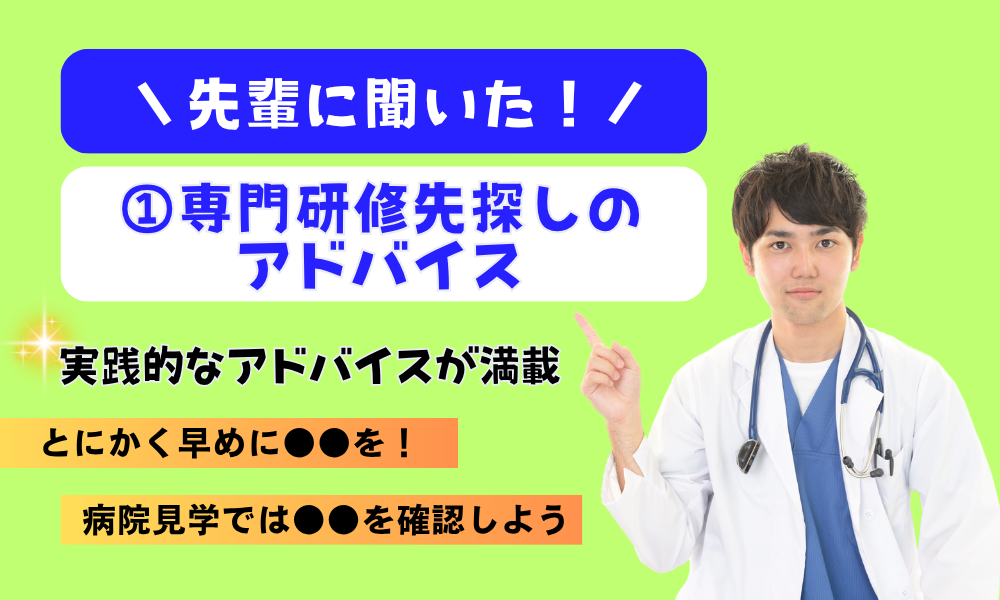
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
-
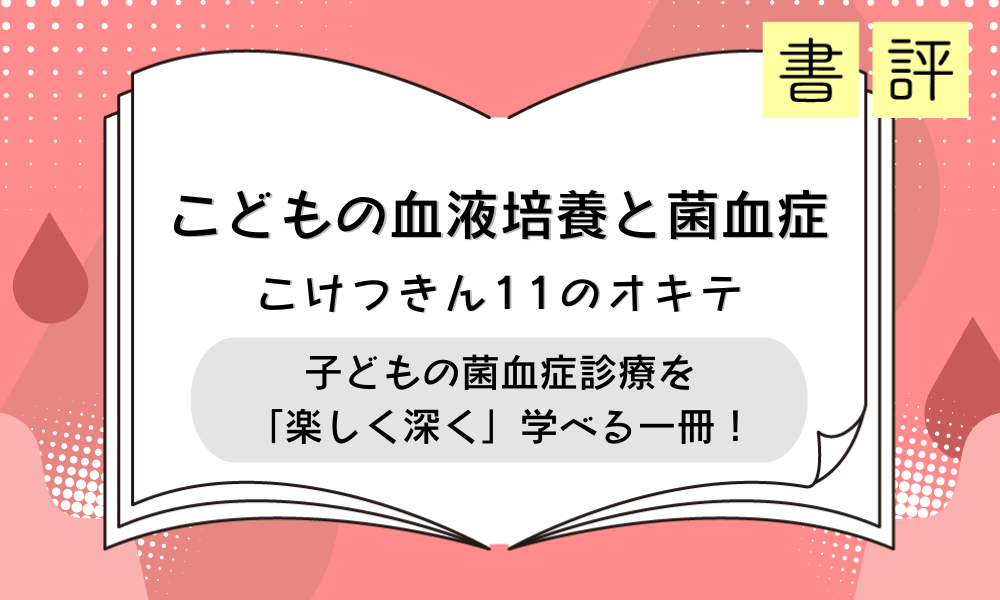
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
永井 友基
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-
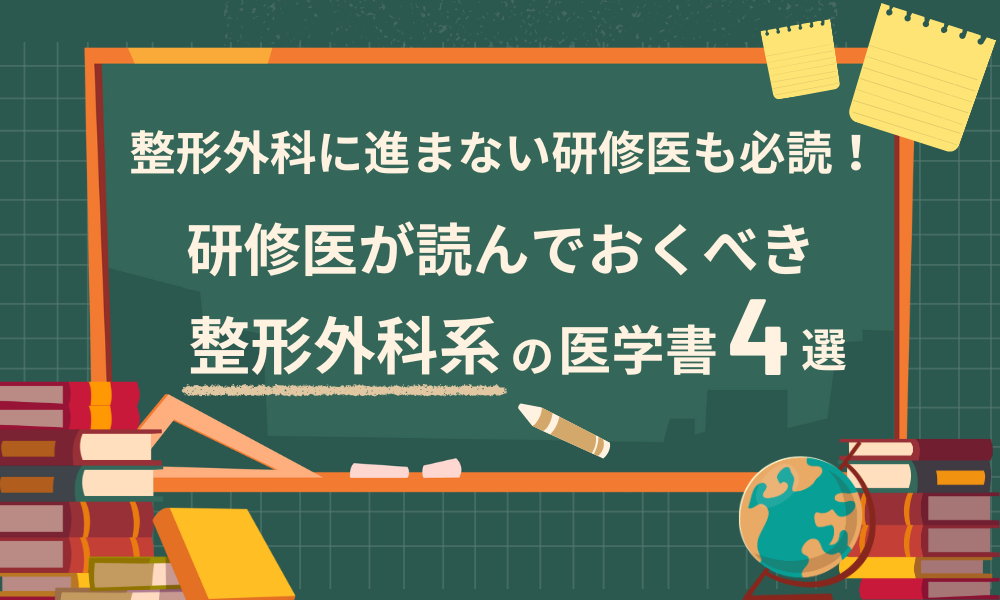
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-

2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
