記事・インタビュー
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床神経科学分野 教授
和泉 唯信
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は全身の筋力低下が進行し、構音障害・嚥下障害、呼吸筋麻痺も生じる神経難病である。治療薬としてこれまでのリルゾール、エダラボンに加えて、新たにメコバラミン、トフェルセンが2024年に承認された。この2剤の承認までの過程からALS治療薬開発の困難さと臨床評価の課題を指摘し、現在の取り組みを紹介したい。
メコバラミンはすでに末梢性神経障害などで保険適用があったが、高用量でALSに適応追加になった。本薬は2006年からエーザイ社が第Ⅱ/Ⅲ相試験を発症3年以内の患者を対象に実施したが、主要評価項目(生存期間と機能評価)で有効性を示せなかった。しかし、発症1年以内の早期ALS患者に限定した事後解析では、主要評価項目において有効性が示唆された。エーザイ社は開発を断念したが、日本医療研究開発機構(AMED)の資金提供によって徳島大学病院を主幹として医師主導治験(発症1年以内、第Ⅲ相試験)を実施した(研究開発代表者:梶龍兒)。比較的短期間の二重盲検期間になったため、機能評価のみの検証となったが、前試験の事後解析を再現する有効性を示した。この結果を受けエーザイ社が承認申請を行い2024年9月に薬事承認を取得した。この経緯は、薬剤によっては、より早期に投与を開始すれば有効な場合があることを示した。経時的に神経変性が進行するALSでは早期の治療介入が必要なのは衆目の一致するところではあるが、従来の想定より早い介入が必要な可能性が示唆された。しかし、一般に発症1年以内にALSの診断に至る割合は低い。その理由の一つに、ALSの主症状である上下肢の筋力低下、構音障害・嚥下障害を生じた場合に初診する診療科として、一般内科、整形外科、耳鼻咽喉科、脳神経外科などが多く、脳神経内科の受診に遅れが生じうるという現状がある。しかもALSは頚椎症と鑑別を要するのみならず、実際に頚椎症が併存する場合が少なくなく、手術にならないまでもリハビリテーションなどを行い経過をみる期間が生じ脳神経内科の受診が遅れる場合もある。薬剤や治験薬を遅滞なく患者に届けるためには、関係する診療科にもALSという疾患を十分認識してもらう必要があり、その啓発が重要である。
次にトフェルセンであるが、これはSOD1遺伝子変異をもつALSのみが対象となる。日本においてALSのうち家族性は約10%であり、そのうちの約30%がSOD1遺伝子変異によるため、一部のALS患者のみが対象になるが、ALSに対しての初めての核酸医薬でありその期待は大きい。このトフェルセンは米国食品医薬品局(FDA)で2023年4月に迅速承認されたが、日本での承認は2024年12月であり、ドラッグ・ラグを生じた。その一因としてFDAではバイオマーカーによる代替エンドポイントでの評価を認めているが、日本では認めていないことがある。
各国で治療薬の規制要件が異なることはやむを得ないが、ある程度の共通性は必要である。欧州医薬品庁(EMA)とFDAはALS治療薬開発に関するガイドラインを公表しているが、日本ではまだ作成されていない。また、現在日本が参加しているALSの国際共同第Ⅲ相試験は極めて少なく、いつドラッグ・ラグ/ロスになってもおかしくない。こうした状況を踏まえ、2024年度からAMEDの委託で「筋萎縮性側索硬化症に対する治療薬の臨床評価ガイドライン作成に関する研究」(研究開発代表者:和泉唯信)に取り組むこととなった。国際的な共通認識を踏まえつつ、ALS治療薬2剤(エダラボン、メコバラミン)を開発した日本ならではの視点を取り入れた、日本版臨床評価ガイドラインを作成する。今後の課題であるバイオマーカーやリアルワールドデータの活用についても研究し記載する。海外のスタートアップなどへの情報発信を意識し、成果は日本語版と併せて英語版も発表する予定である。また、本ガイドライン作成は研究への患者・市民参画(PPI)を実践して進めている。初年度から患者・市民セミナーをハイブリッドで実施し、患者、患者団体、製薬企業、医薬品医療機器総合機構(PMDA)などからも多くの参加があり有意義な意見交換ができた。本ガイドライン作成の取り組みを通じて、難病において治療法開発を推進するために臨床試験の進め方や、それを取り巻く環境を整備することの重要性が一層認識されることを期待している。
和泉 唯信 いずみ・ゆいしん
1989 年北海道大学理学部数学科卒業から1995年徳島大学医学部卒業。広島大学、住友病院での研修を経て、2001年徳島大学へ。2008年医療法人微風会理事長、社会福祉法人慈照会理事長、2020年徳島大学大学院臨床神経科学分野(神経内科)教授に就任。僧侶でもあり、小説『七帝柔道記』の登場人物としても知られている。2022年6月号「ドクターの肖像」に登場。
※ドクターズマガジン2025年10月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
和泉 唯信
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
神庭 重信
-
記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
佐藤 理仁
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
山崎 學
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
黒川 清
関連する記事・インタビュー
-
記事

【Doctor’s Opinion】DPCが日本の医療にもたらしたものは何か~医療ビッグデータの行方~
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】DPCが日本の医療にもたらしたものは何か~医療ビッグデータの行方~
松田 晋哉
-
記事

【Doctor’s Opinion】ゲノム医療の出口と三世代コホート調査
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】ゲノム医療の出口と三世代コホート調査
栗山 進一
-
記事

【Doctor’s Opinion】DNR & DNAR
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】DNR & DNAR
安倍 弘彦
-
記事

【Doctor’s Opinion】我々がめざす専門医制度とは
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】我々がめざす専門医制度とは
池田 康夫
関連カテゴリ
人気記事ランキング
-
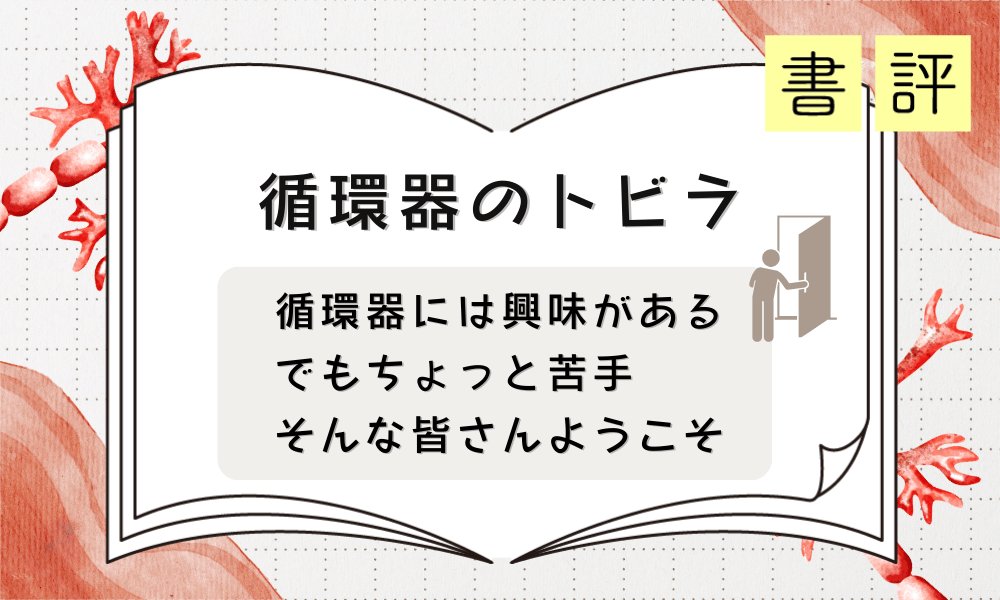
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-
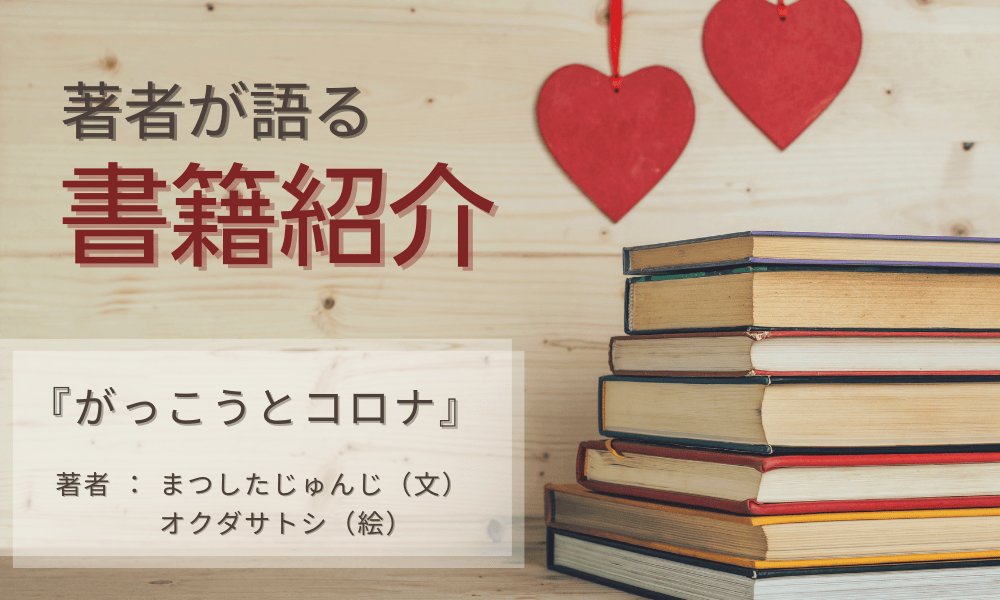
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-
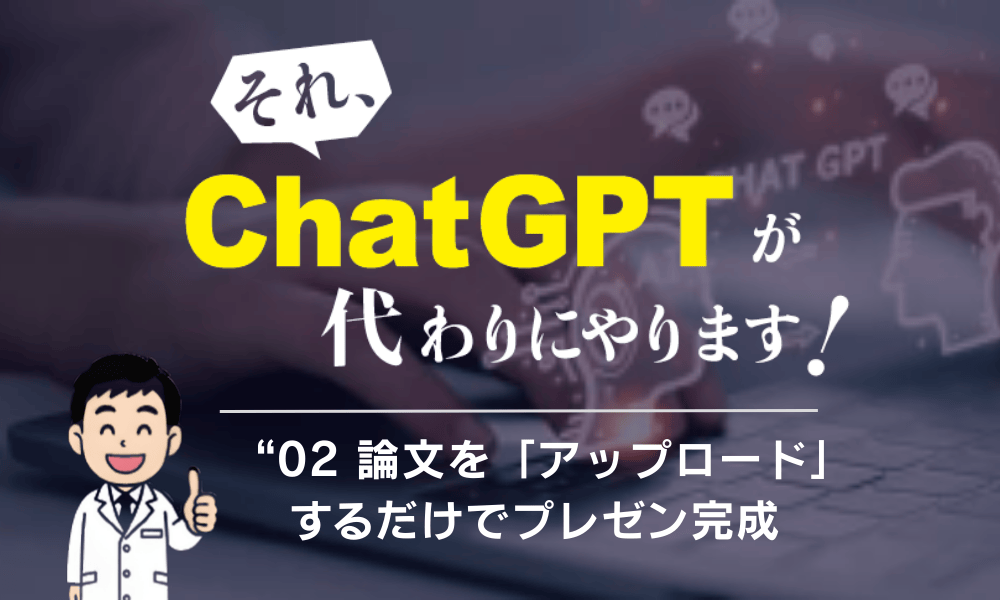
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-
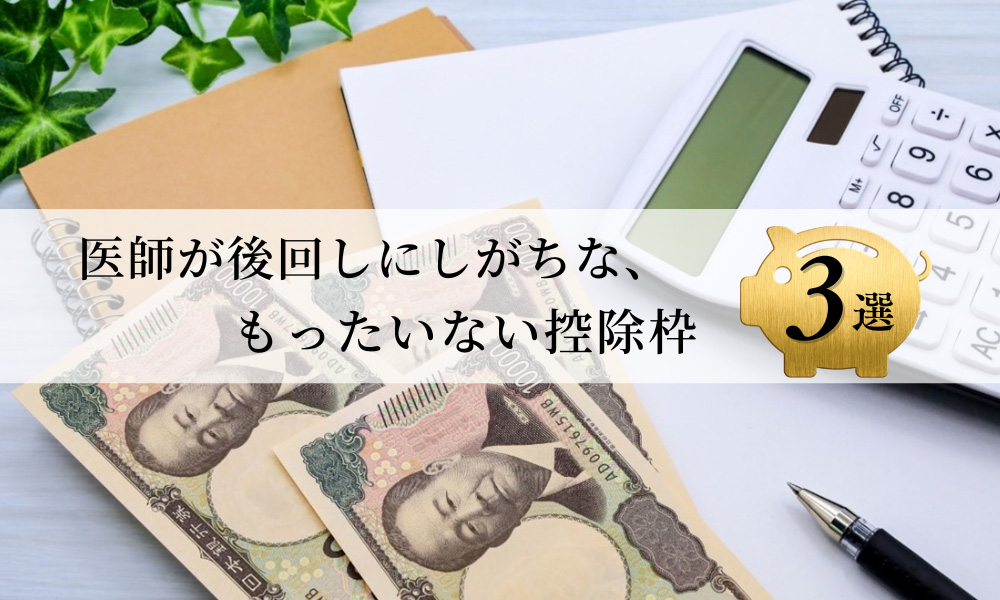
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
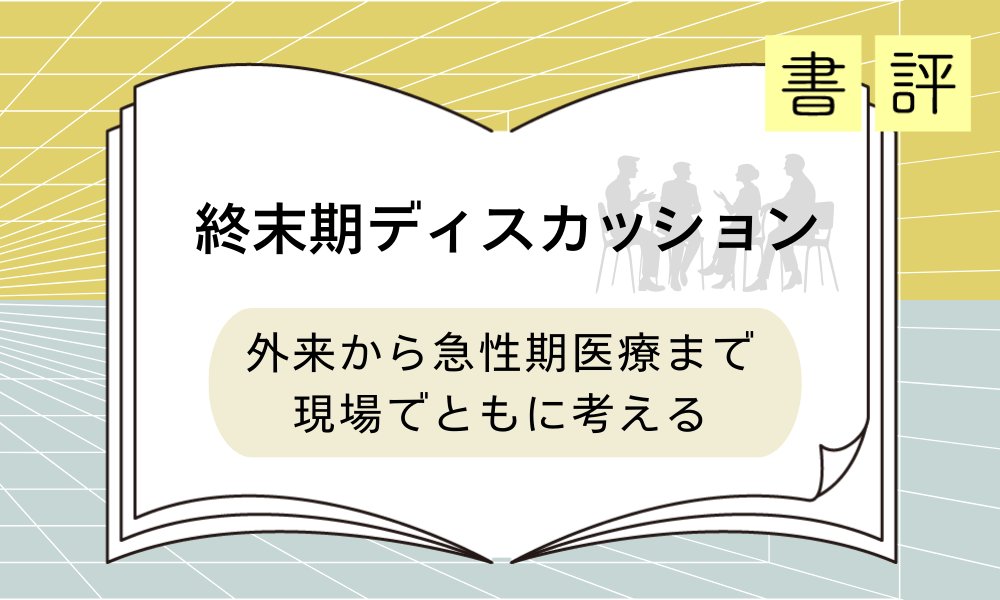
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
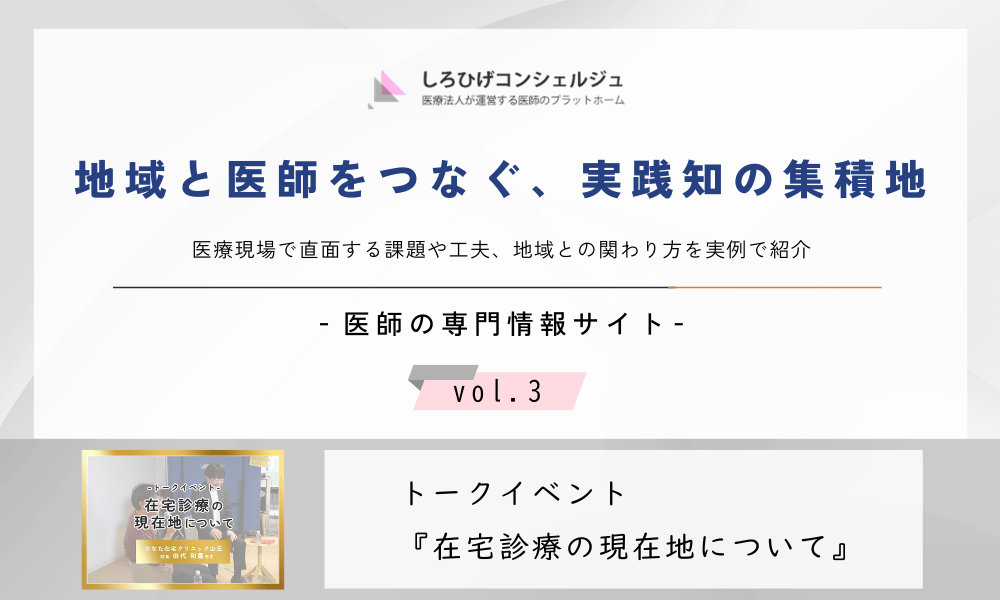
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-
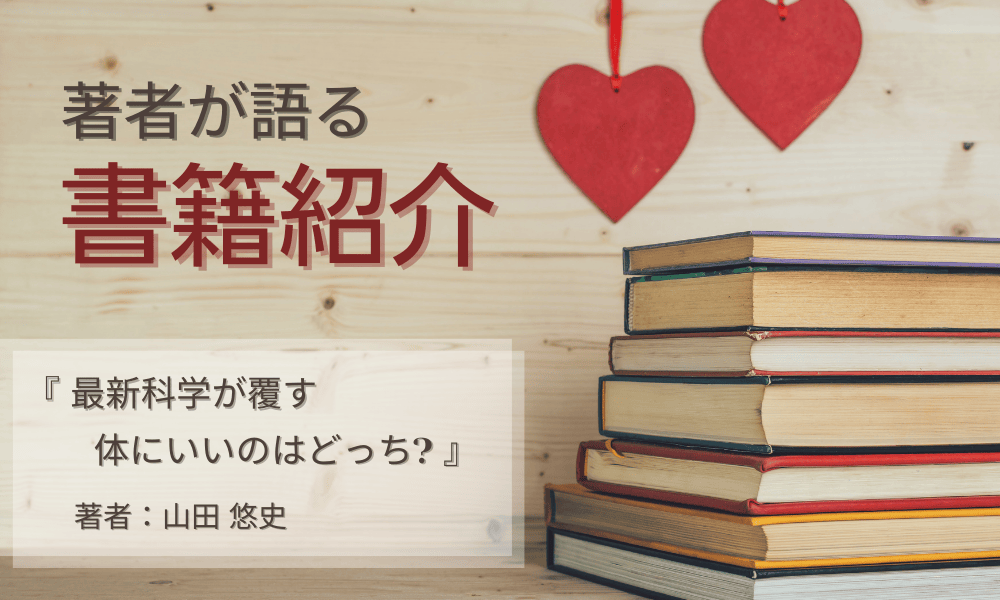
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-
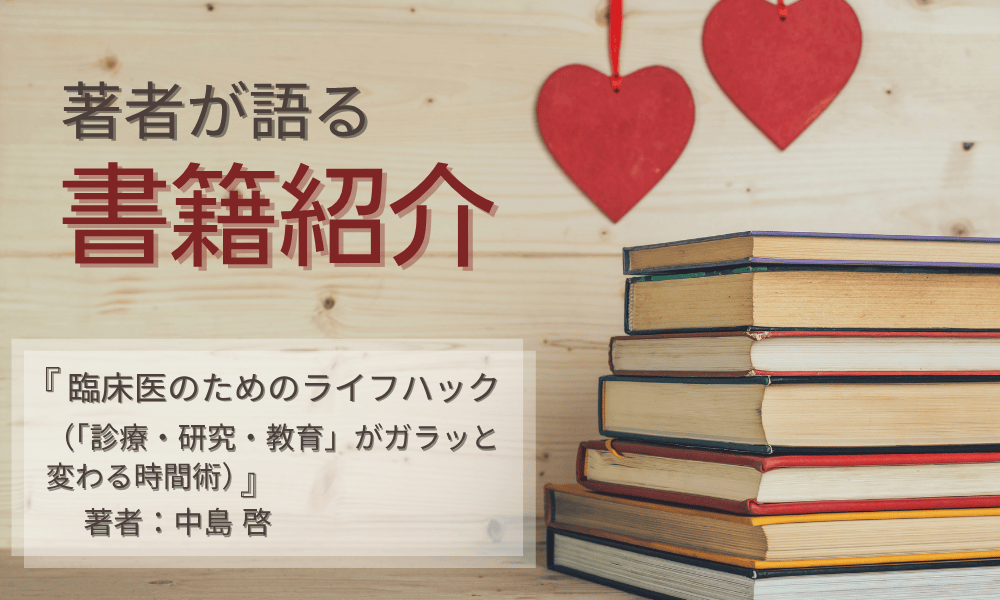
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
