記事・インタビュー
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 院長
門脇 孝
肥満症とClinical obesity
世界でもわが国でも肥満者が増加している。わが国では約2800万人といわれ、特に若年・中年男性の肥満の増加が著しい。日本肥満学会(Japan Society for the Study of Obesity : JASSO)では、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、BMI25以上のものを肥満(Obesity)と定義し、肥満の中で、肥満に起因し関連する健康障害を合併するか、その合併が予想され医学的に減量を必要とする疾患を、肥満症(Obesity disease)と定義する。健康障害には耐糖能異常・2型糖尿病、脂質異常症、高血圧、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、変形性関節症などの運動器疾患、肥満関連腎臓病など、計11が挙げられる。日本人は内臓脂肪蓄積を認めやすく、CT検査などにより確認されると、現在健康障害を伴っていなくても肥満症と診断する。JASSOは、肥満の中から肥満症を取り出し治療の対象とするという肥満症の定義と診断基準を2000年に提唱した。2025年1月14日、The Lancet Diabetes & Endocrinology(Lancet D & E)誌に「Clinical obesityの概念と診断」というコンセンサスステートメントが掲載された。これは、各国の肥満・肥満症の専門家がLancet Commissionという委員会を作り、時間をかけてデルファイ法で意見集約したものである。そこでは、JASSOの「肥満症」に相当する疾患を“Clinical obesity”と呼び、概念に大きな差はない。JASSOが「肥満症」の概念を今回のLancet Commissionより25年も前に提案しわが国で活用してきた先駆性は高く評価される。
肥満症治療の変革
肥満症治療では、まず食事・運動・行動療法を行い、3%程度の減量でも2型糖尿病など健康障害の改善が認められる。一方、NAFLD、肥満関連腎臓病、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、運動器疾患の改善にはしばしば10~20%程度の減量が必要である。このレベルの減量は、食事・運動・行動療法のみでは得られにくい。そこで、高度肥満症(BMI≧35)などの症例には、従来、薬物療法で効果の高いものが無かったことから、減量手術が考慮されてきた。その状況を一変させたのが、GLP-1受容体作動薬のセマグルチド(ウゴービ®)およびGIP・GLP-1受容体作動薬のチルゼパチド(ゼップバウンド®)である。これらの薬剤では、日本人でも15~20%を超えるような減量を達成することができる(Lancet D & E : 193-206, March 2022, Lancet D & E 2025年2月27日)。ウゴービ®は2024年2月22日、ゼップバウンド®は2025年4月11日から臨床使用が可能となった。食欲の抑制や満腹感の促進により食事量が減少することが減量の一番の作用機序である。また、併せて、健康障害が著明に改善する。心血管疾患、総死亡、慢性腎臓病の抑制などのエビデンスも得られてきている。今後は、食事・運動・行動療法で不十分な場合には、まず、これらの抗肥満薬を考慮することになる。同時に、本剤は健康障害を伴わない(従って肥満症とは診断されない)肥満には用いるべきではなく、また、美容・痩身・ダイエット等の目的で用いる薬剤ではない点には十分留意すべきである。サイエンス誌は、2023年のブレイクスルーオブザイヤーにGLP-1受容体作動薬を選んだ。また、ノーベル生理学・医学賞の受賞者を輩出することで知られているラスカー賞(2024年)は、GLP-1の発見や臨床に貢献した2人のアカデミア研究者とノボノルディスクファーマの研究者に与えられた。
オベシティ・スティグマ(Obesity stigma)
肥満者に対するスティグマ(Obesity stigma)は、肥満症の治療は自己管理の問題(自己責任)で医療を受ける対象ではないという誤解や偏見を引き起こし、肥満症の適切な治療の機会が奪われることにつながる。従来、食事・運動・行動療法といった、肥満症を有する患者の努力に専ら依存する治療以外に肥満症治療の選択肢が少なかったことも、オベシティ・スティグマの形成に影響を及ぼしてきた。有効性の高い抗肥満薬の登場がオベシティ・スティグマの改善・解消につながることを期待する。
門脇 孝 かどわき・たかし
1978年東京大学卒業。1986年にアメリカ国立衛生研究所糖尿病部門客員研究員として留学。1996年東京大学第三内科講師、2003年に同大学糖尿病・代謝内科教授に就任。2011年東京大学医学部附属病院病院長、2012年同大学トランスレーショナルリサーチ機構長、2020年虎の門病院院長に就任。2型糖尿病の臨床と研究における世界的権威。2021年11月号「ドクターの肖像」に登場。
※ドクターズマガジン2025年6月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
門脇 孝
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
神庭 重信
-
記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
佐藤 理仁
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
山崎 學
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
黒川 清
関連する記事・インタビュー
-
記事

【Doctor’s Opinion】脳血管内治療の最新情報
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】脳血管内治療の最新情報
吉村 紳一
-
記事

【Doctor’s Opinion】救急専門医から見た災害医療
- Doctor’s Magazine
- 専攻医・専門医
【Doctor’s Opinion】救急専門医から見た災害医療
小倉 真治
-
記事

【Doctor’s Opinion】地域の実情に合わせた医療提供体制を目指して
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】地域の実情に合わせた医療提供体制を目指して
中西 敏夫
-
記事

【Doctor’s Opinion】医師と住民が語り合うことが地域病院を支える
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】医師と住民が語り合うことが地域病院を支える
佐藤 元美
関連カテゴリ
人気記事ランキング
-
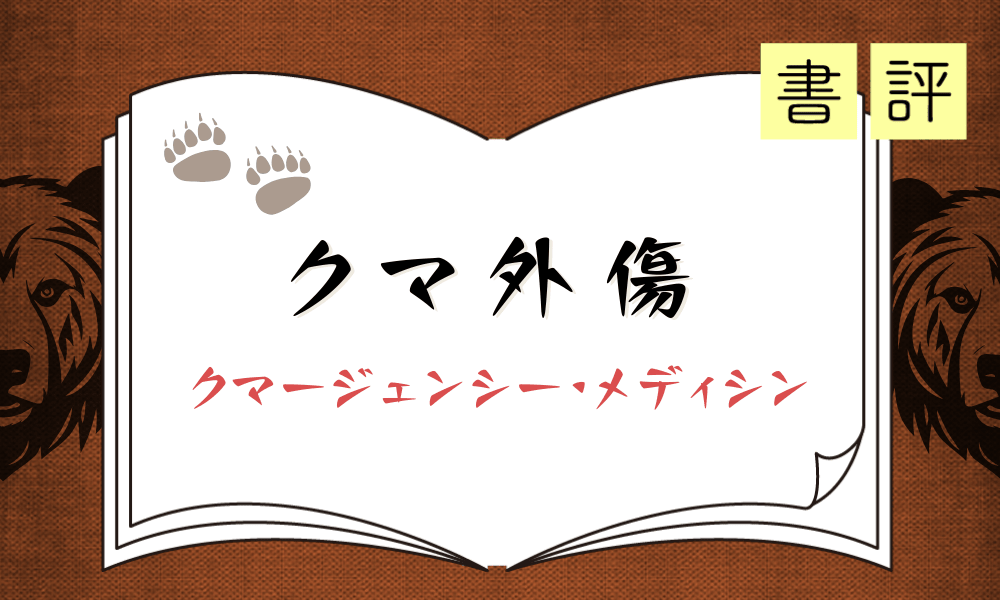
書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
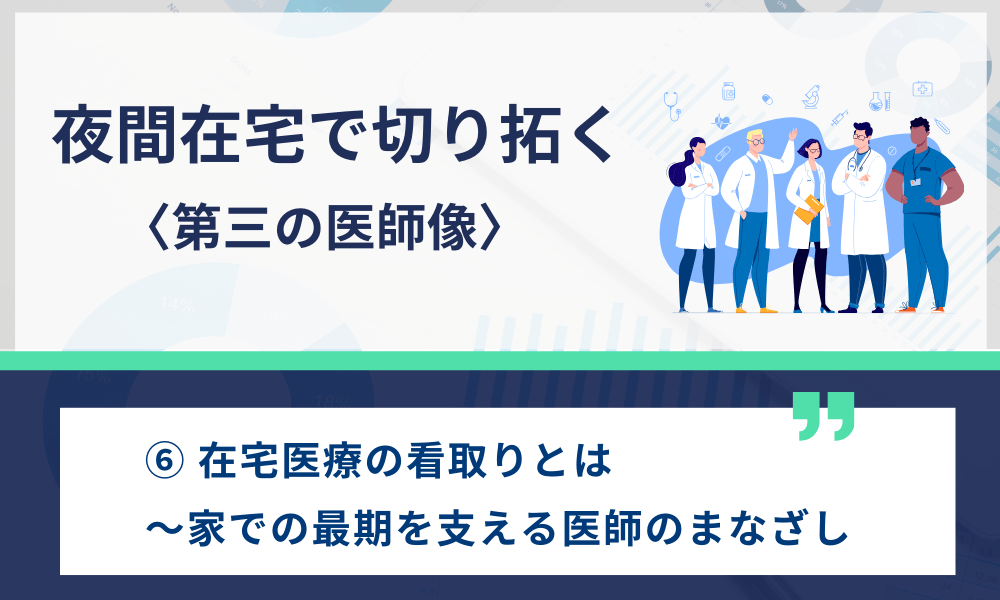
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし
- イベント取材・広報
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし
株式会社on call
-
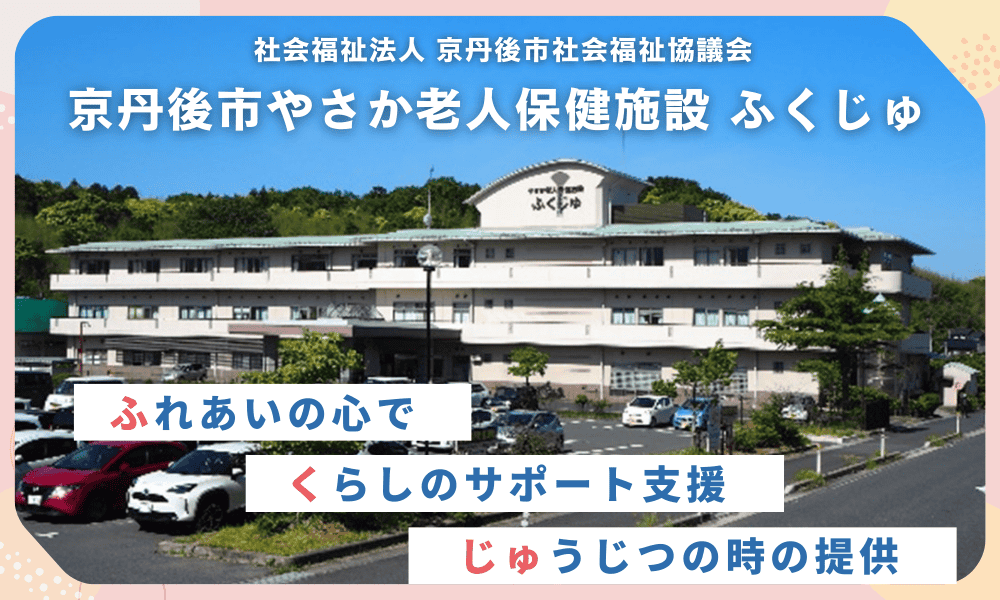
ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供
京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ
-
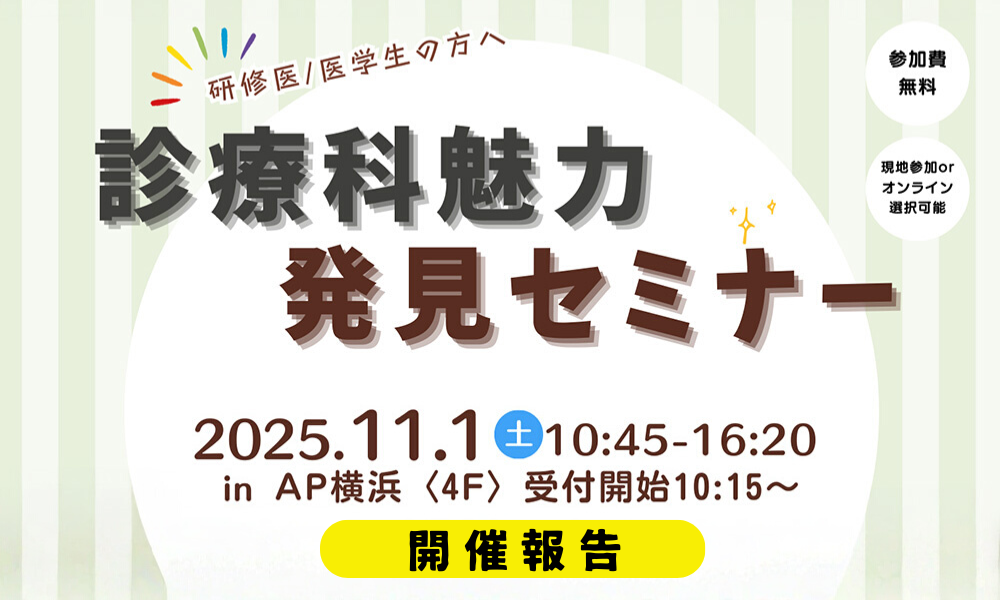
【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025
- イベント取材・広報
【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025
令和7年度神奈川県地域医療支援センターイベント業務運営事務局
-
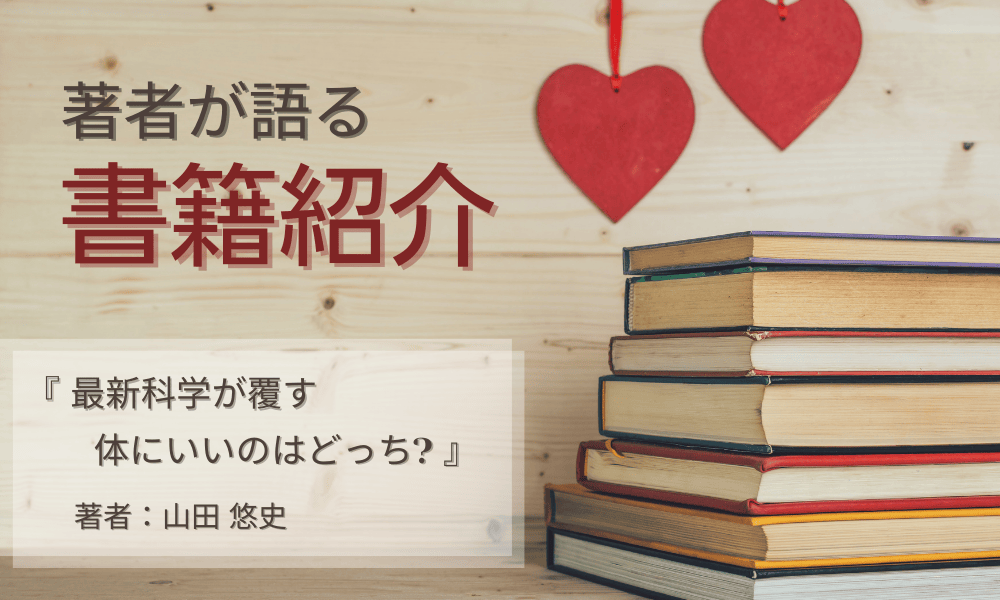
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定
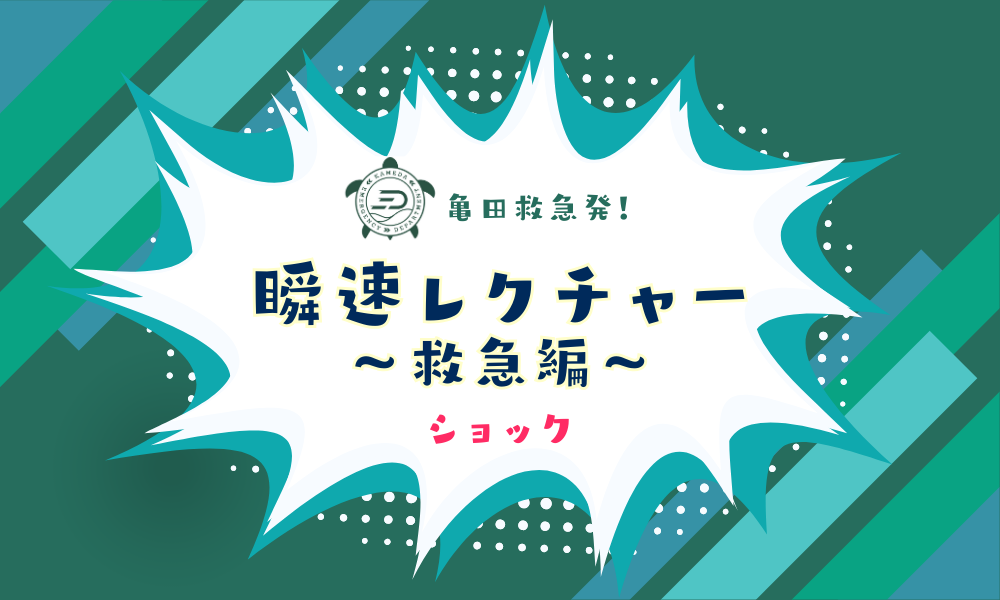
瞬速レクチャー~救急編~「ショック」
- 研修医
瞬速レクチャー~救急編~「ショック」
-

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―
-
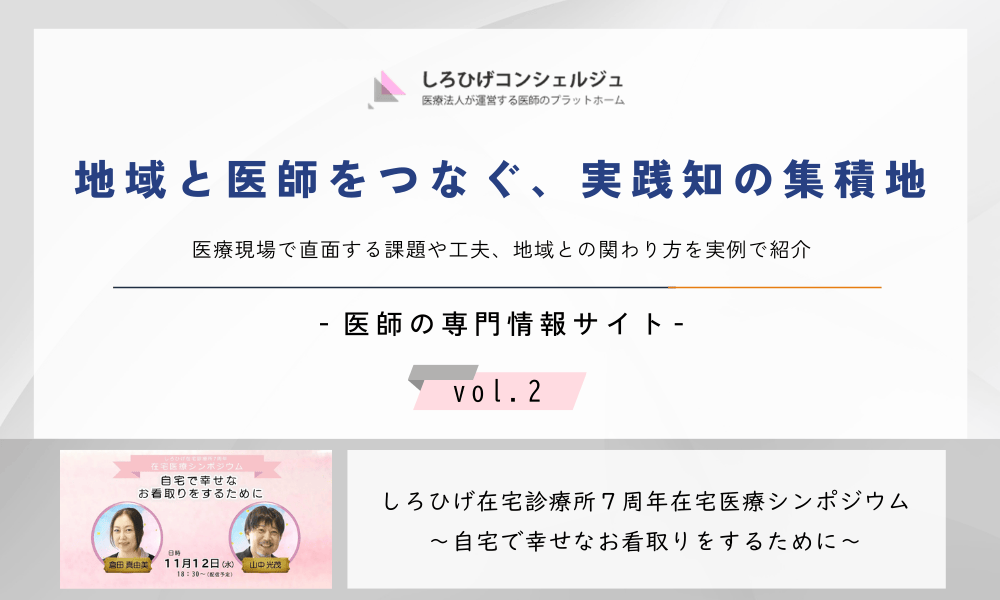
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】
しろひげコンシェルジュ
-
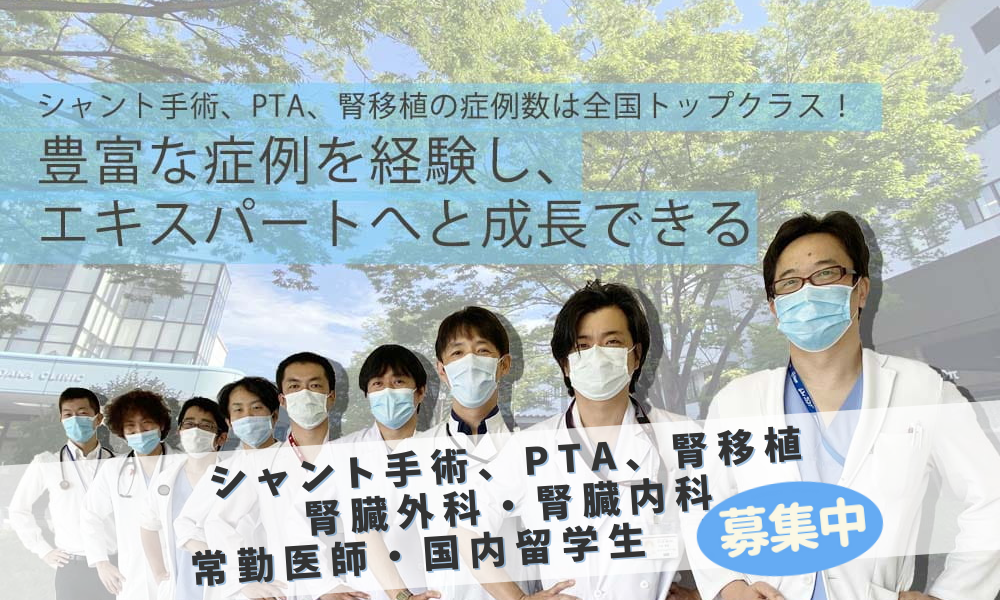
【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる
- ワークスタイル
- 就職・転職
【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる
添野 真嗣、久保 隆史
-
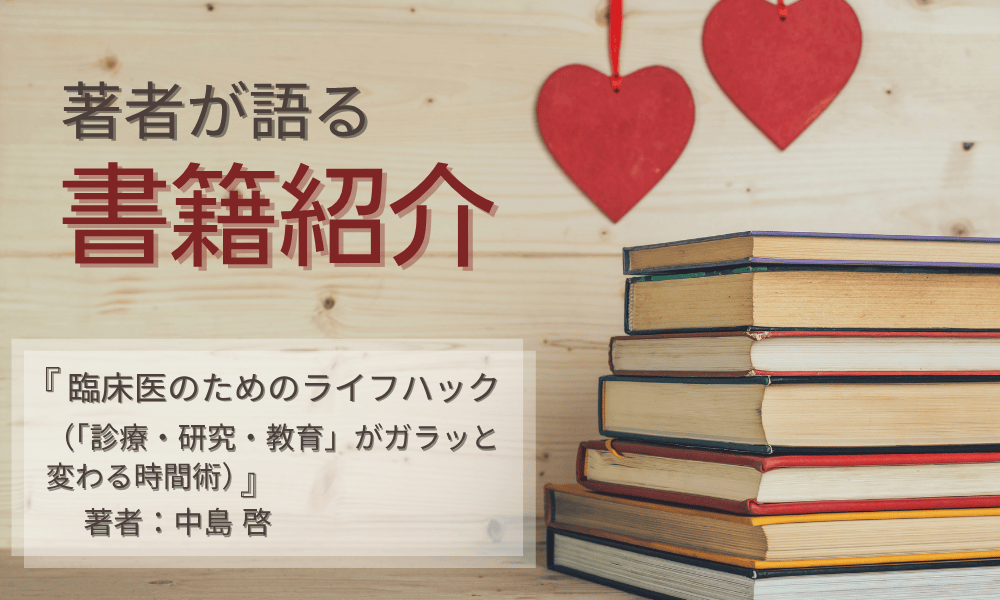
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
