記事・インタビュー
跡見学園 理事長/日中医学協会 理事長/国際医学研究振興財団 理事長
跡見 裕
AIの進歩は著しく、すでに司法試験や医師国家試験の合格レベルを超えている。ChatGPT のような生成AI(生成AIとは、人間が行うような新たなアイディアやコンテンツを作り出す能力を持つ人工頭脳の一種※ )のすごさはすぐに実感することができるが、汎用人工知能(AGI.:Artificial GeneralIntelligence)は数年後には実用化が、さらには人間を超えた超知能も夢物語ではない。研究分野ではすでに研究立案から、論文作成までAIなくしては進まないようにもなっており、教育分野でもAI利用に関してさまざまな議論がされている。
私は1970年に医学部を卒業したが、当時大学が混乱の極みにあった時代である。医学部を中心に全国に広がった学生の運動で、学校閉鎖や学生のストライキがあり、2年間は授業が全くなく全員が留年を経験した。学生が提起した問題点の一つに“大学の自治が教授会の自治とイコールではない”ことがあったが、その中に教育・研究も教授の独占ではないことも含まれていた。ストライキ中の学生討議ではこの問題も語られたが、その後政治闘争となっていく中でうやむやになってしまった。体系的な授業がないまま卒業・国試合格し医師になったが、毎日が不安の連続であった。遅れを取り戻そうと、勤務先の病院で仲間を募り朝7時から1時間の勉強会を持ったが、知識の断片的なものが得られただけとの感は拭い切れなかった。
約35年前、医学部長に呼ばれ某大学でユニークな教育をしているので見学してこいと言われた。手術の予定がいっぱい詰まっているのに、わざわざ学生教育のために時間を取られるのか(医学教育に対する認識はこの程度)との思いが強かった。授業形態の一つは少人数で設問を討議するもので、PBLのはしりでもあった。教員の確保が大変そうで、医学部長には「興味ある点もありますが、本学では時期尚早では」と報告した。当時も解剖学教室では他大学の教授や臨床教授による授業評価や、学生同士によるpeer review などが行われており、頼まれて評価委員を務めながら教授の熱意に感心したものである。そのうちに私は医師国家試験の出題委員になった。就任時には今までにない斬新な問題を作成しようと張り切った。ベッドサイドでしっかりと患者さんを見ていなければ解答できないような問題を考え、作成委員会でも新しい観点からの出題であると高い評価を得た。国試後に本屋でこっそりと国試解答集を見た。最初に見た解答集では、臨床に即した良問とあり、嬉しくなった。別の解答集も期待しながら見てみると、“出題者の意図が全く不明”とあり解答も間違っていた。自信を持って作成したのだが、こんなに評価が分かれる問題は医師国家試験として相応しくないと大いに反省し、翌年度からは当たり障りのない記憶力に頼る出題をしてしまった。
その後医学部長、学長を経験し、さらに医学教育振興財団の常務理事など教育に携わってきた。医学教育は先進的に改革がなされてきた分野で、それを支えているのは医学教育関係者の献身であり、医学教育は専門性をしっかりと確立してきた。一方問題、解答の作成にAIが使用されるようになり、従来型の教育法やテストの持つ意義が問われつつある。医師国家試験を見てもわかるように、残念ながら知識に偏った出題が少なくなく、詰め込み型の教育がいまだ中心である。インターネットで適切な情報が瞬時に得られるならば、知識を詰め込むよりもっと有意義なことを学んではどうなのか。
あまりに医学・医療の進歩は早い。基礎でも臨床でも学ぶべきことが多すぎる。この対応に追われて肝心なことがおろそかになってはいないか。AIの進歩・普及により(高級な機械より安い人件費の)医師は下請け作業的なことをすることになろうか?そうかもしれないし、それにはまだ時間がかかるかもしれない。ただ知識量ではAIにかなわなくなることは間違いない。
“疾患に苦しんでいる個々の人”に直接対応するのが医療であり、それを成すのは、個々の医療人である。瞬時に膨大な知識を提供することはAIの仕事である。しかしAIやそれと共にあるロボットに治療を受けることとは別問題である。他者の考えることを正確に理解しその気持ちをしっかりと共有でき、悩める人に共感する心を持つ医療人こそが患者さんの信頼を勝ち取るはずである。豊かな感性を磨く医学教育が最も必要とされるだろう。
跡見 裕 あとみ・ゆたか
1970年東京大学卒業。専門は消化器外科(膵臓・胆道外科)。1988年カリフォルニア大学サンフランシスコ校客員研究員として留学、1992年東京大学第一外科教授、2004年杏林大学医学部長を経て2010年杏林大学学長、医学教育振興財団常務理事。2023年より現職。日本膵臓学会、日本消化器外科学会、日本臨床外科学会の会長を歴任。アジアオセアニア膵臓学会を設立し初代のPresident となった。「ドクターの肖像」2012年5月号に登場。
※ドクターズマガジン2025年1月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
跡見 裕
このシリーズの記事一覧
-
記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”
神庭 重信
-
記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義
佐藤 理仁
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”
山崎 學
-
記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
- Doctor’s Magazine
【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”
黒川 清
人気記事ランキング
-
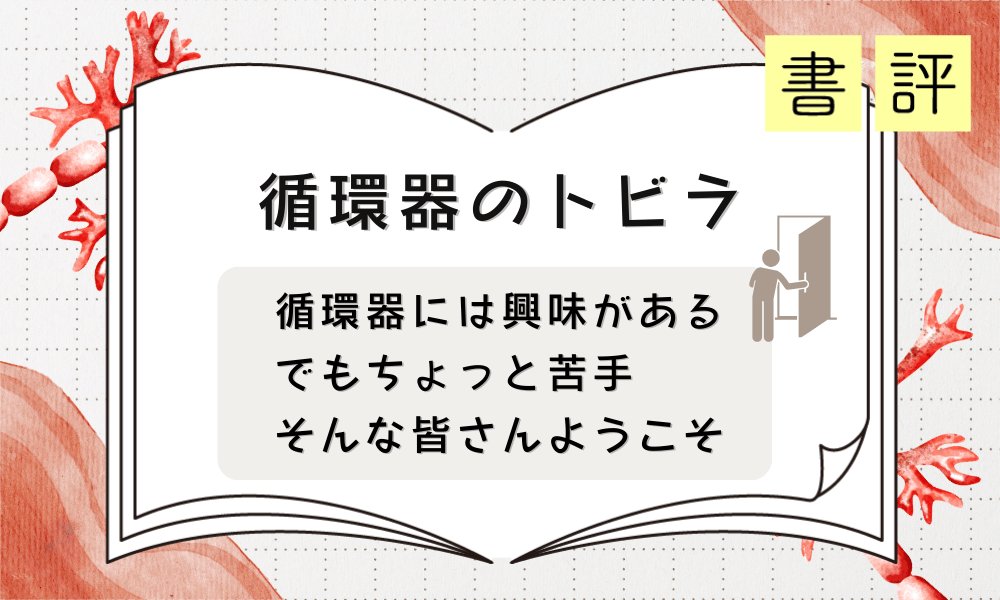
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-
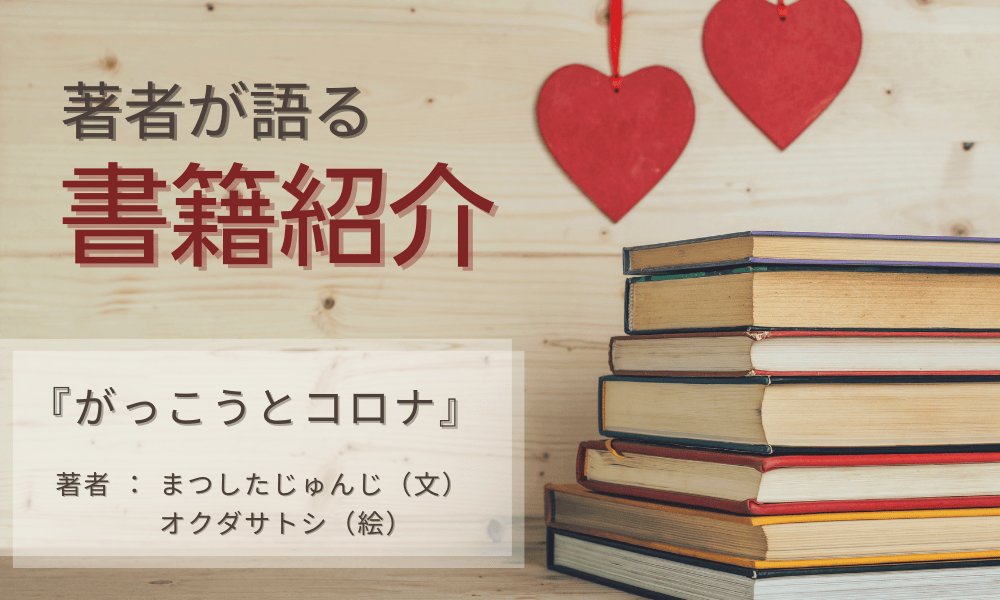
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-
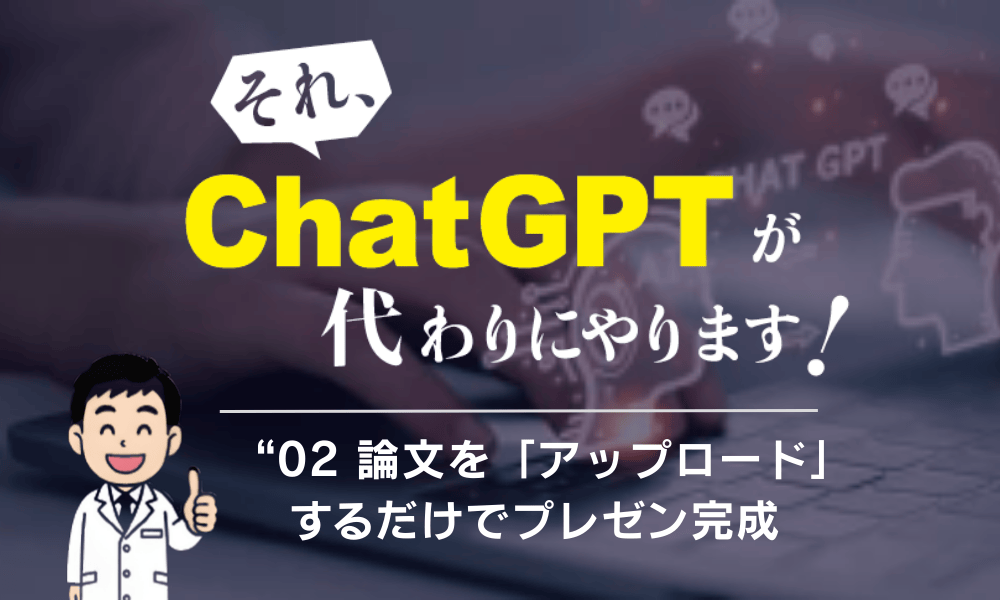
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-
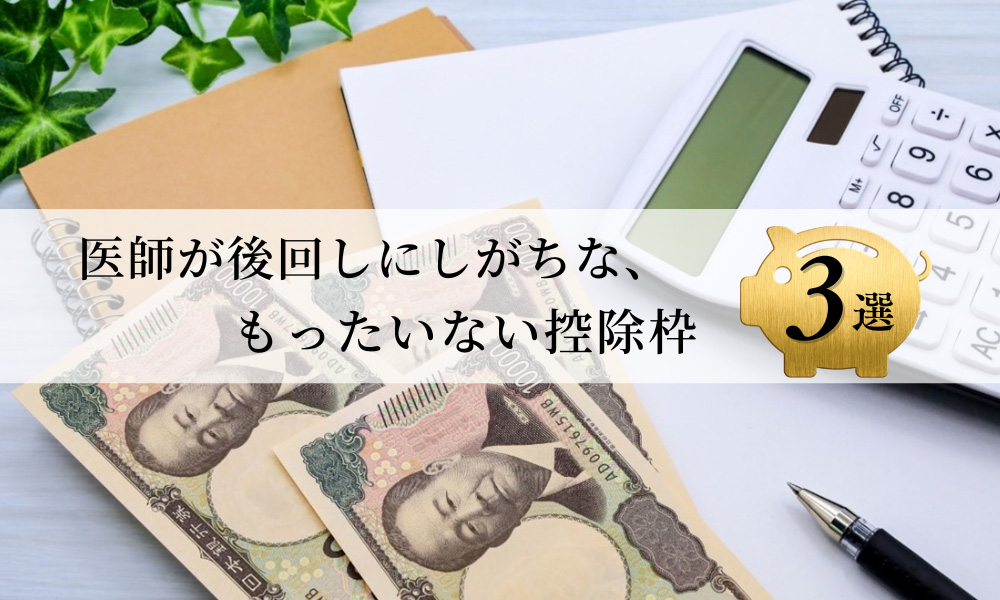
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
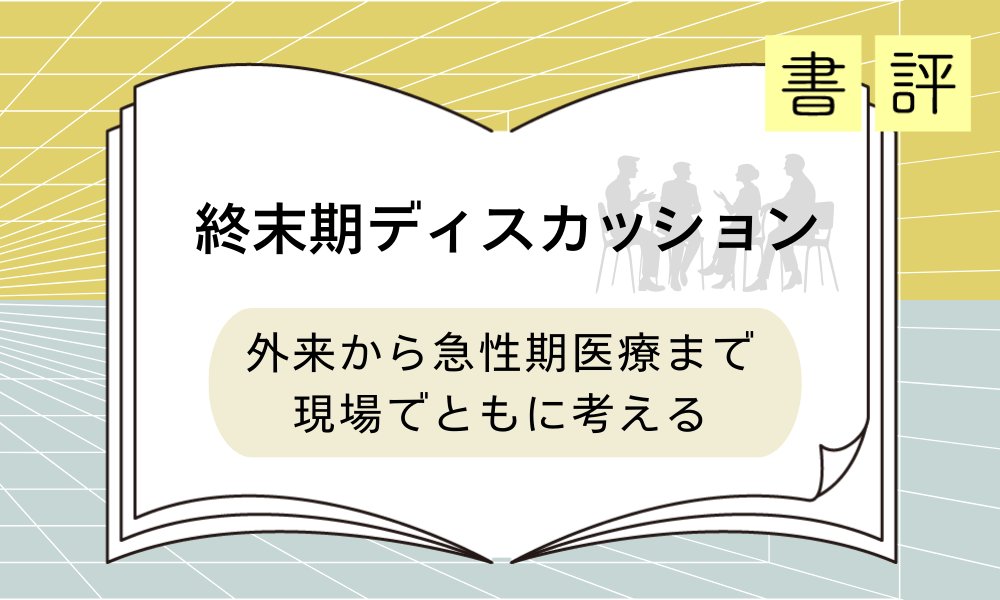
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
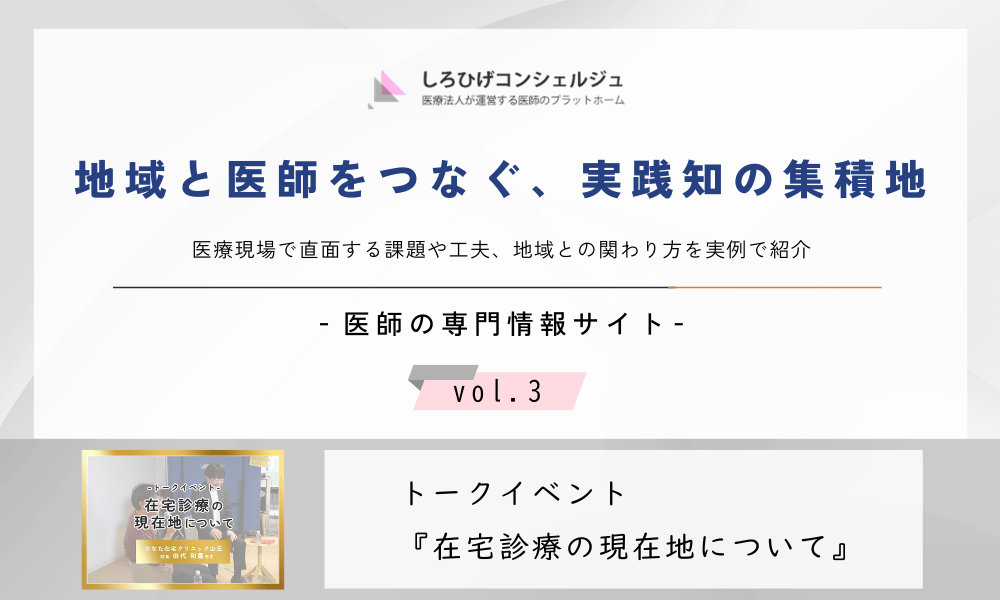
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-
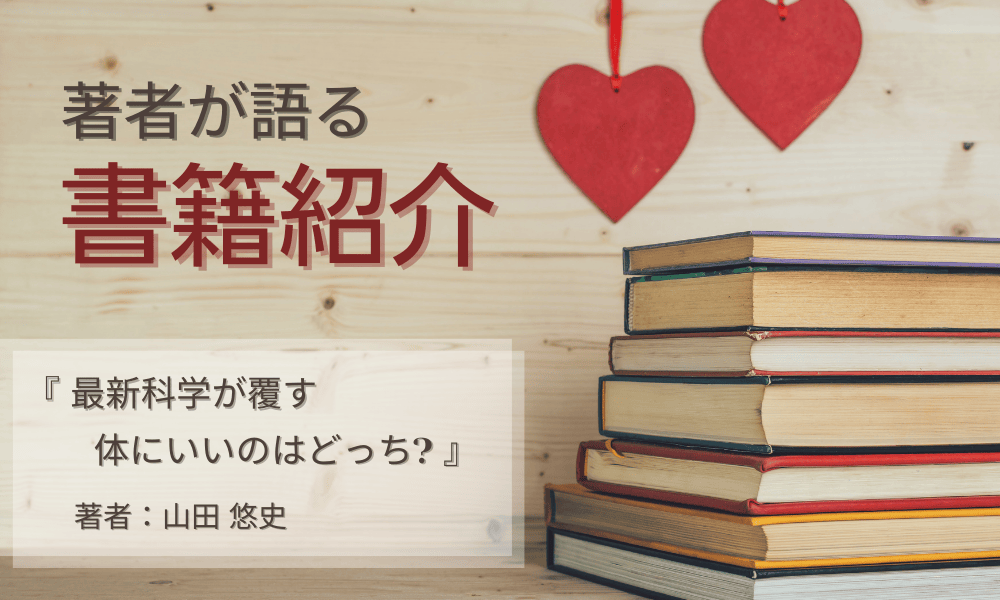
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-
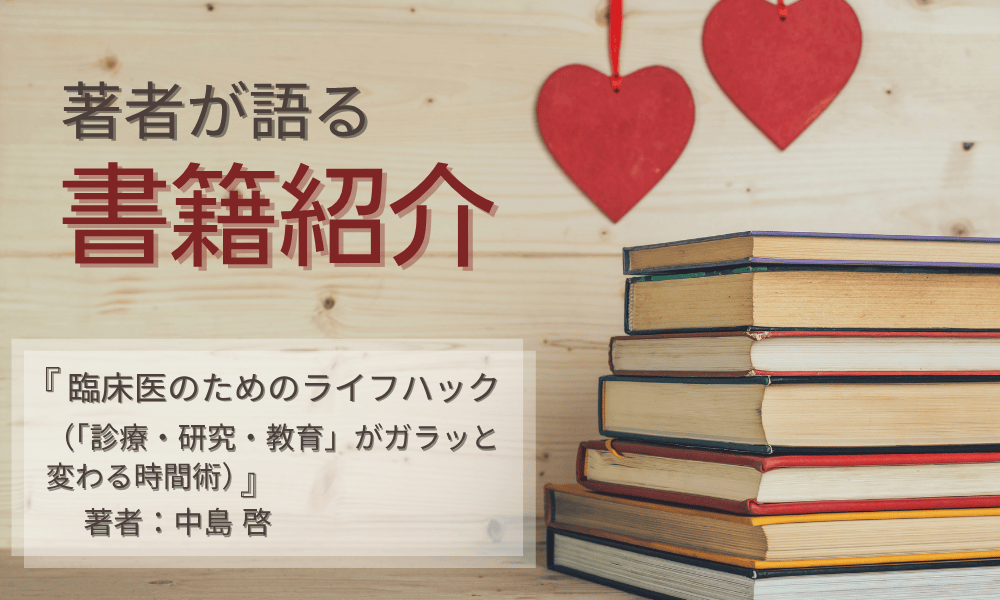
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
