記事・インタビュー
公益社団法人 地域医療振興協会
沖縄地域医療支援センター センター長
崎原 永作

沖縄県へき地医療支援機構の専任担当官を拝命して、今年で14年目になる。自治医科大学の卒業医師として多良間島にたった一人で赴任したのが1984年。その後3ヶ所の離島診療所の常勤医を経験した。最前線の離島診療所の医師としての6年間、離島診療所を支援する県立病院の医師として11年間、そして2002年からは沖縄県へき地医療支援機構の専任担当官として関わってきた。
医師人生の大半を離島医療と向き合って、いつの頃からか、離島医療がライフワークになった。その間、一時も大学の医局に属したことはないし、時々の学会発表を除いて、学会活動に本腰を入れることもなかった。そんな医療界の端っこに住む田舎医者が最近思うことを若干述べてみたい。
日本の医療制度は国民皆保険制度を軸に、先進国の中でも比較的少ない医療費で、新生児・乳児死亡率や平均寿命などの健康指標が世界のトップレベルにあり、世界的に効率の良い医療制度として評判が高い。国民は保険証一枚あれば、安い費用で、大病院でも、診療所でも自由に受診できる(フリーアクセス)。医師も自由に病院を経営し、自由に科を標榜する事が保障されている(自由開業制)。
ところが、この二つのフリーが医療界に暗い影を落としている。診療科が揃っている、診療レベルが高いなどの理由で、多くの国民は本来の機能を考えずに大学病院などの大きな病院を選択している。その結果、高度医療で力を発揮する大病院に風邪や腸炎、腰痛などの日常病が大挙して押し寄せ、先進国の中で最も少ない勤務医を疲弊させている。最悪のケースでは、自分の身を守るために病院を立ち去る勤務医も出ている。
その影響は救急当直に及び、積極的に急患を引き受ける事が困難となり、「患者のたらい回し」が始まる。そして医師側のフリー(自由開業制)も「医師の偏在」や「診療科の偏在」という事態を引き起こしてしまっている。それらが絡みあって、地方の中小の病院に致命傷を与えている。これが「地域医療の崩壊」である。
また、最近耳にする「医療難民」という言葉の裏には大勢の国民が適切な医療を享受できない悲しみが渦巻いている。その悲しみの総和が限界点を超え、「医療不信」へ行き着く。国民の求める医療サービスが提供できない現状で、公共財としての医療は、立ち枯れ状態といえる。
そんなときに飛び込んできた第19番目の専門医としての総合診療専門医の誕生のニュースは一筋の光明が差し込んだように思えた。しかしながら、この新しい専門医が活躍するには、新しい場面設定が必要になる。はまり役は医療界の門番である。一次医療は全て総合診療専門医が担う。それにより、外来の8割を占める日常病は適切に対応され、精密検査や高度な治療が必要な患者は適切な医療機関や専門家へ紹介される。国民は医療のワンストップサービスを手に入れることになる。
もちろん一次医療の全てを総合診療専門医が担うには、日本の医師の一定程度の割合に総合診療専門医が占める事が大前提である。それは五年や十年で実現できるとは思わない。ただ、せっかくのチャンスなので、自分が今いる立場にとらわれることなく、総合診療専門医を中心に医療界の再編に着手し、現在の医療界の影を消し去ることができれば、次の世代によりよいものを残せると思うからである。
総合診療専門医に期待する根拠は、と問われれば、その答えは離島にある。沖縄の離島医療は島の住民も医者を選べず、医師も24時間離島医療から逃れることはできない。この究極の不自由さの中で、沖縄の島医者達は踏ん張っている。それを知っている住民は医師に全幅の信頼を寄せる。
離島医師は島の医療問題全てに関わる。そこには総合診療専門医が将来果たすべき、絶対的な信頼関係の上の豊かな医療が行われている。医療人のエネルギーの源泉(医療の根っこ)が離島には息づいている。できるだけ多くの若い医者が本物の豊かな医療に触れることを願っている。
これが、総合診療専門医に期待する根拠であり、沖縄で離島医療に携わり続ける意義である。
さきはら・えいさく
1981年自治医科大学卒業後、沖縄県立宮古病院附属多良間診療所 、那覇病院附属渡嘉敷診療所、沖縄県立中部病院救命救急センターなどを経て 2004年より地域医療振興協会沖縄地域医療支援センター長。20年以上沖縄の離島医療に携わる。 専門は「いな科」でその延長に「救急室」があるという。
※ドクターズマガジン2016年5月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
崎原 永作
人気記事ランキング
-
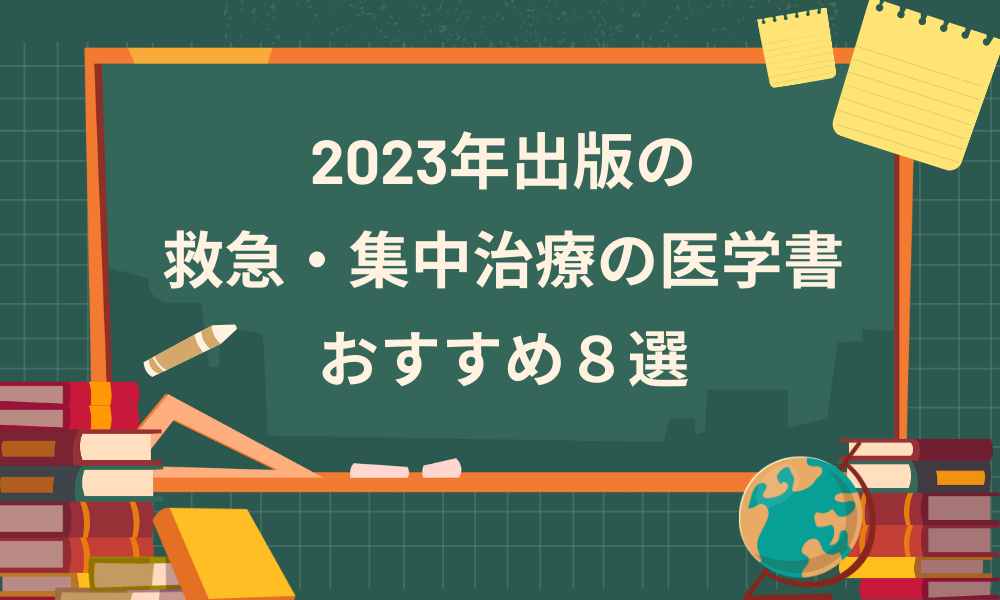
2023年出版の救急・集中治療の医学書おすすめ8選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2023年出版の救急・集中治療の医学書おすすめ8選
三谷 雄己【踊る救急医】
-
会員限定

【民間医局コネクトセミナー】アーカイブ動画(2024年6月)
【民間医局コネクトセミナー】アーカイブ動画(2024年6月)
-
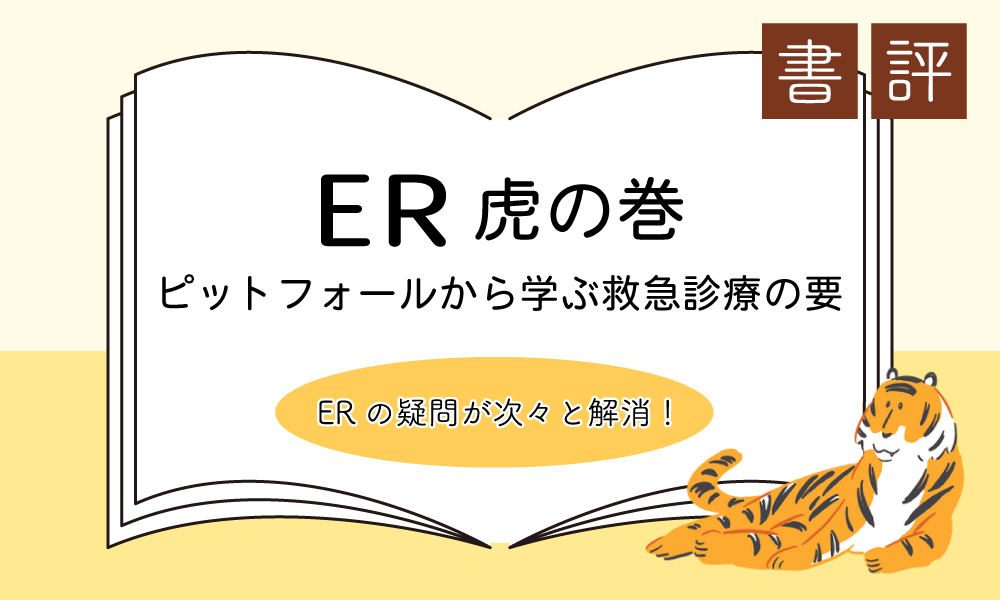
書評『ER虎の巻 ピットフォールから学ぶ救急診療の要』ERの疑問が次々と解消!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『ER虎の巻 ピットフォールから学ぶ救急診療の要』ERの疑問が次々と解消!
三谷 雄己【踊る救急医】
-
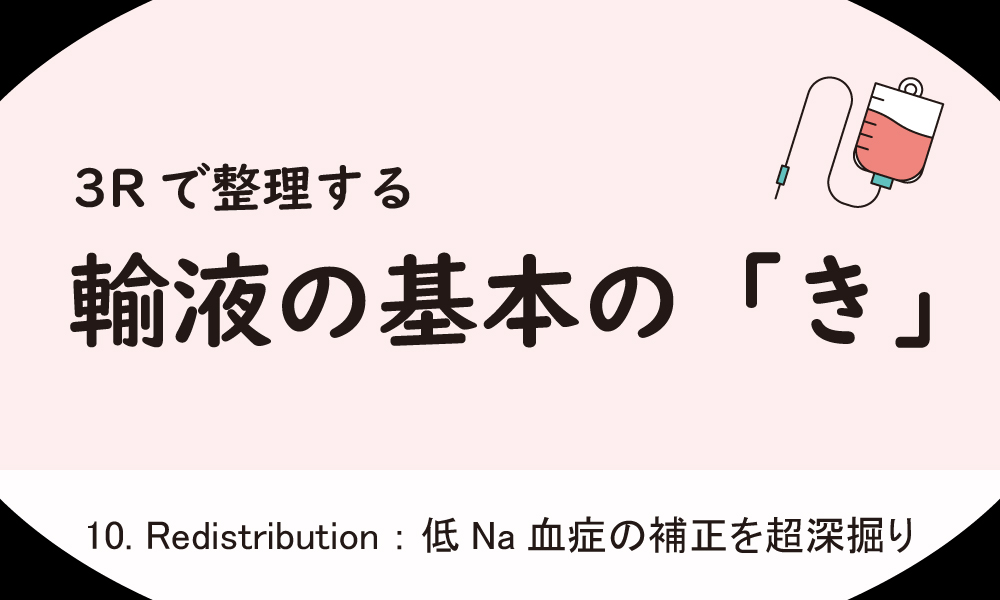
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低Na血症の補正を超深掘り~
- 研修医
- 専攻医・専門医
3Rで整理する 輸液の基本の「き」 ~Redistribution:低Na血症の補正を超深掘り~
柴﨑 俊一
-
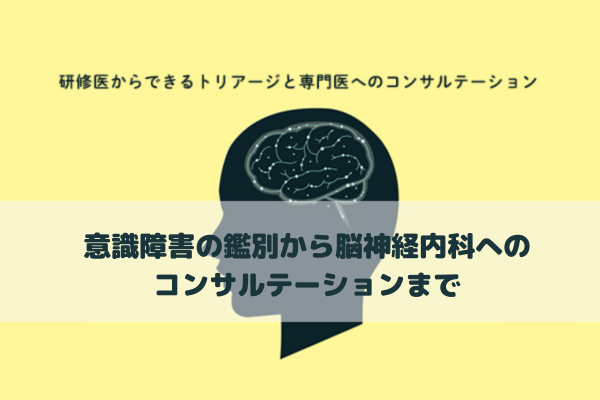
けいれん、てんかん、意識障害―研修医からできるトリアージと専門医へのコンサルテーション―vol.5
- 研修医
- 専攻医・専門医
けいれん、てんかん、意識障害―研修医からできるトリアージと専門医へのコンサルテーション―vol.5
音成 秀一郎
-

水分補給だけでは、脱水症状は改善されない?
- Doctor’s Magazine
水分補給だけでは、脱水症状は改善されない?
髙瀬 義昌
-

海外で医師として働くためのステップ
- ワークスタイル
- 海外留学
海外で医師として働くためのステップ
-

【特集】内科のサブスぺ領域を極めるなら、京都市立病院におこしやす~QOLの高い環境で、理想のキャリアを目指す~
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
【特集】内科のサブスぺ領域を極めるなら、京都市立病院におこしやす~QOLの高い環境で、理想のキャリアを目指す~
羽生 裕太、高木 佑亮、大西 佑弥、吉田 葵
-

医師の離島での働き方 ―その特徴と魅力―
- ワークスタイル
- 就職・転職
医師の離島での働き方 ―その特徴と魅力―
-

医局や慣例にしばられない!江別で自分らしいキャリアを描く
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
医局や慣例にしばられない!江別で自分らしいキャリアを描く
安田 素次
