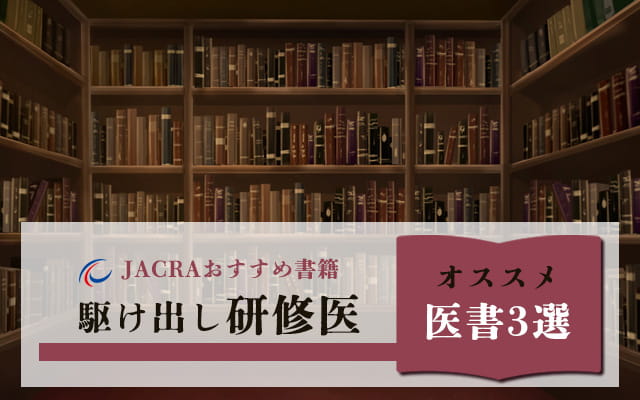記事・インタビュー
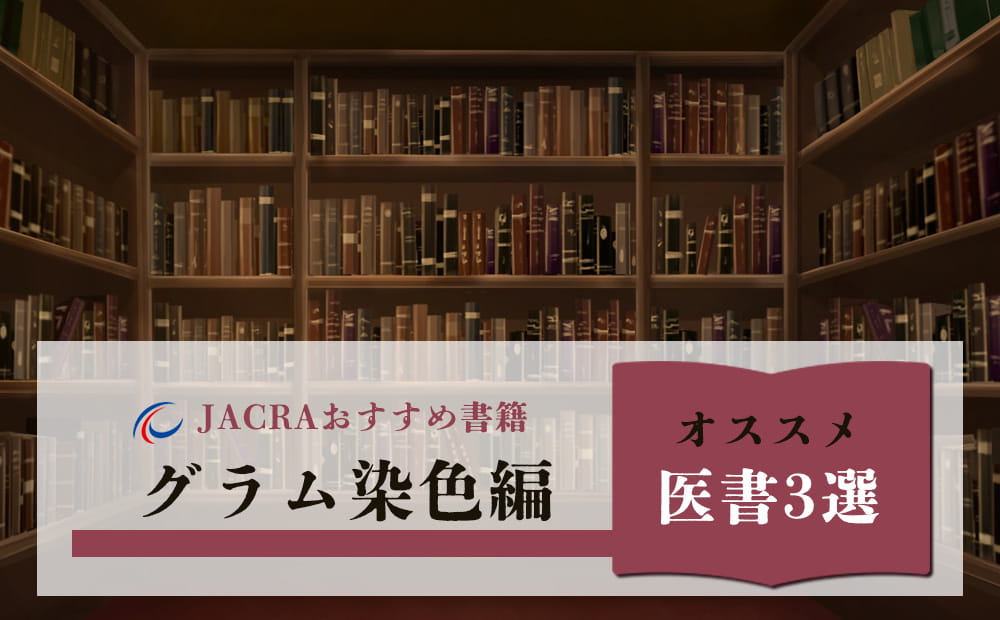
はじめに
グラム染色は救急外来、入院患者、内科・外科領域を問わず感染症診療を行う医師として必須のスキルです。しかしコロナ禍でそれを実践する、学ぶ機会が減ってしまい、自己学習しにくい分野だと思います。グラム染色の原理、形態的な菌の分類、解釈の仕方、得られた情報を実臨床へ活かすポイントなどを初学者の皆様に視覚的にわかりやすいお勧めの3冊を選ばせて頂きました。
- 【JACRAおすすめ書籍】~グラム染色編 オススメ医書3選~
1.第3版 感染症診断に役立つグラム染色―実践 永田邦昭のグラム染色カラーアトラス
2.グラム染色道場2 菌も病気も染め分けろ!
3.感染症ケースファイル―ここまで活かせる グラム染色・血液培養
まとめ
感染症診療において原因微生物を推定することは非常に重要であり、簡便・迅速に行えるグラム染色は微生物の情報を知るために必須のスキルです。しかし、グラム染色に関してはここで紹介したような素晴らしい書籍が多数ありますが、研修医の先生が独学で全てを学ぼうとしても正直難しいと思います。私が研修医の時もそうでした。頑張って座学で菌の名前を丸暗記してその菌の特徴を掴んだつもりでも、学んだ情報を実臨床ですぐに活かせるわけではありません。これから感染症診療の勉強をはじめる研修医の先生方は、微生物や抗菌薬の勉強だけでなく、まずは担当患者、家族からの病歴聴取や丁寧な身体診察を怠らずに何度も繰り返し行い、鑑別疾患を挙げアセスメント・プランを考える内科診療のトレーニングをお勧めします。
担当患者のグラム染色、微生物検査を提出した際には電子カルテ上で結果を確認して終わるのではなく、ぜひ自施設の微生物検査技師とコミュニケーションを取り、自分の眼で顕微鏡を使って標本を見てみること、菌の同定や微生物検査に関してわからないことがあれば教えを乞うこと、迷惑にならない範囲でグラム染色をやらせてもらうことをお勧めします。研修医室で座学で学ぶだけでなく、自ら動いて多職種の方々からたくさん学ぶ姿勢を身につけましょう。良好なコミュニケーションは担当患者のアウトカムの改善に繋がります。
<プロフィール>
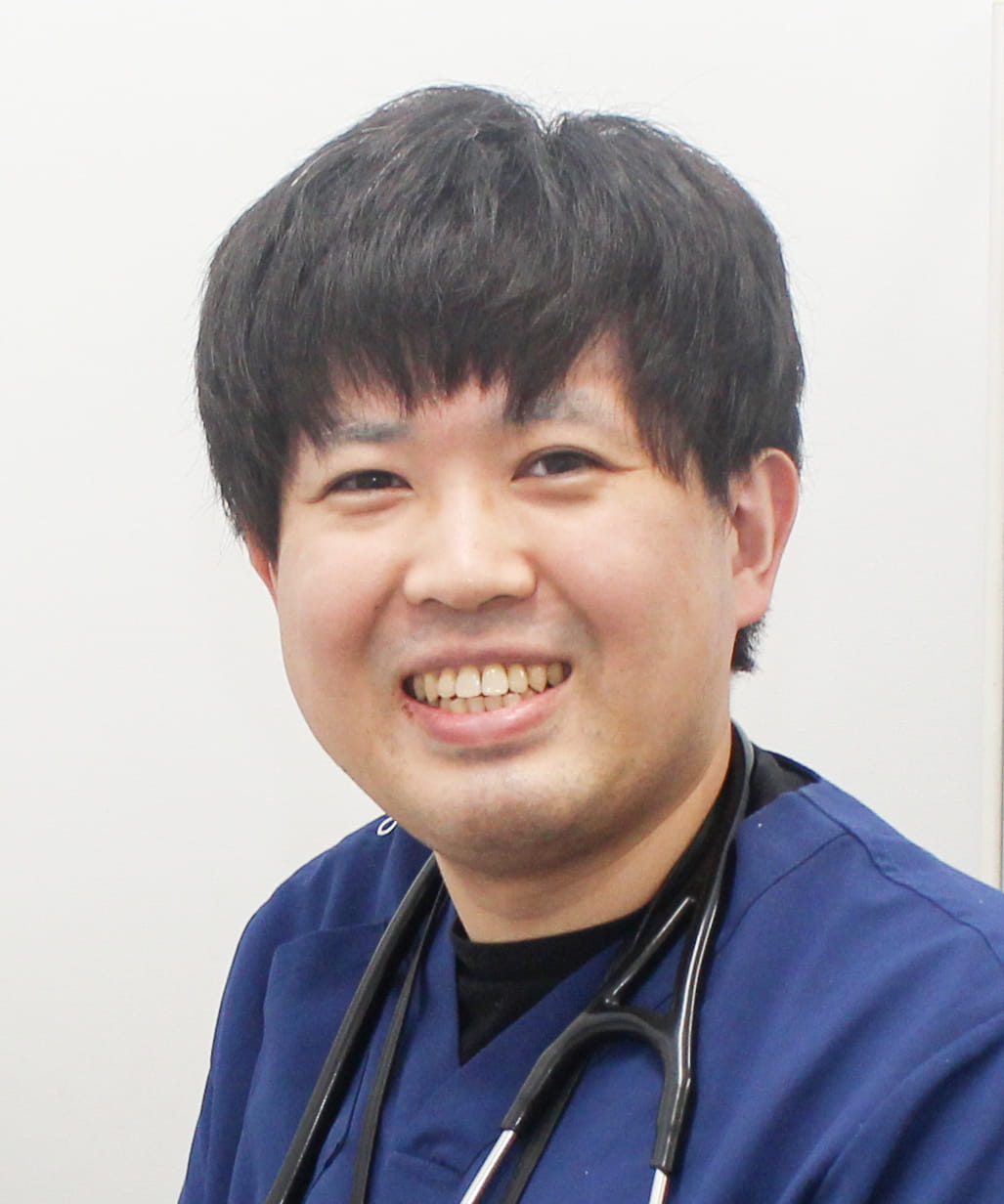
長谷川 雄一(はせがわ・ゆういち)
所属先:株式会社麻生 飯塚病院
専門科目:総合診療科、感染症科
2015年度旭川医科大学卒業。
北海道の砂川市立病院で初期研修、株式会社麻生 飯塚病院 総合診療科後期研修終了。2019年度チーフレジデントを経て、2021年度より株式会社麻生 飯塚病院感染症科所属。日本チーフレジデント協会(JACRA)所属。
長谷川 雄一
人気記事ランキング
-
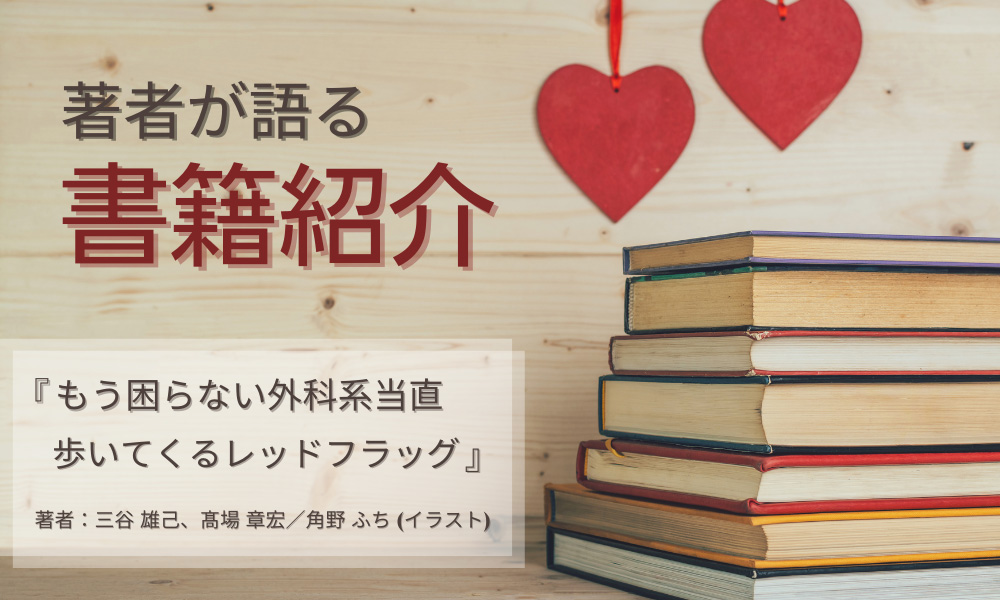
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
三谷 雄己
-
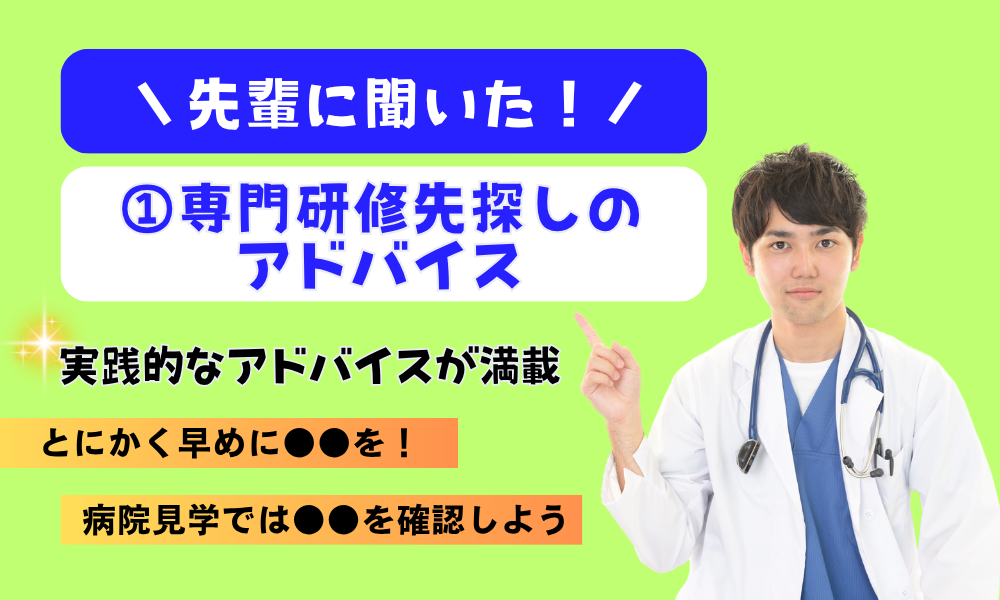
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
-
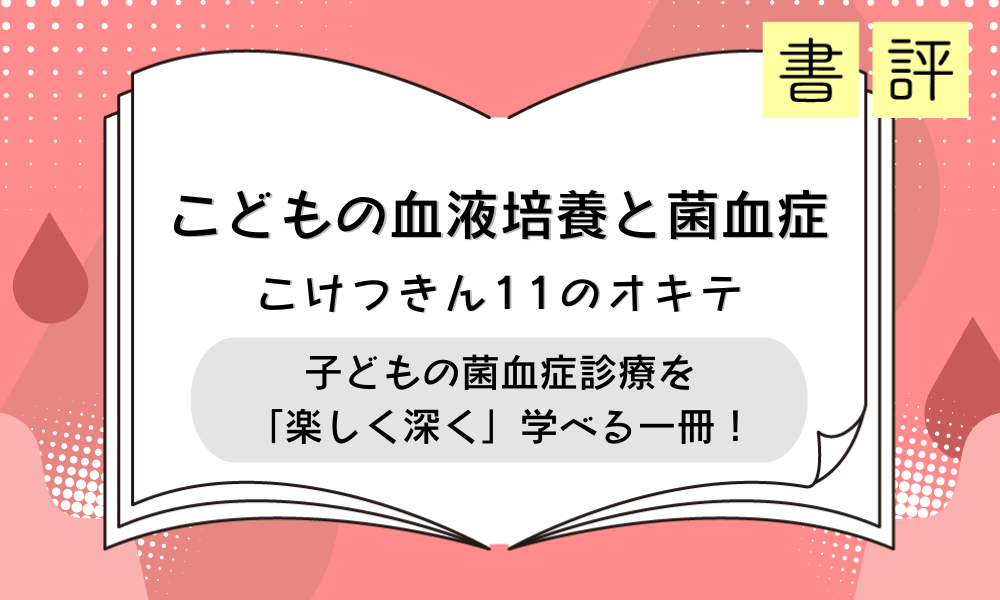
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-
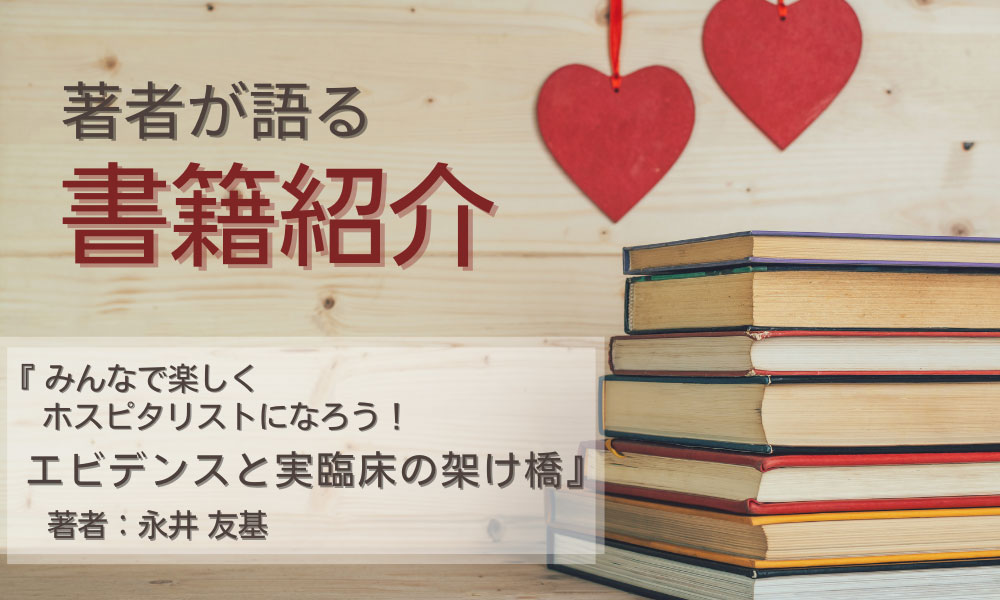
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
永井 友基
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-
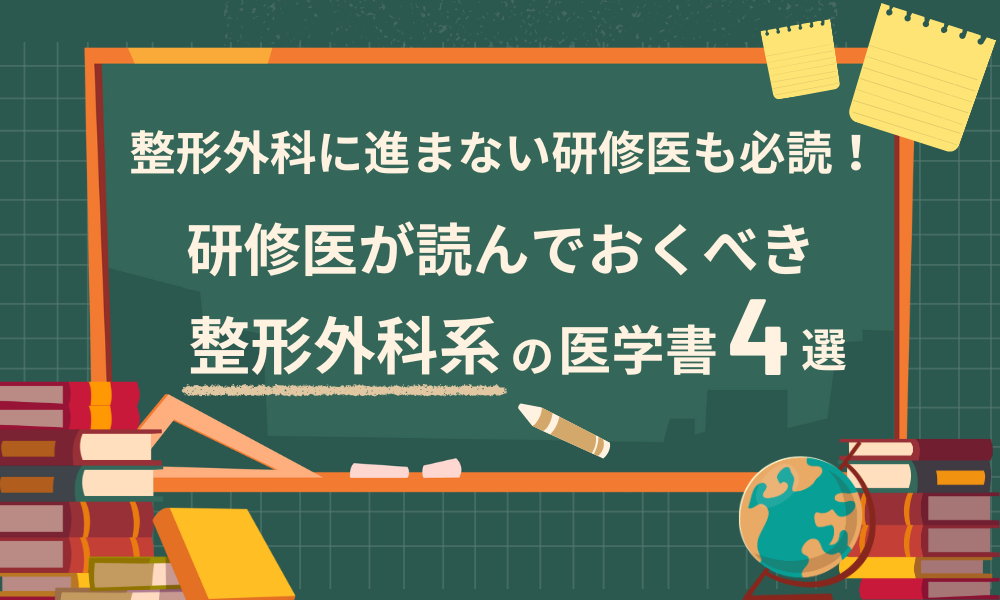
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-
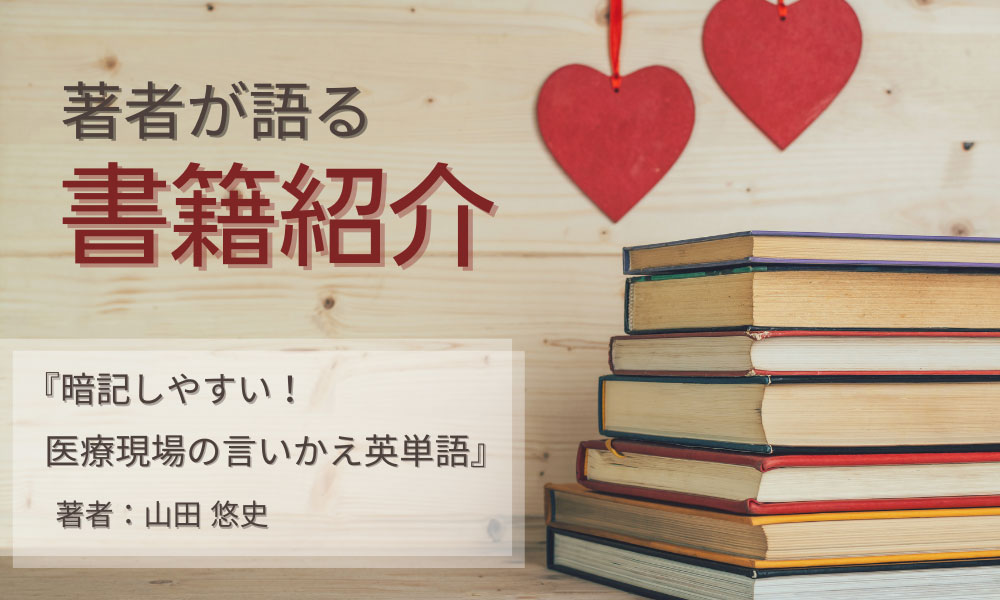
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-
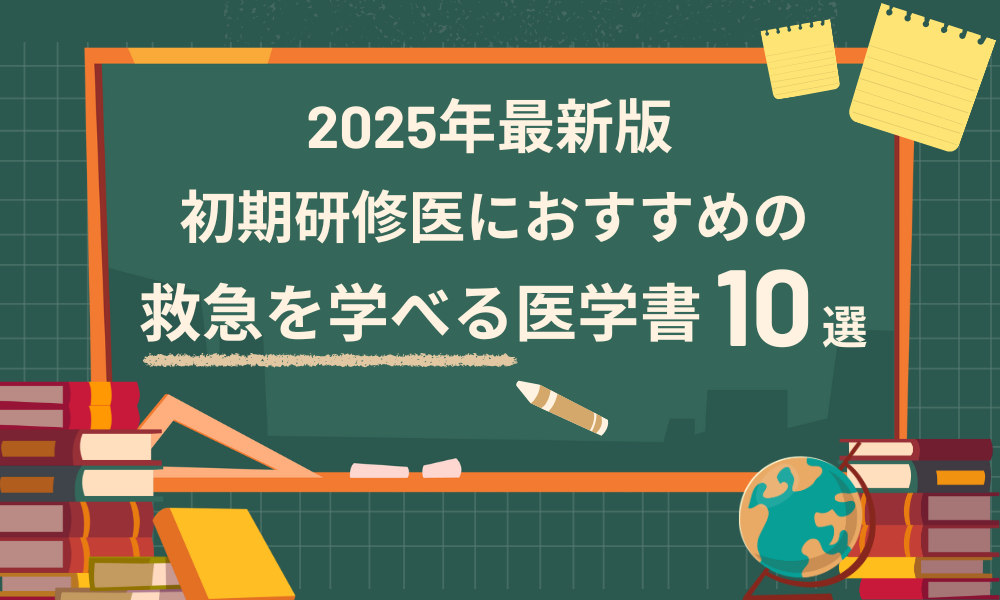
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】