記事・インタビュー
ドイツはノルトライン=ウェストファーレン州にあるボン大学で循環器内科のフェローとして働いている杉浦淳史です。
この記事では、日本生まれ日本育ちの循環器内科13年目がドイツでの研究・臨床留学の中で経験するさまざまな困難・葛藤・喜びを、ありのままにお伝えします。
ボン大からの雇用延長オファー
6月、ドイツはすっかり気候がよくなってきて、街中は人で溢れるようになり、郊外はジョギングを楽しむ人たちが増えています。
なんとここに来て、ボン大学から改めて秋以降の雇用のオファーがありました。それはカテ室専属専門医、4週間のICU勤務、の常勤医スタッフ雇用というものでした。ボン大学で病棟を持たないカテ室専属医師はかつて前例がなく、非常に光栄でしたし、Motivationを掻き立てるものがあったのを感じました。さてどうするか。残留か帰国か。ドイツに残るメリットは、非常に多くの治療経験と最先端の研究を遂行できる点で、日本に帰るメリットはドイツで学んだ事を日本に還元しながらハートチームを発展させ、長期的には大規模臨床試験を元に最新のエビデンスを日本から発信できる可能性が出てくる事、だと思います。デメリットは書きません(笑)。6月現在、ただいま絶賛考え中のままこの文章を書いています。

写真は、三尖弁カテーテル治療の風景
仕事を分担することによる効率化
個人の能力と時間には限界があり、逆にチームワークによって医療の質と速度が向上することを感じています。
臨床現場において、日本では主治医の意見がまあ強いと思いますし、さらに言うと、医者年次の上下関係はとても強いように思います。ボン大学では病棟毎にAssistenzarztが3人程度+Oberarztのチームが担当していて、普段はベルトコンベア的で、型から外れる症例はOberarzt・Leitender Oberarzt・Chef、という順でコンサルトするので、質と速度が担保されています。病棟の患者治療だけでなく、カテーテル治療も同様です。 通常の症例は僕らFellowやOberarztが治療しますが、常にLeitender OberarztやChefがBack upしていて、困難症例や合併症時にはすぐにコンサルトする仕組みになっています。彼らの経験値はかなり圧倒的で、よく聞く「欧米人は手技が上手くない」というのはある面で事実と思いますが、「Topの人達の技術は飛び抜けている」というのも事実です。この辺は、ドイツの症例集約化も大きく貢献していると思います。いずれにせよ、チーム医療・仕事の分担とコンサルティングの普及によって、現場の効率化と質の向上を行なっています。
研究についても同様の事が当てはまると思います。例えばある一臨床研究プロジェクトを考えてみると、研究テーマ立案、患者説明、データ集め、統計解析、論文作成、英文校正、論文投稿、Revisionおよび追加解析、といった形で非常に多くの仕事内容があり、どれも時間のかかる作業です。こういったものを最初から一人で行うのは非常に大変ですし、経験が少ない場合余計に時間がかかる反面、質を伴っていないことが多いと思います(自分はそうでした)。自分が頑張れば研究は進み、自分が休めば研究は止まる。ただでさえ雑務の多い日本の臨床医が、臨床研究を遂行するのは、非常にハードルが高いことがわかります。
今僕らのチームが行なっている方法は、研究テーマに関して最初に複数人で議論しプランを立て、研究の患者説明やデータ集めなどを学生・Assistenzarzt・Fellowがチームで行い、研究の責任医師が適宜状況確認や方向修正などを行ない、解析結果に対して議論して、さらに方向修正を行なっていく形です。仕事を分担して個人の負担を軽減すると共に、常に研究を進行させ、そして議論によって内容を充実させていく方法です。こうすることで、複数の研究を並列して行うことも可能ですし、研究の質自体が上がってきます。「そんなの日本でも同じ」という声が聞こえてきそうですが、こちらでは速度とスケールが違います。例えば治療デバイス絡みの研究案や解析結果に関しては、日単位で世界的な研究者のところにコンサルトがまわりFEEDBACKが帰ってきたりします。
ボン大学ハートチーム
ボン大学はカテ室4部屋とハイブリッドOPE室1部屋で普段のカテーテル治療を行なっています。年間の治療件数はPCI約2000件、弁膜症カテーテル治療700件、その他の構造的カテーテル治療150件程度です。循環器内科医、心臓外科医、看護師、麻酔科医、などが主なチーム構成ですが、今のチームは控えめに言ってとても良い感じです。お互いに常にコミュニケーションを取りながら、阿吽の呼吸のところもありつつ、責任の所在としてのヒエラルキーはしっかりしています。職種間あるいは医師間でのコミュニケーションの垣根がとても低いので、なにかうまく行かなかった時にはみんながオープンに話あって、改善点を見つけていきます。あとは、欧米文化ゆえだと思いますが、まずは良い点、共感できる点、同意できる点を言って、基本的には褒めます、笑。そしてそのリアクションは大きめ。そのうえで、「こういう方法もできたかもね。」とか「僕だったらこうするね。」とか言ってみたりしますが、それで気分を害する人は絶対にいません。

写真はProf. Zimmerの誕生日パーティー。みんなでシャンパン飲んで、また治療へ。
<プロフィール>

杉浦 淳史(すぎうら・あつし)
ボン大学病院
循環器内科 指導上級医(Oberarzt)
論文が書けるインテリ系でもないのに「ビッグになるなら留学だ!」と、2018年4月からドイツのボン大学にリサーチフェローとして飛び込んだ、既婚3児の父。
杉浦 淳史
人気記事ランキング
-
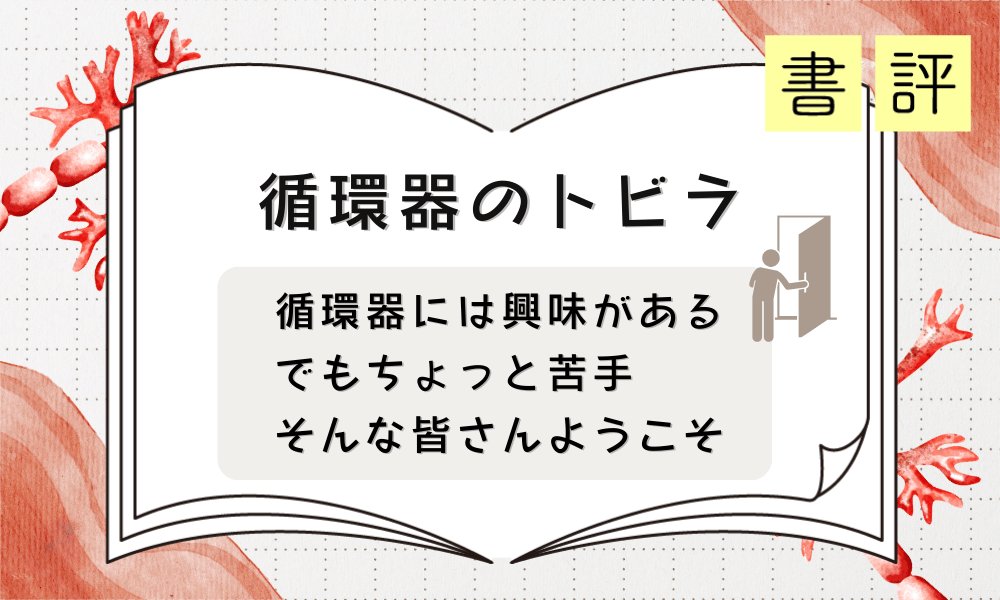
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-
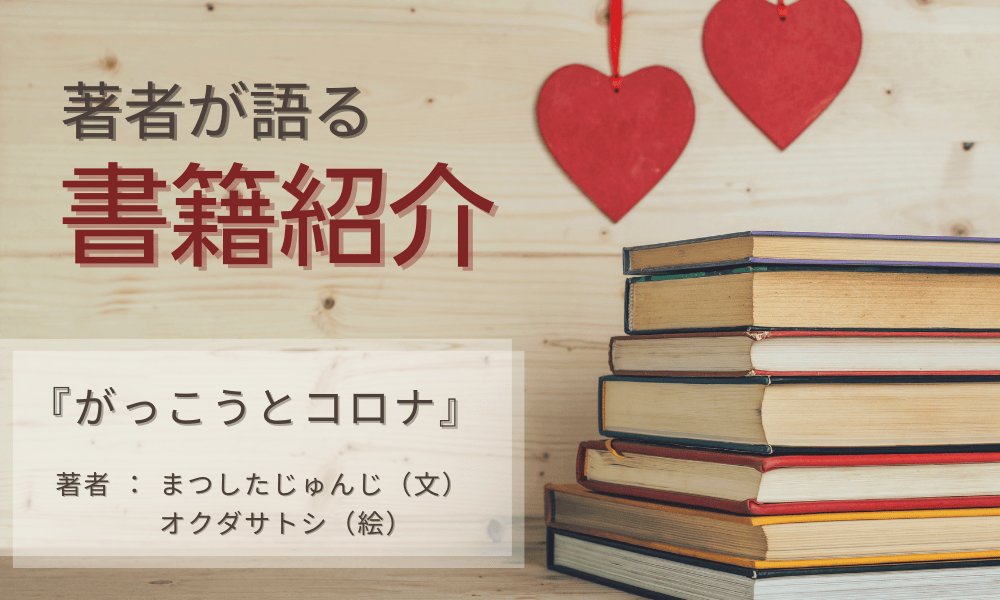
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-
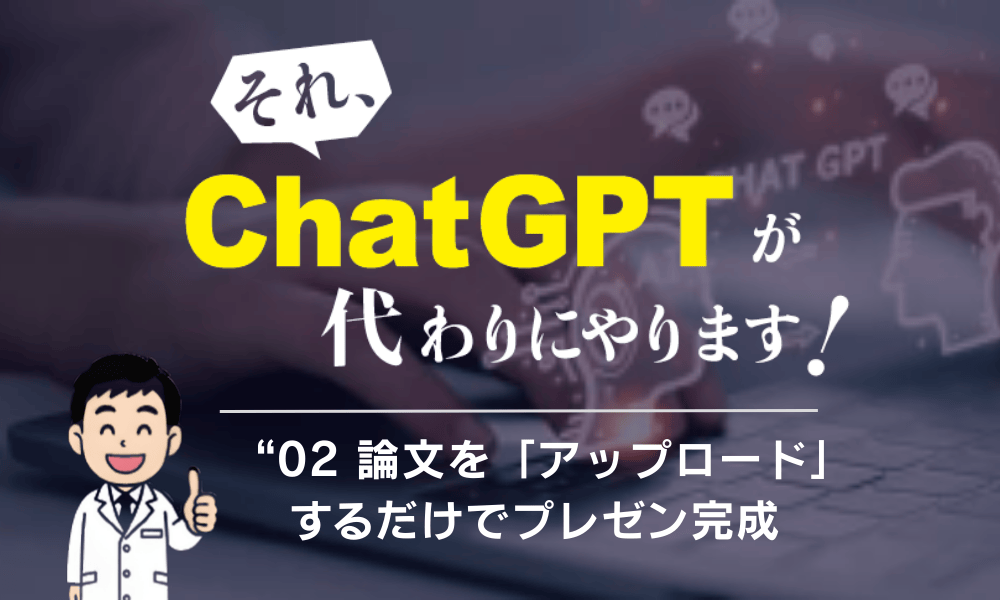
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-
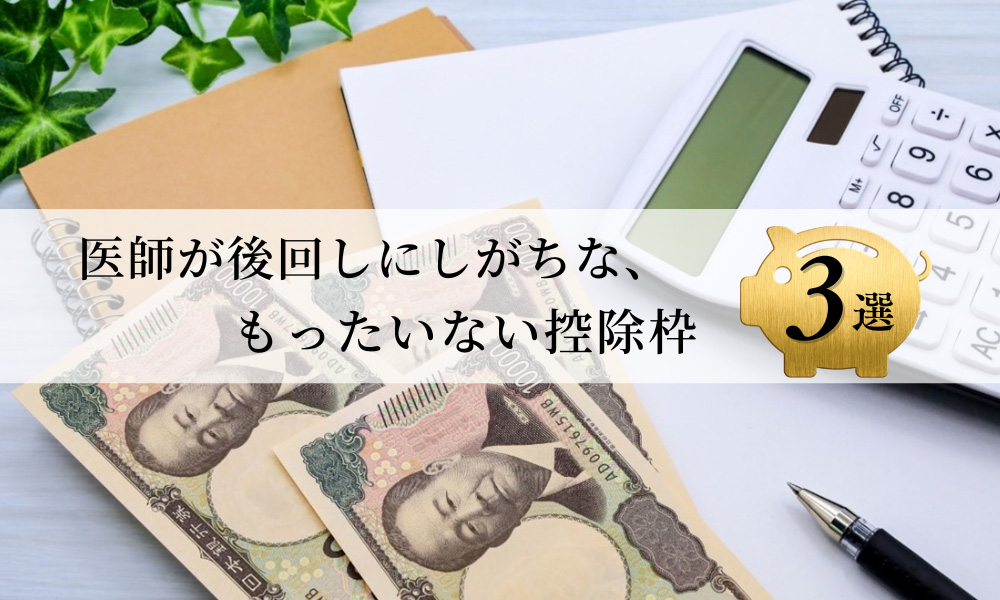
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
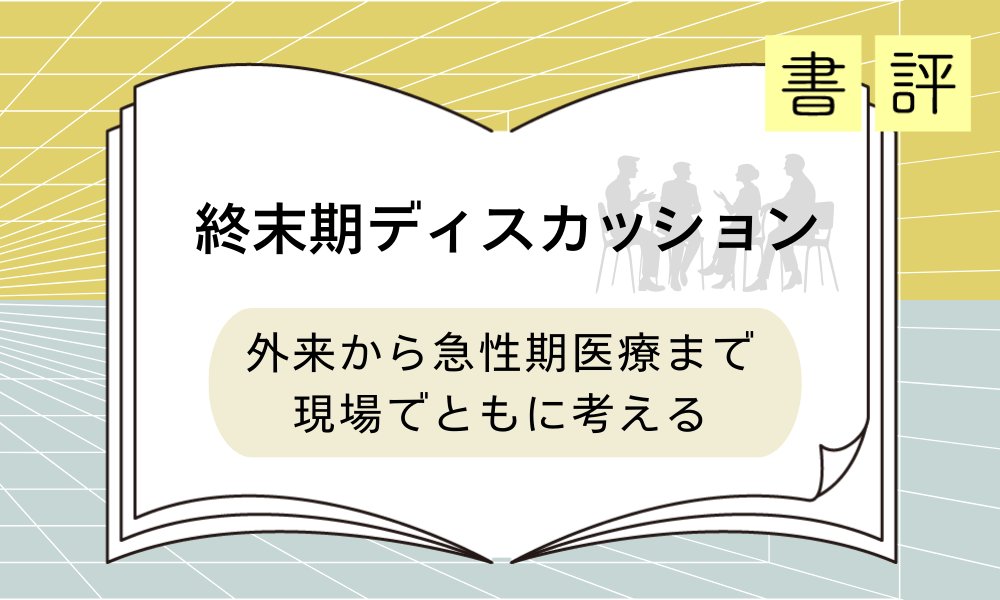
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
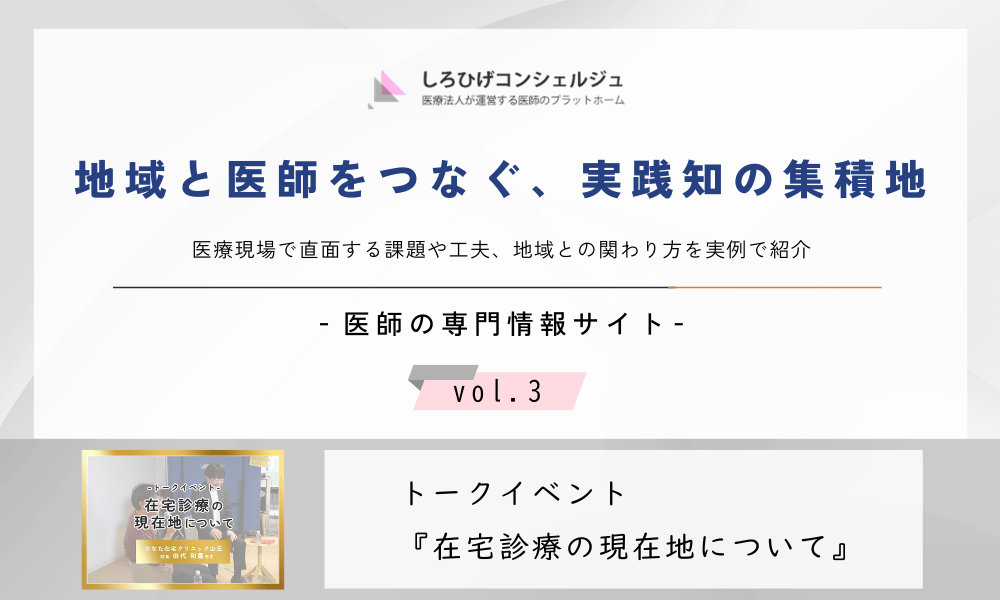
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-
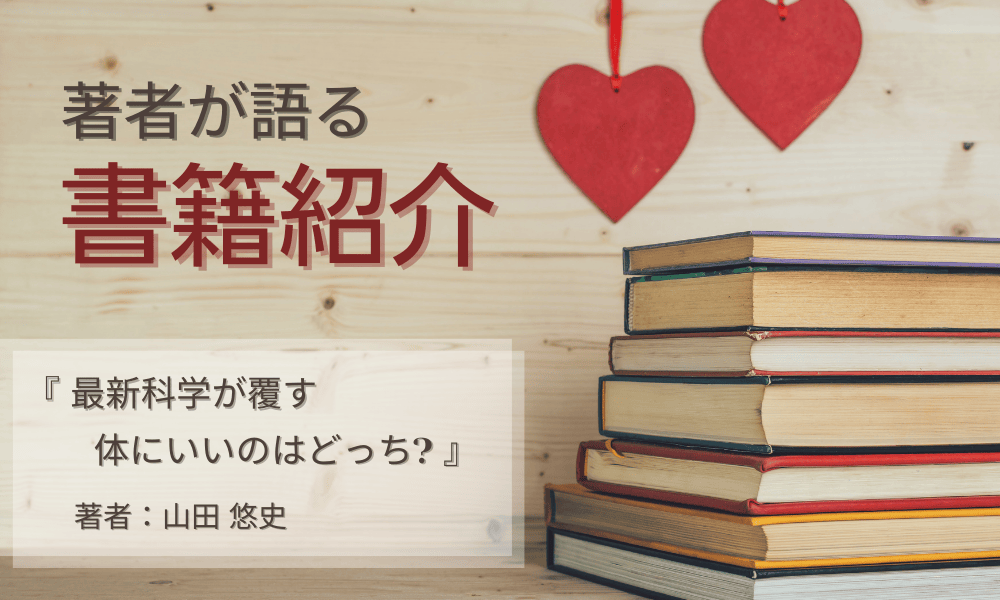
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-
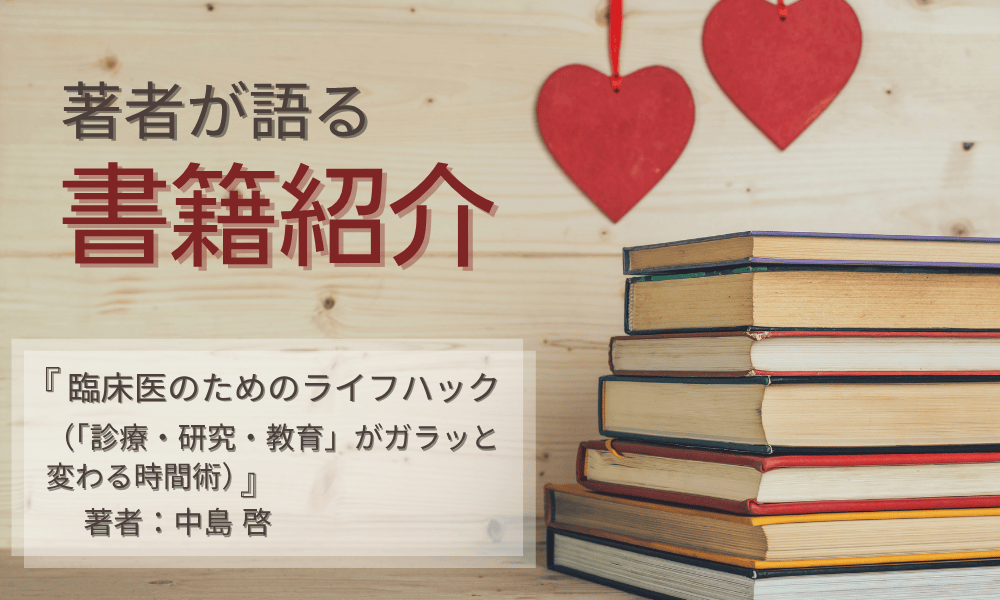
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓

