記事・インタビュー
日本赤十字社 和歌山医療センター
外傷救急部/外科/精神科/国際医療救援登録要員
益田 充
「先生、面白い仕事してますね」
国際医療救援活動から帰国して報告会などをすると、必ずと言っていいほど頂く賛辞なのであるが、最近これが単なる「社交辞令」でなく、「本当に」ニーズのあることなのではないかと思い始め、機会もあり、ここに筆を執らせていただいた。
私は現在、日本赤十字社の傘下の病院の医師として、普段は地域住民の健康のために診療活動をしながら、災害や紛争・難民の発生時などには海を越えて支援に行く、という生活をしている。昨年はバングラデシュ南部避難民(いわゆる「ロヒンギャ」難民)支援に参加し、仮設診療所にて1日100人程度の患者さんの診療を、7週間程度続けた。
また、今年は中東レバノンに4ヶ月派遣され、国内のパレスチナ難民キャンプの2病院にて、エコーや外傷診療の技術指導や、多数傷病者受け入れ対応の支援などを行った。同じ難民キャンプでも前者は2年目で後者は70年目、また同じ医療支援でも前者は直接診療で後者は診療技術の教育など、それぞれの活動に背景や内容の差はあるものの、「医者を必要とする地域に駆け付けて汗を流す」という基本は共通している。
私としては、もともとこのように「世界中で一番困っている人々に、直接手を差し伸べられるスキルが欲しい」と法学部から転身して医師になったので、今の仕事が面白いのは当たり前なのだが、そのような奇特な経歴を持たないであろう他の方々にも「面白い」と思われる背景には、きっと日本だけで医療をしていては見えてこないものがあるからかもしれない。それは何かと問われたら、例えば(半分近くが20歳以下の子どもであった)バングラデシュ支援においては、一人の若者を治療することで彼の未来が開けるだけでなく、「この国そのものが活性化する」感覚があり、それは帰国後に高齢化が進む地方都市で勤務を再開して、とても強く感じた。
また、新聞の活字では紛争の欄にしか出てこない「パレスチナ難民」と呼ばれる方々と、医師―患者関係だけでなく同じ医療スタッフ同士として交流し続けたことで、目の前の友人たちが背負ってきた歴史や、あえて置いてきた「わだかまり」などを実感し、そこから自分が何を持っていて何を捨てているのかを相対的に理解することとなった。このように、ただ医師として働いているだけなのに、そこから社会や世界とのつながりを感じたり、逆に自分は何者かを問い直したり、そのような契機に満ちあふれていることも、国際救援医という生き方の魅力なのかもしれない。
そうすると若い皆さんより(時折若くない方々からも)、「どうしたらそういうフィールドに入れるのか?」との質問を受けることになる。詳細は最寄りの赤十字病院にお問い合わせいただきたいが、要約するとまずは「派遣地で生きていけること」「派遣地で医師として働けること」「赤十字チームの一員として働けること」、これらを満たすための準備をしていくことになる。
特に医療スキルでいうと、例えば外科系では「何でも切れること」であり、腹部の緊急手術はもちろん、四肢切断や植皮・皮弁、そして途上国に必須なのが帝王切開の手技である。これらを習得するために国内で外科・救急・整形・形成・産科などを数年かけて回ることになるが、この一見新専門医制度と逆行するような研修システムも、少なくとも院内連携の上で貴重な人材となり得るし、災害時にはそのネットワークは特に有用だろう。
その他、最低限度の英語力と異文化理解力はもちろん必要になるが、それらは国内にいてもある程度遭遇する外国人患者さんの対応を通して学ぶことができる。また、人質対応などの危機管理能力は、(今まで派遣先で一人の死者も出していない)日本赤十字社自慢の研修体系から学べるので心配はない。
そうだとすれば、もしこの記事があなたの目に留まったとしたら、何をはばかることがあろうか? 私にとって「面白い」とは「世界中で一番自分が必要とされ、必要とする場所にいること」であるが、あなたにとっての「面白い」の定義を、ぜひご自分の目と足でつかんでみてはいかがだろうか?
ますだ・みつる
東京大学法学部や国際人権NGOにて難民支援活動をする中で、「紛争に苦しむ人を自分の手で救いたい」と神戸大学医学部に再入学。医学生や初期・後期研修医時代から、アジア・アフリカを含む国内外の医療機関で活動し、現職に至る。
※ドクターズマガジン2019年12月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
益田 充
人気記事ランキング
-
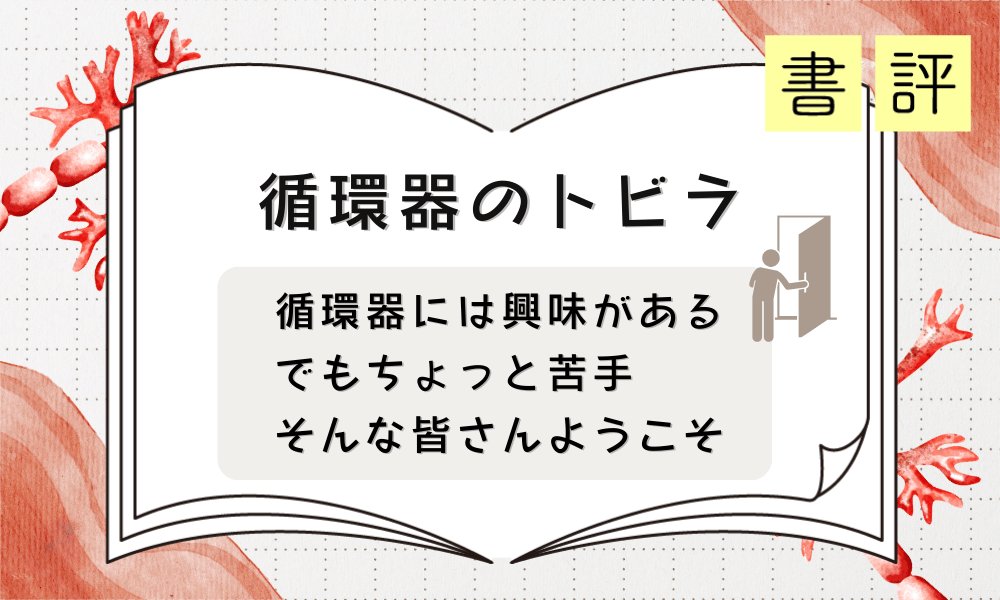
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
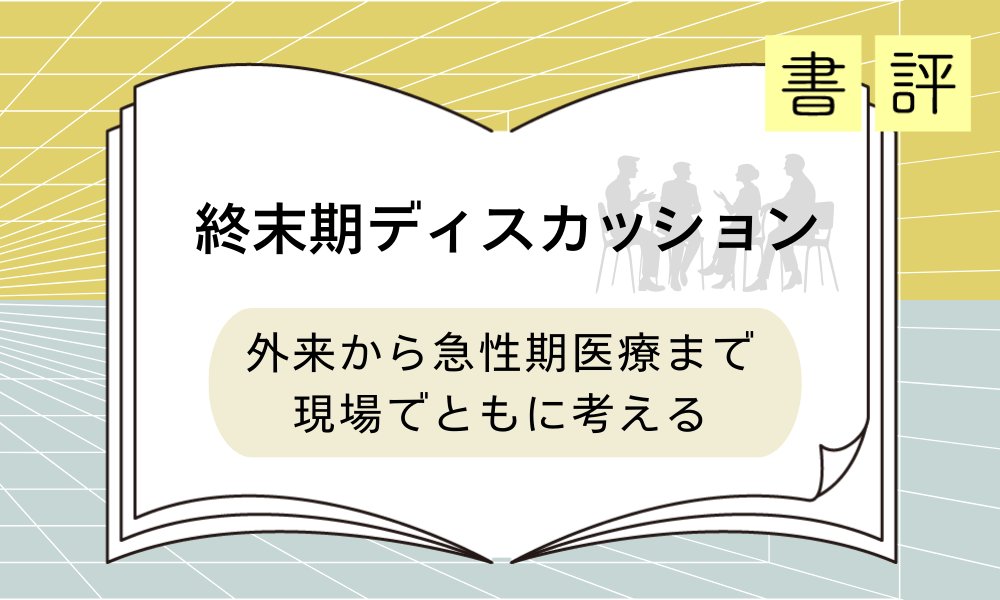
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
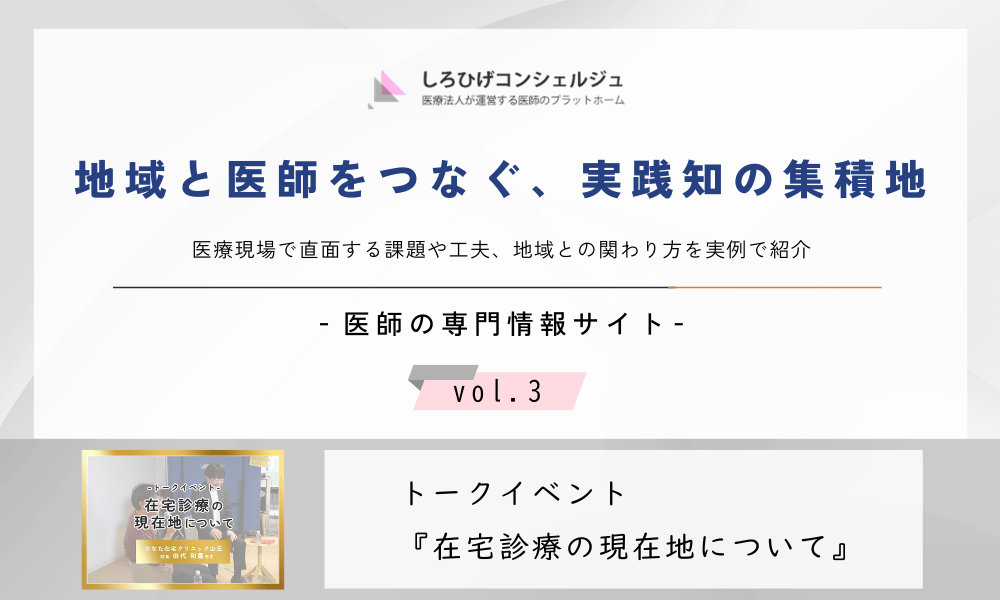
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
