記事・インタビュー
がん・感染症センター 都立駒込病院
外科部長(肝胆膵外科)
本田 五郎
今日の腹腔鏡下肝切除症例もなかなか手ごわい…その瞬間、右肝静脈の付け根に孔が開いて…手術前に手を洗いながらネガティブ思考が頭の中をよぎる。外科医になって四半世紀が過ぎた今でも時々このネガティブ思考はやってくる。このネガティブ思考への向き合い方は、おそらくアスリートのそれと似ている。まずは妥協なきトレーニング、そしてあらゆる可能性を想定した万全のシミュレーション。「こういう時はこうする」、頭の中にはトーナメント表のようなアルゴリズムが完成している。これらによってネガティブ思考を押し返し、平常心を取り戻す。そして「俺よりうまくできる外科医は他にはいない」と本気で思う。君はそう思えるか? だってプロだろう?
私が肝切除術を一人で任されたのは京都大学の外科を辞めて熊本に帰った年、卒後7年目だった。それまでに京都大学で山岡義生教授(当時)の肝切除術に30例くらい参加させてもらったが、術者の経験など一度もなかった。ビッグチャンスは突然訪れた。それは大ピンチでもあったのだが。その日の朝、外傷後の胆管狭窄が原因で肝右葉に繰り返し膿瘍を形成する患者に対して肝右葉切除術が始まった。第2助手の私の役目は術野展開と吸引だった。炎症による線維化も相まって手術はなかなか先に進まず、良性疾患だから何とかなるだろうという甘い空気は徐々に凍り始めた。上司がギブアップした。「お前できるか?」、「たぶんできると思います」。倫理的に問題になりそうな会話だが、何とか収拾がついて患者は無事に退院した。その後、肝臓内科医からじかに肝切除術の依頼が来るようになった。それまでは手術適応のある患者を福岡の大学病院に送っていたらしい。さすがにしばらくの間、人生は〝運〞次第で何とかなるものだと勘違いした。
大学時代にさかのぼる。6年の秋にポリクリが終了して卒試期間に入ると、サッカー部の先輩が麻酔科部長を務めていた医師会病院に毎日せっせと通い詰めた。外科の患者に麻酔を導入した後、番犬のように麻酔の維持管理をしながら手術を特等席から見学した。「そぎゃん手術が好きとね。んなら、この血管の名前知っとるね?」、「coronary vein です」。解剖の勉強は好きだったので結構答えられた。「よー知っとるねー、卒業したら2外科に入りなっせ」。そんなことよりも手術のやり方に興味があった。同じ胃の手術でも外科医によってやり方が違う。どこが違うのか…「なるほど」。卒後6年目、京都大学で山岡教授の肝切除の助手をしていた1年間もそんな目で手術を見ていた。ただし学生の時とは少々違った。「俺ならこうするのに」。もちろん山岡教授は肝切除術の達人であり、当時一度も自分で肝臓を切ったことのなかった私の考えは、多くが浅知恵にすぎなかった。しかし、明日は自分がやってやると思いながら見ていると、そういう分不相応なことまで考えてしまうものだ。
最近、大学病院の指導医からよく聞く嘆きの言葉、「とりあえず手術をやらせないと若い人が集まらないからね」。しかし、実際の患者で手術を一から手取り足取り教えることには違和感を覚える。
手術は人の命を預かる仕事であり、〝そこ(術者の立ち位置)に立つ資格〞というものがあってしかるべきだ。資格といえば、外科系専門医の多くは術者の位置に立って手術を一から手取り足取り教えてもらってその資格を取得している。要は資格ではなく自覚の問題であり、〝そこに立つ資格〞とは自覚を持って最大限の準備をすることで得られるものということか。
トップアスリートを育てるように外科医を育てたい。トップアスリートにとっての〝最大限の準備〞は、試合に向けた妥協なきトレーニングだけではない。試合環境や対戦相手の徹底した分析とそれに基づくシミュレーションがもう一つの重要な要素だ。そして、連勝するためにこれら〝最大限の準備〞を怠ることなく繰り返し、〝運〞に委ねる割合をできる限り少なくする。それがプロとして〝繰り返しそこに立つための資格〞だ。
「相変わらずブラックやねー」、「外科医の仕事がブラックで何の悪かとね」。
本田 五郎 ほんだ・ごろう
1992年熊本大学卒業。京都大学外科教室入局。市立宇和島病院、京都大学医学部附属病院、済生会熊本病院、小倉記念病院を経て、2006年より都立駒込病院に。2018年10月より誠馨会新東京病院に消化器病センター外科部長として異動予定。小学生よりサッカーを始め、熊本高校、熊本大学時代に熊本県代表として国体に出場。
※ドクターズマガジン2018年9月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
本田 五郎
人気記事ランキング
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-

書評『臨床推論の落とし穴 ミミッカーを探せ!』~“ミミッカー”の視点で臨床推論を深める一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『臨床推論の落とし穴 ミミッカーを探せ!』~“ミミッカー”の視点で臨床推論を深める一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-
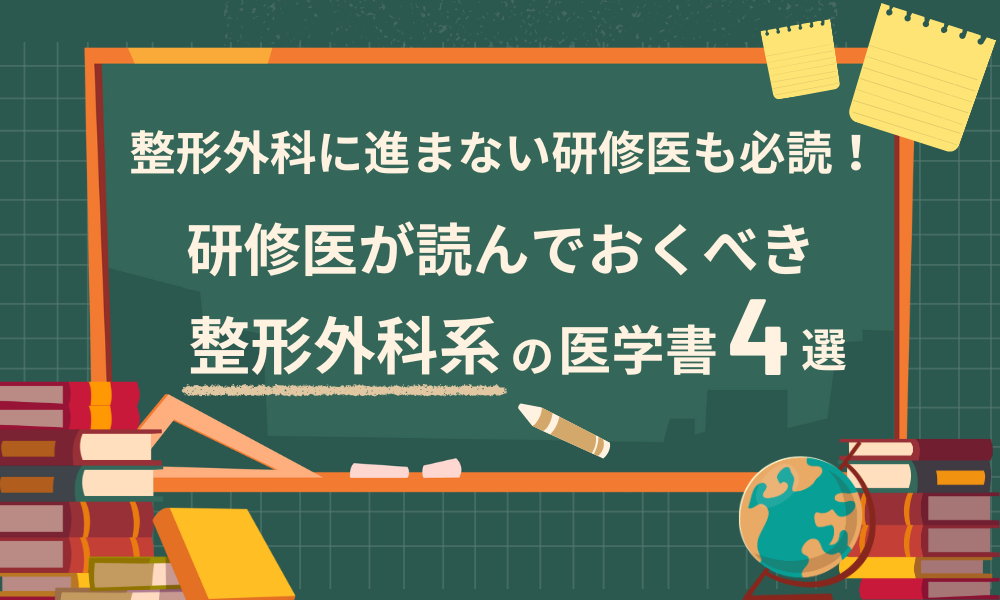
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-
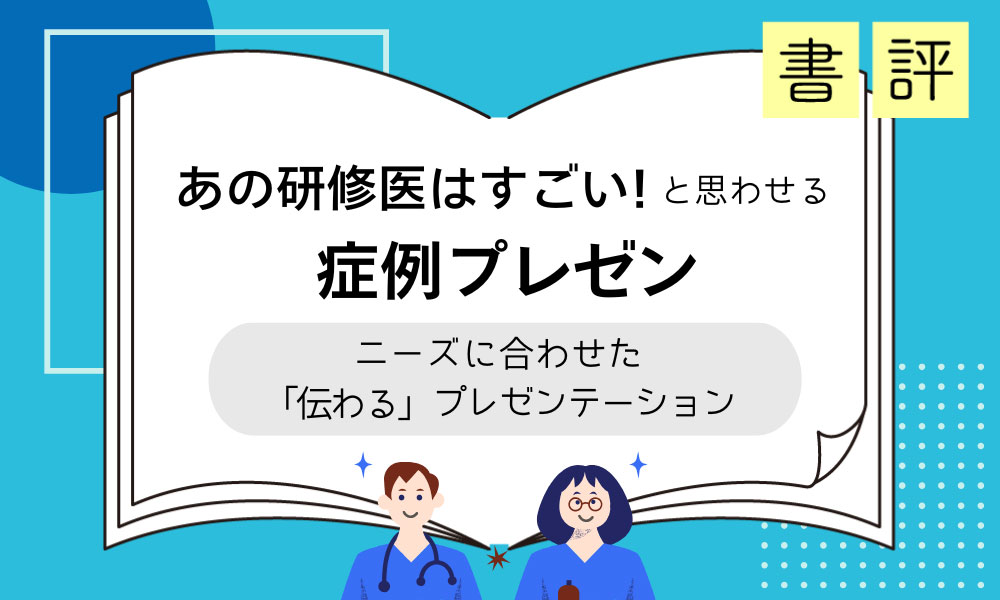
書評『あの研修医はすごい! と思わせる 症例プレゼン〜ニーズに合わせた「伝わる」プレゼンテーション』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『あの研修医はすごい! と思わせる 症例プレゼン〜ニーズに合わせた「伝わる」プレゼンテーション』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-

著者が語る☆書籍紹介 『胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教えます!改訂版』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教えます!改訂版』
中島 啓
-

2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
