記事・インタビュー
焼津市立病院 病院事業管理者
太田 信隆
本年4月26日に開催された厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会」で6年後の2022年には医学部定員の増加、人口の減少などにより医師の需要と供給がマクロ的に均衡する、その一方で診療科・地域における医師の偏在は改善されておらず今後の見通しのつかないことが報告されています。
専門医制度を利用して診療科の定数制限をするという議論は紛糾しており、勤務地域制限への強硬な反対もあり今後も難航が予想されます。
さて、私が勤務する地域では公立、私立を問わず病院の医師が不足しています。かつてあった診療科が閉鎖され、病院が規模縮小に追い込まれ、選択と集中はいやが応でも進んでいます。
それでは、病院は医療機能の変化に十分対応できているのでしょうか?答えは否です。医療内容の進歩と専門化により、診療に必要な医師数はどんどん増加しています。
当院の医師数は開設時の約3倍に増加していますが、まだ不足しています。当院は築30年以上を経過し建て替え計画の真っ最中ですが、改めて驚くことは各診療科の外来スペースが30年前には極めて狭かったことです。とくに耳鼻科、泌尿器科などのいわゆるマイナー科は医師1人か2人での診療が前提となっていました。現在では改造を積み重ねて、泌尿器科では4診のスペースを確保し対応しています。
さて、社会問題にもなった医師不足ですが、どこで起こっているのか改めて考えてみましょう。
地域が医師を必要とするのは、当たり前ですが困ったときです。困ったときの医療は救急医療で、そのほとんどを担っているのは急性期病院です。医師不足は急性期病院に医師が足りないということなのです。
しかし、「医療従事者の需給に関する検討会」の議論は医師総数、地域偏在、診療科偏在などの問題にすり替えられ、見方を変えると 医師は足りているので心配ないといっているのです。
医師の勤務形態は大きく分けると勤務医と開業医の2通りがあり、勤務医不足の問題はその比率が改善するよりも悪化の方向にあります。急性期医療を担う病院の勤務医は、その比率の低下が見てとれます。
私の手元に興味深いデータがあります。私は2つの大学の同窓会員でさらに別の大学の同門会員ですが、この3大学を卒業した医師の30年間の勤務医比率を集計してみました。
最初の2つの大学の勤務医比率は卒業直後から卒後15年目頃までは上下変動し最低値は50%前後となりますが、その後上昇に転じ、卒後30年目すなわち定年が近づく頃には80%近くになります。それに対して3番目の昭和40年代に開設されたいわゆる新設医科大学では卒業直後の勤務医比率が最も高く80%以上ですが、その後30年目まで低下し続け最終的に50%前後となっていました。ここに挙げた3つの大学はいずれも国立大学ですが、これほどの差が出ます。極めて少数の事例ですので普遍的なものとはいえませんが、医科大学の新設や定員増は医師総数の増加に役立っても、自由開業の原則がある限り診療最前線となる病院の医師不足解消にはならないのではと感じます。
ここで考えなければならないのは医師数が大学の設置、定員などで厳しくコントロールされているのは何故かということです。医師は高い倫理性を求められ、また社会的に敬意を払われている職業です。そのような職業人の育成が厳しくコントロールされるのは当然のことですが、一方で社会の要請に応えることもまた当然の義務です。社会は困ったときの医師、すなわち救急医療をしてくれる医師を求めています。救急医療は救急科のみの仕事ではありません。何科であっても急性期医療を行う場所にいることが社会の要請に応えることになるのです。「困ったときの友が本当の友」という言葉がありますが、困ったときに人の役に立つように医師は自分たちが社会的に高く評価・保護されていることを認識し、いわゆるノブレス・オブリージュを果たすべく行動する必要があると考えます。
おおた・のぶたか
1978年北海道大学卒業後、浜松医科大学泌尿器科、焼津市立総合病院を経て2001年東京大学泌尿器科助教授、2003年に天皇陛下の前立腺がん摘出 手術の主治医団長を務める。2004年焼津市立総合病院病院長、2015年より現職。
※ドクターズマガジン2016年8月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
太田 信隆
人気記事ランキング
-

著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
三谷 雄己
-
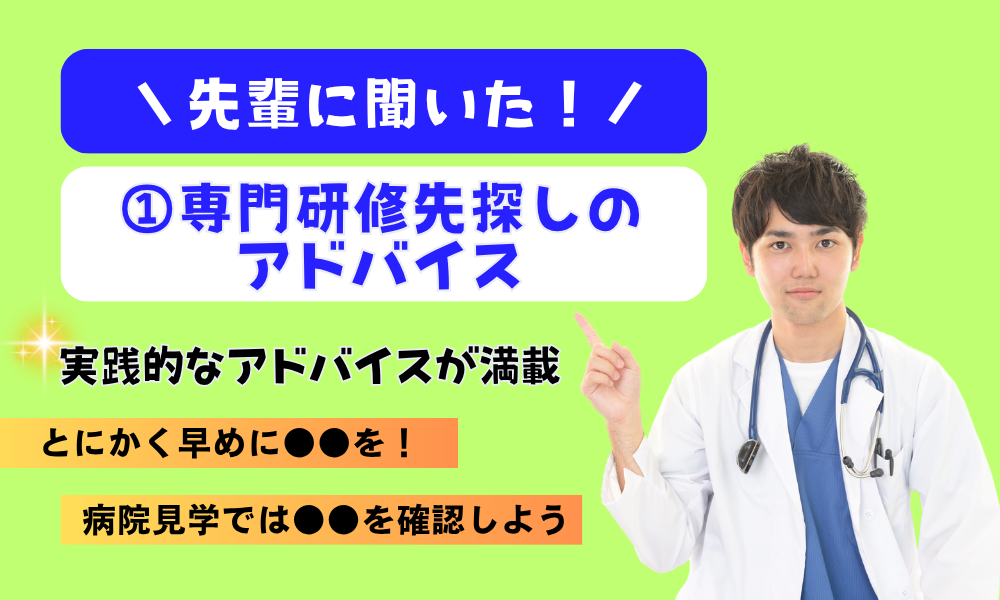
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
-
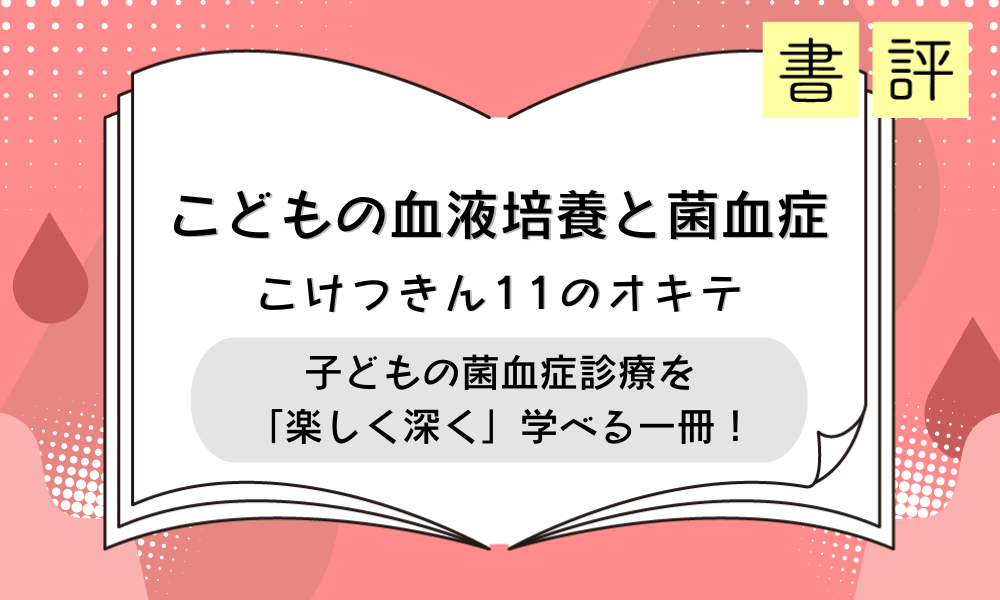
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
永井 友基
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-
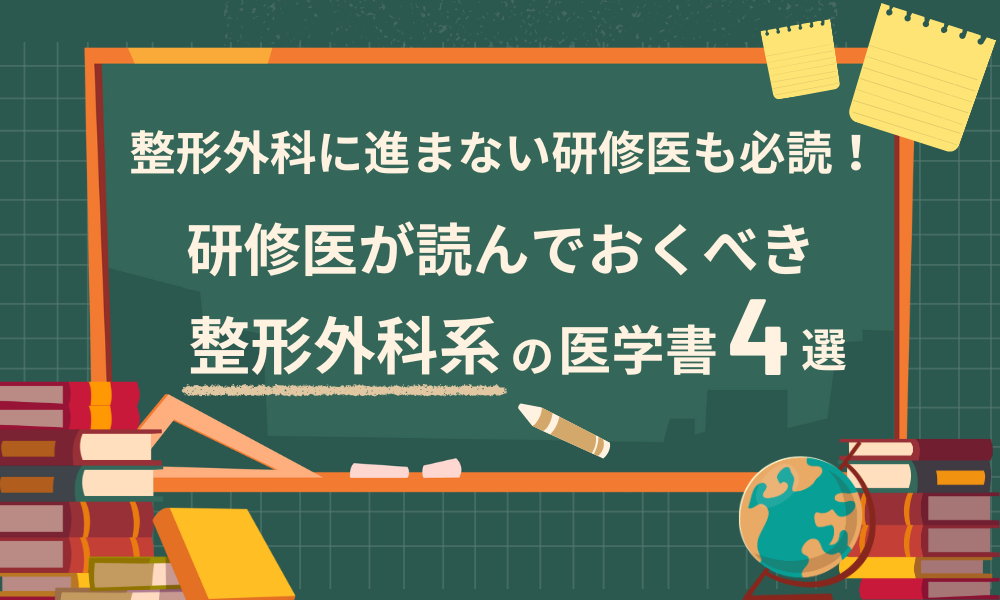
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-

2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
