記事・インタビュー
公益財団法人 北海道医療団 帯広第一病院 院長
富永 剛
今年で初期臨床研修義務化が始まって丸10年、制度はすっかり根付いた感がある。節目の年とあってさまざまな評価がなされているが、「成功」と「失敗」の評価は相半ばしているようだ。
北海道の地方都市の基幹型研修病院である当院はこの制度に翻弄されてきた。当院は内科・外科を中心とするケアミックス病院(300床)だ。北海道にありつつも、歴史的に東北大学と関連が深い。
東北大学では、昭和40年代から「関連病院で3年前後の研修を受けてから入局する」という流れがあった(マイナー科は直接入局する)。現在との違いは、「研修医が卒業時に志望科を決めていた」ことだ。当時は、毎年当院にも研修医がやって来て、志望科中心の研修をしつつ、ローテーションも行っていた。
例えば、外科志望者であれば、外科の基本を身に付けた後、外傷治療に必要だと感じたら脳外科や整形外科、周術期の不整脈に不安があれば循環器内科と、自ら目的を持ってローテーションをしていた。結果として、現在のように「医師として何も分からないうちからローテーション先を決める」というよりも充実した研修ができていたように思う。
実技を重んじる当院の研修は、現在もその流れを引き継いでおり、内視鏡や手術など、手技を数多く経験してもらっている。今年の外科重点研修の修了者には、2年の間に腹腔鏡を含む100例以上の手術を経験してもらった。
2004年の臨床研修義務化に際しては、中小病院故の苦労も多くあった。当初は協力型病院の確保、指導医の養成に苦労し、ようやく軌道に乗ってきたところ、2009年からは研修病院の認定資格に「年間入院患者が3000人以上」という条件ができ、当院は資格を失いかけた。その後、激変緩和措置によって救われていたが、その期限も迫り、「このままでは死活問題だ」と、2010年春には厚労省に直接陳情にも行った。これが功を奏したわけではないだろうが、「初期臨床研修制度の評価のあり方に関する研究(桐野班)」が行われることになった。
桐野班では、年間入院の条件は満たさないものの、コンスタントに研修医を受け入れてきた病院を直接訪問し、研修の質を調査した。当院も全国7病院の調査対象に指定された。研究班は「規模の小さい病院でも研修はできる」という結論を出し、当院は「毎年調査が入る」という条件付きながら、指定存続が認められた。
かろうじて救われたものの、なぜ厚労省は中小病院から研修医を締め出したのか、甚だ疑問に思う。そもそも、初期臨床研修制度ができた理由は、研修医の待遇改善もさることながら、「Common Diseaseを診られる医師を育てる」ことにあったはずだ。大病院は専門性の高い医療が求められ、症例にバイアスがかかる。その点、地方の中小病院はCommon Disease の宝庫だ。短期間の地域医療という形ではなく、中小病院で腰を据えた研修をさせた方が良いはずだ。
結局、初期研修義務化は成功だったのか。個人的には「成功とは言えない」と思っている。この制度だけが要因ではないにせよ、医療崩壊の大きな要因となったことは誰しも認めるだろう。
研修医の待遇改善には一定の評価ができるが、卒後3年以降は置き去りのままだ。マイナー科専攻の人には良い面が多いが、全身管理を行う科の医師にとっては遠回りさせられる感がある。基礎に進む人も減った。臨床医局でも入局年度が遅くなり、研究生活に入る年齢が高くなっている。科学立国を謳うわが国にとってこれで大丈夫なのか、と不安になる。
一方、研修制度自体も変化している。2009年からは必修項目が減り、実質的に約1年間必修科目を学べば、残りは志望科に専念できるようになった。これは制度の理念が骨抜きにされた印象だ。そして、その間に卒前教育も変わった。CBTやOSCEが導入され、大学教育も見学型から参加型へ変貌を遂げつつある。全国医学部長病院長会議が示す「Student Doctor 制度」を充実させ、学外病院実習を活用すればCommon Diseaseの診療能力は卒前に習得できる可能性もある。そうなると、初期臨床研修制度の存在そのものに、疑問符がついてしまう。
2004年の初期臨床研修義務化は日本の医療の大きな変換点だった。今後、この制度はどうあるべきか。
こんなことを考えつつも、まずは優秀な研修医に来てもらうべく、担当者にゲキを飛ばすとともに、見学に来た学生をもてなす日々が続く。
※ドクターズマガジン2014年7月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
富永 剛
人気記事ランキング
-

著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ (jmedmook)』
三谷 雄己
-
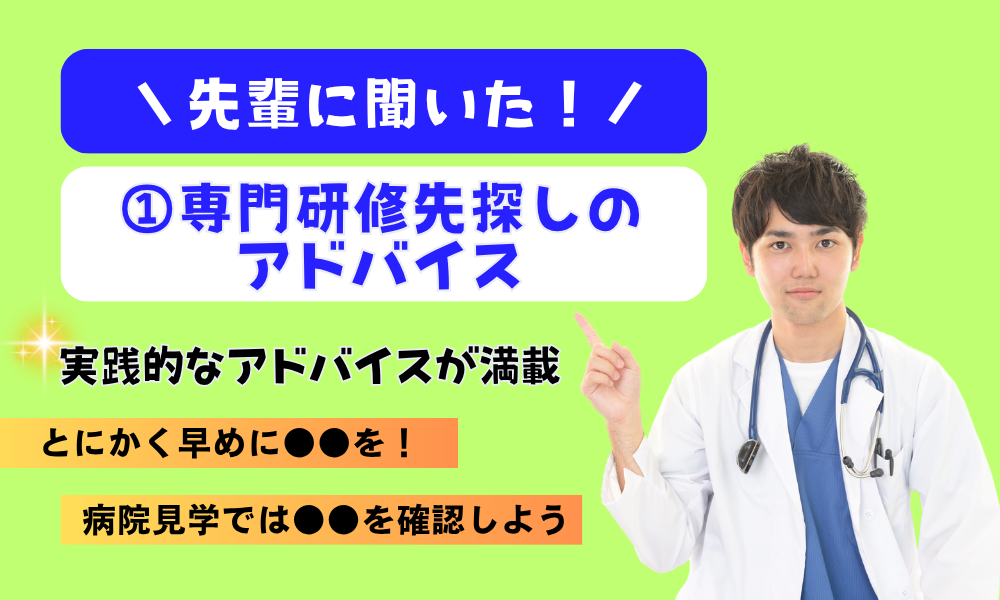
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ①専門研修先探しのアドバイス
-
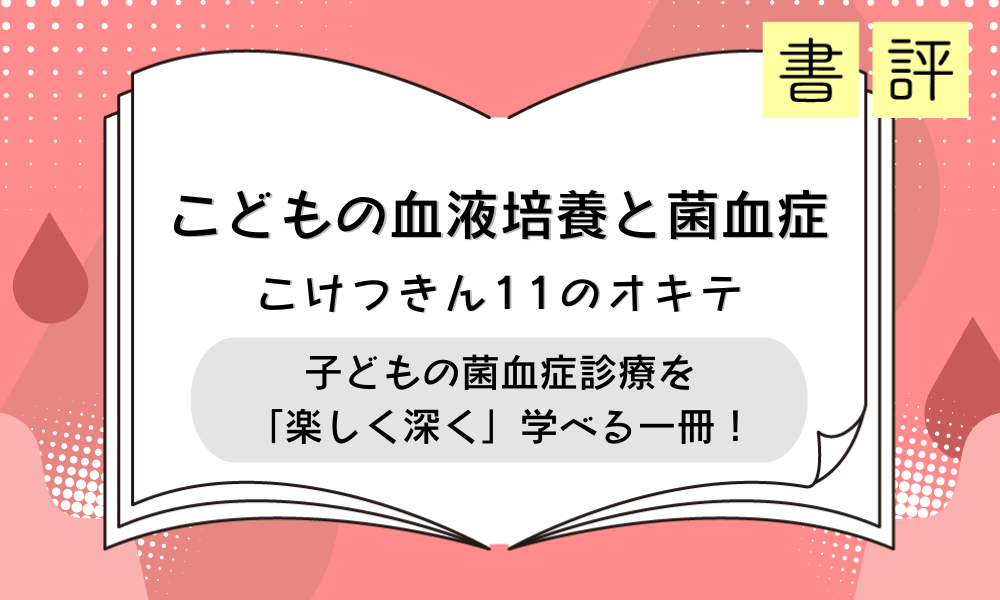
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『みんなで楽しくホスピタリストになろう!エビデンスと実臨床の架け橋』
永井 友基
-

医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
- ライフスタイル
- 開業
- お金
医師が選ぶならどんな保険?お得な保険の選び方
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっくんといっしょ エコー解剖のひろば』
石田 岳
-
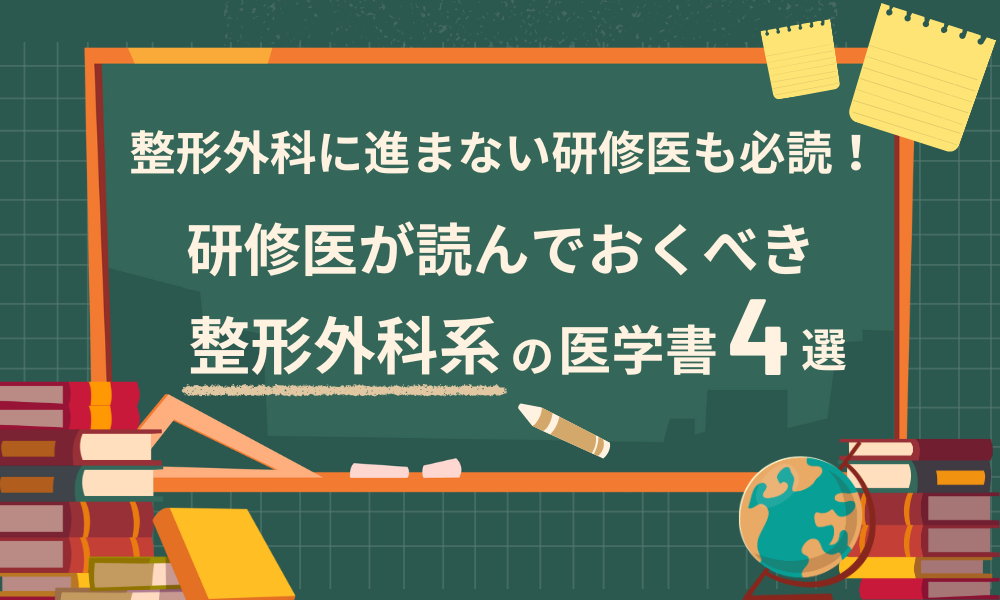
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
整形外科に進まない研修医も必読!研修医が読んでおくべき整形外科系の医学書4選
三谷 雄己【踊る救急医】
-

著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『暗記しやすい! 医療現場の言いかえ英単語』
山田 悠史
-

研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
- 研修医
- ライフスタイル
- お金
研修医や専攻医などの若手医師でも、医師賠償責任保険は必要?
-

2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
- ベストセラー
- 研修医
- 医書マニア
2025年最新版 初期研修医におすすめの救急を学べる医学書10選
三谷 雄己【踊る救急医】
