記事・インタビュー
医療法人社団愛生会昭和病院 院長
杉内 登
当院は岩手県最南端、世界遺産の平泉を訪れる拠点都市として人口約12万をかかえる地方都市、一関市にある54床の小さな内科系民間病院である。新築建て替えを決意したのは、2009年6月であった。当院は築40年が経過しており、公的機関からも耐震診断を受けるように勧められていた。三陸沖地震の発生確率は当時30年以内に99%の確率で起こると言われており、岩手県に耐震建築の補助金制度があることを知って、直ちに申請の手続きに入った。昨年まで医師数は4名、うち3名が80歳以上で一番若い私でも還暦が近く、大学では年寄り扱いされていたが今では若先生と言われ、大分違和感を感じている。
この地域は人口10万人あたりの医師数が全国平均を大きく下回る150人以下であり、さらに医師の高齢化も進行しており、宮城、岩手県とも医師が減少しているのが現状である。その中で当院は2次救急輪番病院としてほぼ8日に一度担当しており、年間270台前後の救急搬送を受け入れている。現状の診察入院体制を維持したまま、2010年12月に新病院建築が始まった。
しかし、忘れもしないあの悪夢が襲って来た。旧病院の3階でいつものように病棟業務をこなしていた14時46分、突然スタッフの携帯の緊急地震速報が鳴り響き、間もなく細かい横揺れが始まったかと思ったら強烈な縦揺れが始まり物に摑まっているのがやっとの状態となった。揺れはなかなか収まらずさらに強くなり、電源が吹き飛び停電した。揺れはさらに続き、床か天井が落ちるのではないかと思い、一瞬死を覚悟した。やっと揺れが収まり、院内は白煙に包まれ職員が患者様の安否確認に走った。
幸い入院、外来患者様、職員に怪我はなく、通常診療は中止して救急対応に切り替えた。予備電源が30分しか持たないため新築現場の発電機から電源を回してもらい、輸液ポンプや重症者のモニターなどの電源にあてることができた。人工呼吸器管理中の患者様は、従圧式の人工呼吸器に変更することで事なきを得た。窓は全て揺れで開き、数カ所に亀裂が入った状態だったが診療は可能と判断し、継続して救急患者の受け入れを決定した。停電のため情報は個人の携帯とラジオからで、沿岸があれほどの大津波に襲われているとは全く思っていなかった。また隣の栗原市に震度7の情報があり、軽傷患者の受け入れ準備をしていた。
深夜には沿岸部の陸前高田市から津波を逃れた高齢者が搬送され、懐中電灯と石油ストーブで暖を取りながら診療にあたった。しかし、沿岸部や近隣からの軽傷患者は殆んど来なかった。これは阪神大震災や中越地震とは大きく異なり、津波のため重症者は少なくほとんどが津波に巻き込まれ死亡したからと後でわかった。当院でも南三陸町に帰省していた職員1名が津波に巻き込まれ帰らぬ人となった。
当院のみならず内陸地域の病院は、地震による被害を受けながらも停電の中医療を継続していた。しかし、マスコミも行政もどうしても沿岸部の甚大な被害の医療機関に注目するため、被災者である我々は知らぬ間に被災者でなくなっていたように感じる。もちろん震災被害に対する補助金はなく、建築の補助金も減額されるダブルパンチとなった。行政サイドも、震災時に頑張った内陸部の医療機関をもっと評価しても良いのではないかと思う。
震災により基礎の鉄筋が全て緩んでしまい、やり直しを余儀なくされた。停電は3日間で回復して水道も使用できるようになったが、慢性疾患の急性増悪の症例が増え始め、暖を取るために練炭を使用した一酸化炭素中毒の患者が搬送されるようになった。震災直後は、今後の薬剤の補充の見込みがつかないため数日の処方で制限をかけた。震災後約10日で医療活動はほぼ正常に戻ったが、殆んど十分な睡眠が取れない状態であり、知らず識らずのうちに体力を失っていたのか、私自身が突然帯状疱疹を患うことになった。幸い内服で痛みもなくなり完治したが、これほど体力を失っていたとは想像もしなかった。再び4月9日に震度6弱の最大余震に襲われ、またもや組み直した鉄筋が緩んでしまった。結果2ヶ月完成が遅れ、建築資金も増額を余儀なくされたが、2012年6月1日に無事にグランドオープンすることとなった。今後、東南海巨大地震の発生確率が高いと指摘されているが、二度とあのような震災は経験したくないし、また発生しないことを祈るばかりである。
※ドクターズマガジン2014年4月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
杉内 登
人気記事ランキング
-

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
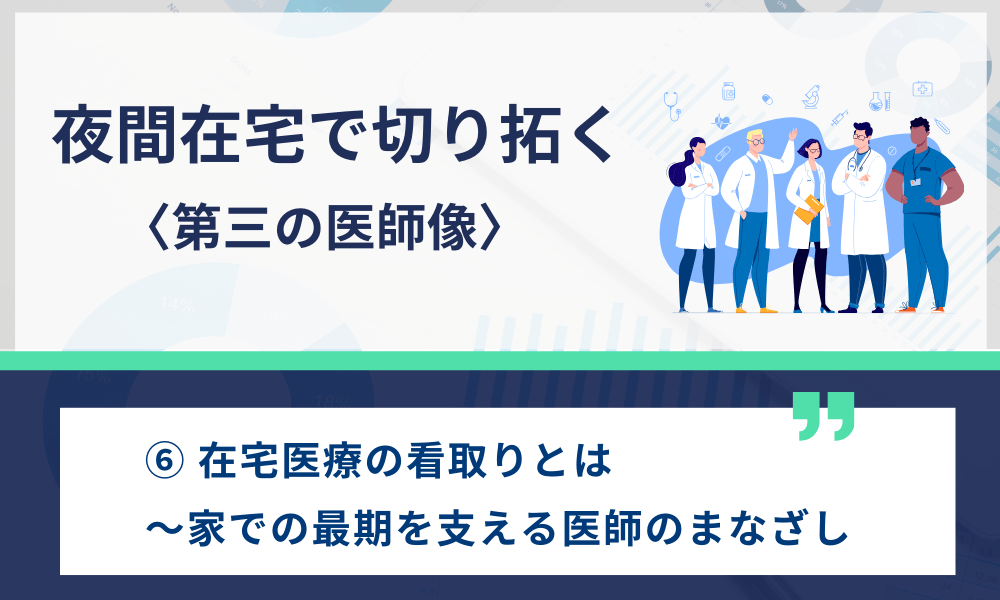
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし
- イベント取材・広報
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし
株式会社on call
-

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供
京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ
-

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025
- イベント取材・広報
【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025
令和7年度神奈川県地域医療支援センターイベント業務運営事務局
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」
- 研修医
瞬速レクチャー~救急編~「ショック」
-

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―
-
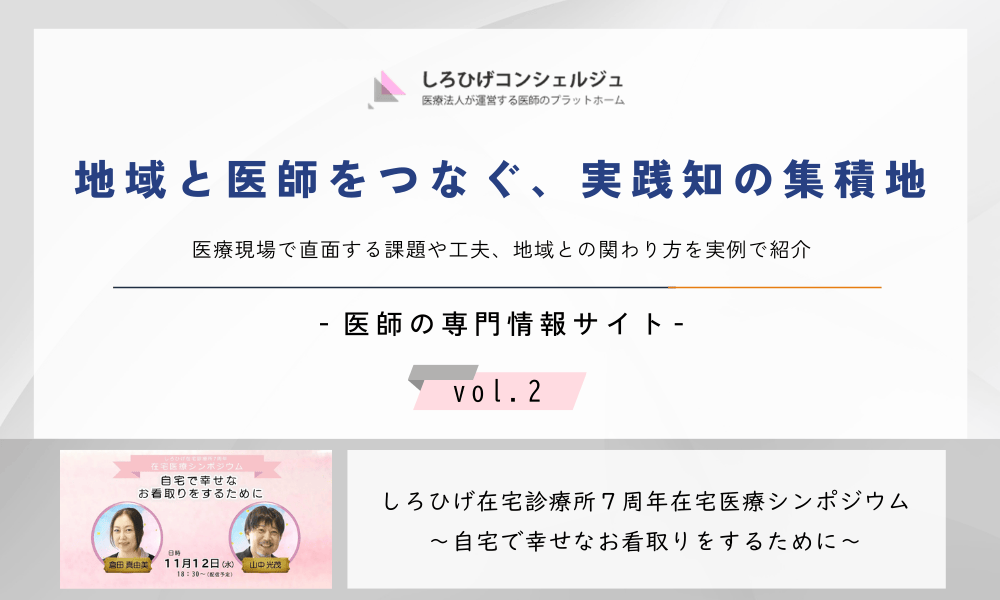
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】
しろひげコンシェルジュ
-
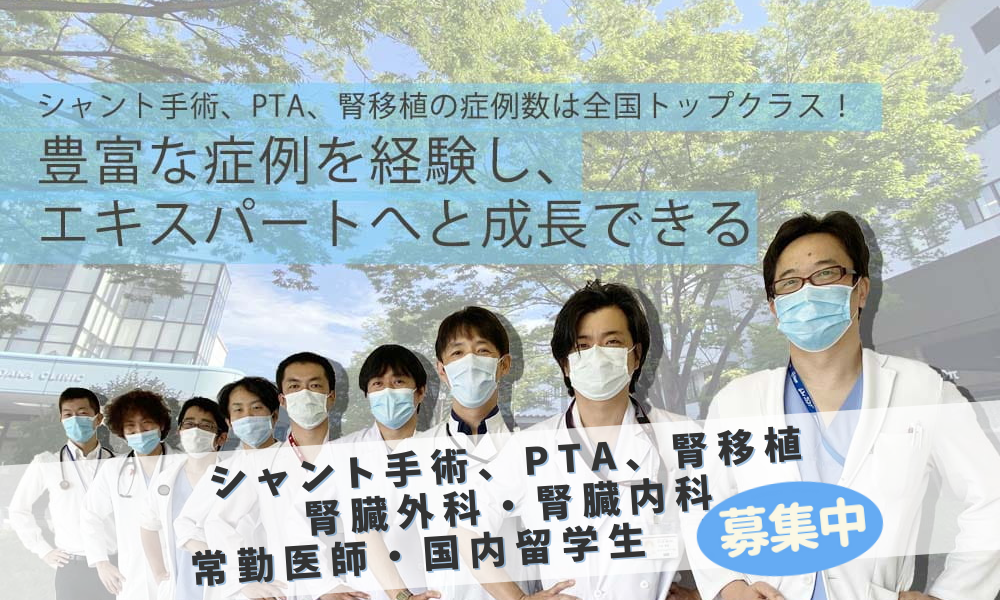
【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる
- ワークスタイル
- 就職・転職
【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる
添野 真嗣、久保 隆史
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
