記事・インタビュー
独立行政法人国立病院機構南九州病院長<br/ >福永 秀敏
思いがけず「がん」や「難病」などの病名告知を受けたり、あるいは治療中に思わしくない結果の説明をされたとき、人間のとりうる行動はさまざまである。
「患者さんがいなくなりました」という情報が、当該病棟の師長から医療安全管理者にもたらされたのは、ある日の夕方の5時すぎだった。捜索を始めたが、かねてより病院にとめてあったという車(セルシオ)が見つからない。そこで、無断離院の可能性が高くなった。
この67歳の患者さん、地元で不動産業を手広くやっていたが、肺がんが見つかった(転移もある)。入院したときには、手術は無理との診断で、化学療法と放射線療法中だったが、治療方法をなかなか素直に受け入れられない様子で、ガンマナイフや民間療法についても相談していた。この日も主治医と今後の治療計画について話した後、ちょっと様子がおかしいと感じた師長が彼に声をかけ廊下の長椅子で20分ほど話をした。後に「売店に行ってきます」と言ってその場を離れたが、「自殺を考えたりする」というような言動も聞かれたので、師長は気になっていたという。家族とも相談して警察に捜索願を出し、出かけそうな場所を探したが有益な情報はないまま時間はすぎていった。
ところが夜の8時に、友人をともなってひょっこり帰って来た。何事もなかったかのように、「友だちがスッポンの血を飲むと元気が出るというので釣りに行った」と言う。そのスッポンであるが、当初2匹釣り上げたのだが、よくよく聞いてみると2匹ともに逃げられてしまったそうだ。「外出許可をとってくだされば良かったのに」と師長が言うと、「白血球が減っているので、外出は許してもらえないでしょう。抜けるにはこの時間帯がいちばんいいと思っていた」、「あと10年は生きたいという気持ちと、早く決着をつけたい気持ちとが揺れ動くんだよな」と、今度はしみじみと自分に言い聞かせるように話す。「今夜はゆっくり休みましょうね」と師長が話しかけると、初めて笑みがこぼれた。
さて「スッポン釣りに出かける」というちょっと滑稽で悲しい行動は、私にもよくわかる。「太陽と死は見つめられない」という言葉もあるように、突然がんと診断され余命いくばくと告知されたら、誰だって気が動転するだろう。
死の不安を克服してきた先人を見るとき、一生懸命にその日、その日を生きることが、死の不安から逃れる近道のように思えてくる。
10年ほど前に、あたかも旅行にでも出かけるように超然と旅立った35歳の筋ジストロフィーの青年は、「死について」次のように書き遺している。
「入院したときに8人の同級生がいたが、20歳を境に次々とこの世を去った。彼らが志半ばで逝くたびに死への恐怖が襲った。気管切開を受ける前は、冬が来るたびに感冒に神経をとがらせていた。友だちが亡くなると、次は自分の番ではないかと常に死を意識しながら春を待っていた。ただ同病の兄の死に顔を見たときには、なぜか冷静に受け止められた。生前に何事にも一生懸命に取り組む姿を見ていたからだろう。
近い将来、私も死を迎える。死を前にしていかに生きるか、その答えは、過去にこだわらず、常に前向きに生きていくことではないだろうか。今日が終わらなければ明日は来ない。今日を楽しむことがすべてである」
また、プロレスラーの小橋健太は腎臓がんの術後で、いつも再発への不安を抱えている。それでも、「やりたいことをやって1、2年しか生きられなくてもいい。リングで必死に生きることで、不安を乗り越えている」と正直な思いを吐露する。
死の不安に対して仏教は、「今生きている、生かされていることを精一杯生ききっていけば良いのだ」と教えている。今までの医学では、生かすこと、治すことだけに力を入れて、老病死となると、宗教の世界のこととして関心を払わないきらいがあった。ところが、高齢社会になり、また、がんや難病のように現代医学をもってしてもいかんともし難い病気も増えている。このような状況下で医師は病気にどのようなスタンスで臨めばいいのか、医学の教科書には書かれていない。
一人ひとりの人生は、いくつかの小さな物語からなる大きな物語である。患者さんと人生を語り合い時間を共有することで不安を和らげ、彼らの人生の終末を豊かなものにできないだろうかと、時間に追われるような日々の中で常々考えている。
※ドクターズマガジン2010年1月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
福永 秀敏
人気記事ランキング
-
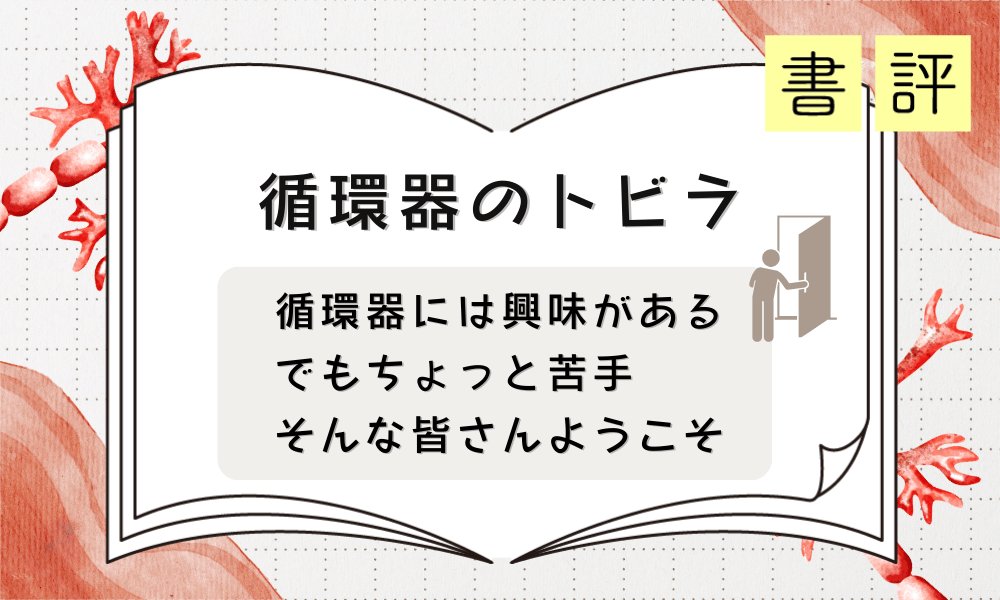
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
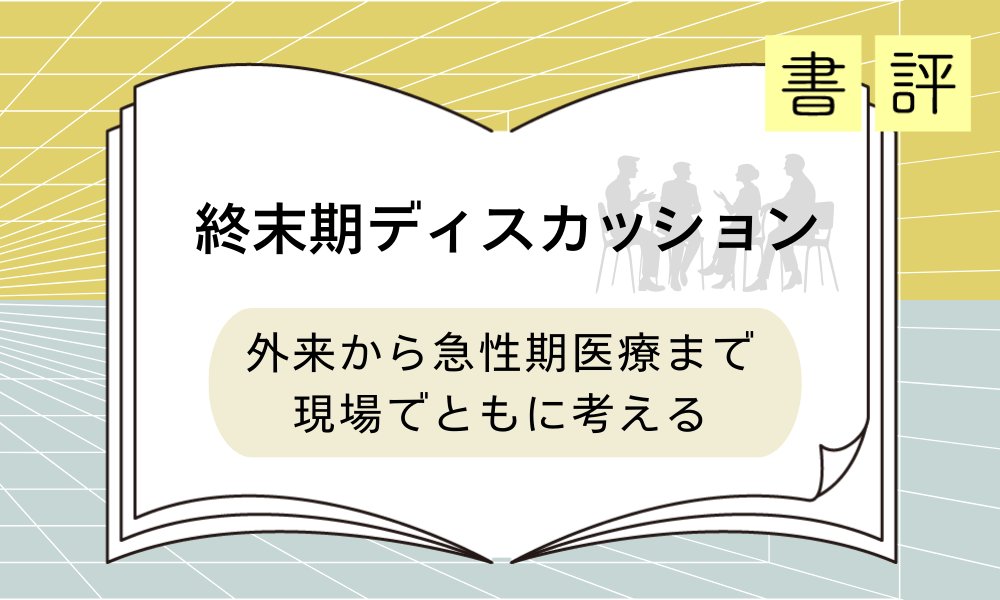
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
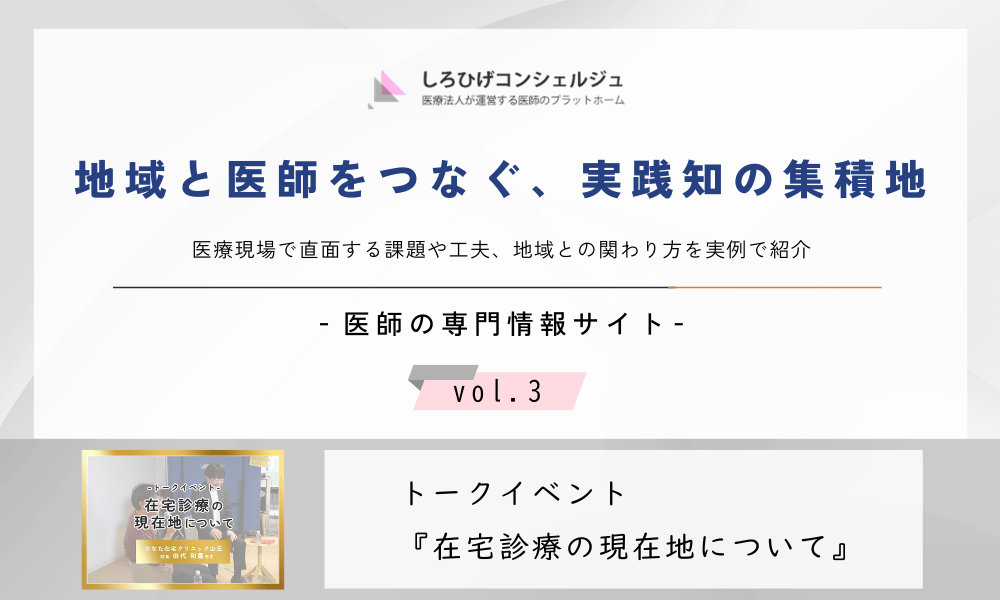
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
