記事・インタビュー
聖路加国際病院
アレルギー膠原病科(成人、小児)
岸本 暢将
EBM教育の第一人者、名郷直樹先生の連載を継続して、様々な科のリーダーに協力をいただき、これから1年にわたり日常診療の「常識の非常識」をお伝えしていきます。初回は日常診療とは関係ありませんが、医学生や研修医に送る言葉として「留学経験」について話します。
米国へ留学する日本人が減っているそうです。中国や韓国からハーバード大学への留学生は急増し、日本人は危機的な状況だそうです。なぜでしょうか。今の生活に満足している、日本の教育は世界一で米国に行く必要はないという意見もあり、英語の環境に自分を置くのが怖い、世界で活躍する学生・同僚と競争する自信がない、などネガティブな理由もあるようです。
私は2001年からハワイ大学研修医として内科を3年間勉強しました。英語のハンディがあり、「上級医や周囲のコメディカルが快適に仕事できるように」という目標をたて、自主的に朝5時までに病院へ行き、上級医が来る7時までに回診を終え、診療記録や指示を書き終えていました。上級医に余裕ができると指導時間も増え、研修内容も充実します。そんな努力が実り、米国人を含む20人弱の同期の1年目研修医(インターン)の中で、ベストインターン賞をいただきました。上級医に楽をさせ、学生に対しては時間の許す限りミニレクチャーをして課題を与え、あとで教えてもらったりと双方向性の指導を心掛けたのが良かったのでしょう。後輩から信頼を得られ、人に教えることで自分の不明点が再認識され記憶定着にも役立ちます。
もう一つ意識していたのはスマイルを絶やさないこと。インターンのとき慕っていた上級研修医から、「いつでも笑顔で仕事をしろ」と言われていたからです。その先生のアドバイスは「夜勤でとても眠いときでも、些細なことで患者さんに呼ばれたときでも、どんな患者であろうとも、必ず診なくてはならないのであれば気持ちよく診たほうが誤診も少なくなる」というものでした。今も私はその言葉に共感しています。
またハワイ大学1年目に、日系人でリウマチ膠原病の専門医、Ken Arakawa先生との出会いは私の人生を変えました。先生のもとでの研修は、患者さんの半分が高齢者でした。もともと全身疾患を診たいと思っていた私にとり、リウマチ膠原病はぴったりのテーマでした。当時、日本では承認前だった生物学的抗リウマチ薬を米国では関節リウマチの患者に使っていました。その注射に、2カ月に1回、日本から通院する患者さんが何人かいて、抗リウマチ薬を打つと「先生、本当に良くなるんですよ」と言って、皆さん喜んで元気に帰っていきました。
「この分野をもっと勉強して、日本に伝えなくては」と思いを強め、総合内科研修後はリウマチ膠原病の専門研修(フェローシップ)を志し、ニューヨーク大学のプログラムに進み、改めて専門研修の素晴らしさに驚きました。開始当初の7月は、通常の病棟業務もあるのですが、毎朝月曜から金曜日の朝8〜9時に、さまざまな科のエキスパートがフェロー(専門研修医)向けのキックオフレクチャーをしてくれます。
米国では専門医への病診連携が比較的スムーズに行われており、ある病気のエキスパートであれば他施設からも多くの紹介患者が訪れます。短期間で集中的に学ぶ専門研修を行うにはまたとない環境です。例えばニューヨーク大学皮膚科の膠原病専門外来には、東海岸のあらゆる病院から患者さんが集まり、そこで外来研修をすれば、膠原病の皮膚病変のほとんどを数カ月で診られます。また、年2回、世界的に有名な先生の前でレクチャーをする機会もあり、プレゼン能力も鍛えられました。
医学生研修医の方にお伝えしたいのは、「どんな形でも良いから海外へ出よう!」ということです。昔と違って情報を得る手段が多く、わざわざ海外に行く必要性を感じないようですが、それは勘違いだと思います。間接的に得た情報だけを鵜呑みにするのでなく、自分の目で確かめて、良い点悪い点を比較してほしいのです。実際の医療現場を体験すると、単に批判的な目で見るのと異なり、米国式の良い部分も悪い部分も見えてきます。その上で、日本にない米国式の優れた部分を日本に伝え、逆に米国にない日本式の優れた部分を発信したいと思っています。
一度しかない人生、皆さんも自分の目で確かめて、自分にしかできない新しい道を切り開いてみるのはいかがでしょうか。
※ドクターズマガジン2012年1月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
岸本 暢将
人気記事ランキング
-
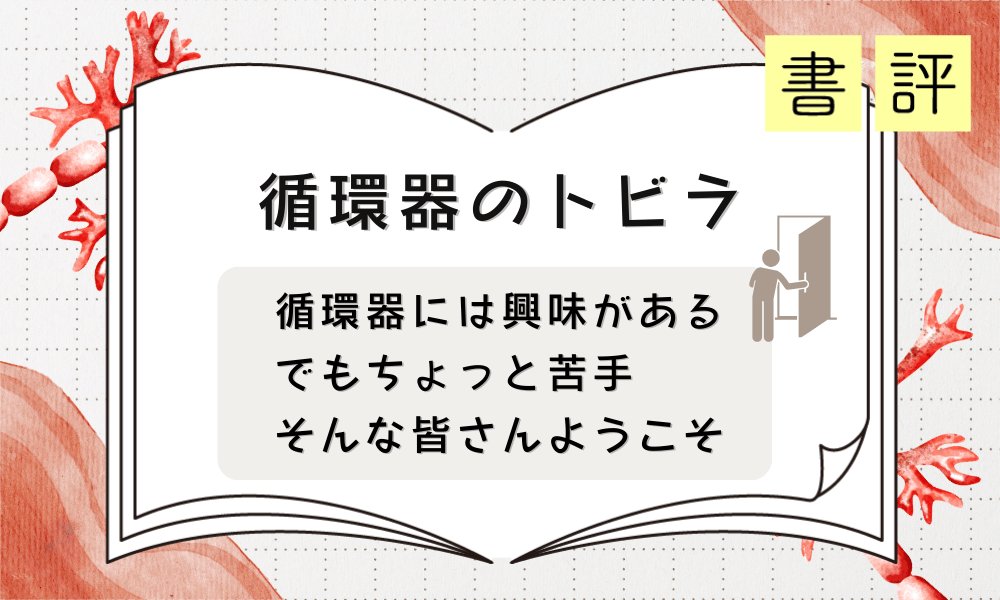
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
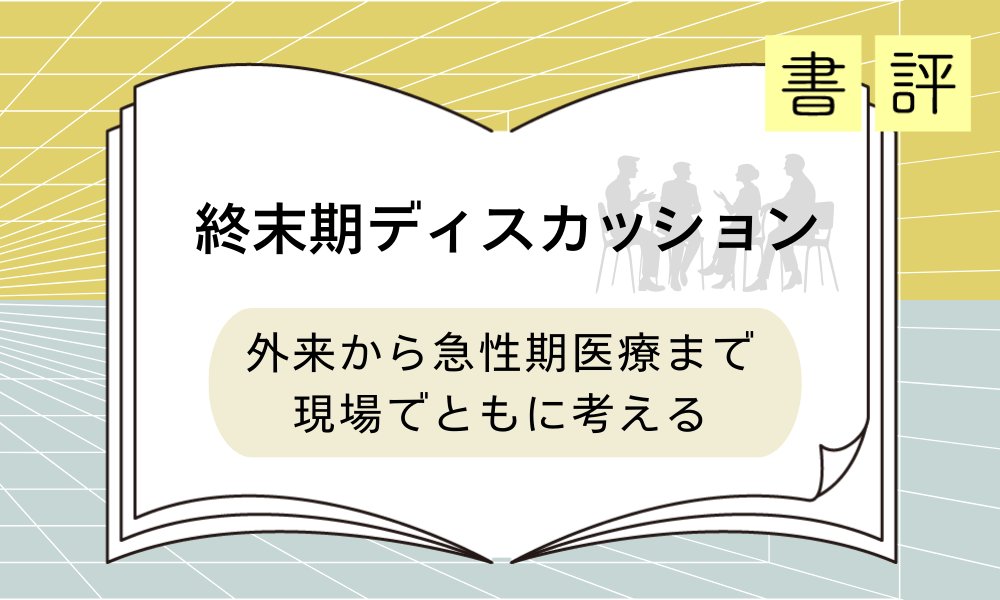
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
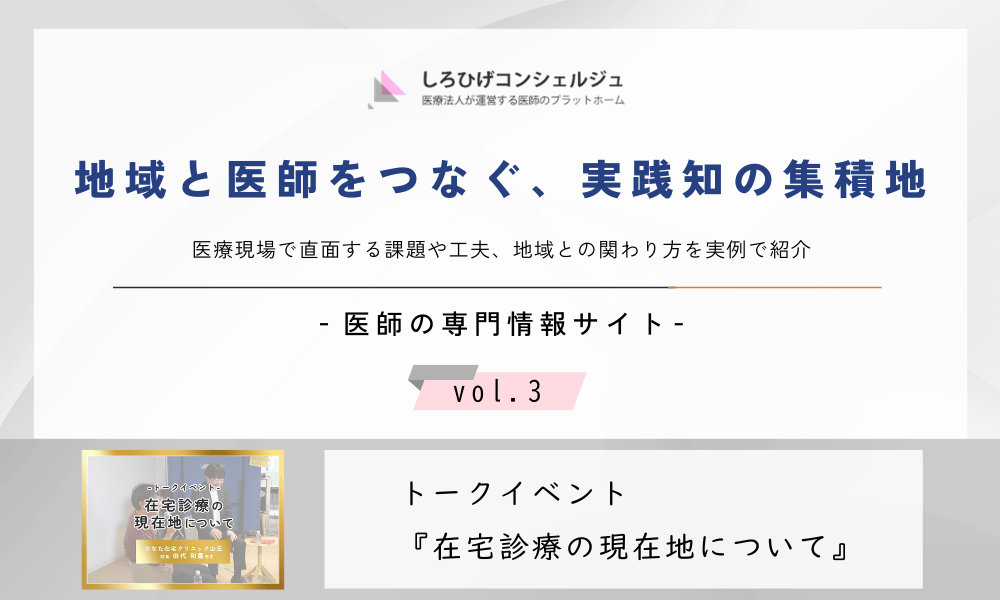
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
