記事・インタビュー
東京女子医科大学 放射線腫瘍学講座
教授・講座主任
唐澤 久美子
第3期がん対策推進基本計画には、患者本位のがん医療の実現の一環として高齢者のがん対策が挙げられている。私は2018年度より厚生労働科学研究「高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究」班(研究代表者福岡大学田村和夫教授)に入れていただき、高齢者のがん診療について考える機会を得てきた。
がんはそもそも高齢者に多い病気である。2017年の全国がん登録では、がん罹患者の31%が65~74歳、44%が75歳以上であり、合計75%のがん患者が65歳以上である。実は高齢者のがん医療こそが、がん医療の本流なのである。
高齢者の特徴は、身体機能低下の進行、認知機能が低下傾向、併存症を持ち薬剤を服用、人生の残り時間に制限あり、人生の達成感をある程度持っているなどである。高齢者は、前期高齢者(65~74歳)、後期高齢者(75~89歳)、超高齢者(90歳以上)に分けられる。前期では非高齢者と同程度の心身機能を持つ人も多くなってきたが、個人差は大きい。後期となると年々心身機能の低下が進行し、超高齢者では顕著になってくる。高齢者のがん医療といっても、年齢や心身機能により一概には決められない。
現代の医療では科学的根拠に基づく医療(エビデンス・ベイスト・メディスン)が重要視される。ところが、がんに関する臨床試験の多くは健常成人を対象に行われており、高齢者を除外したランダム化比較試験に基づいてエビデンスを構築し、標準治療を定めている。患者の大多数を占める高齢者では、どのような治療が良いのか、健常成人と比較して認容性に問題はないのか、エビデンスが乏しく、エビデンス・ベイスト・メディスンが行えない、手探りの状態なのである。
健常成人対象の臨床試験での主なエンドポイントは、全生存期間、無病生存期間、生存率、腫瘍消失率などである。しかし、高齢者では、年齢や心身の状態、今後の人生に対する考え方によって、がん治療のエンドポイントが、健常成人とは異なってくると思う。高齢患者の望むエンドポイントは生存期間の延長とは限らない。人生における仕事を成し遂げ、穏やかな時を過ごしながら人生のしまい方を考えていた人は、有害事象は強いが生存期間を数ヵ月延長できるような治療は選択しない可能性がある。健康寿命(自立して生活できる期間)の延長を優先し、生活の質を下げない程度の治療を希望するかもしれない。あるいは、治療による有害事象でつらい思いをするくらいなら治療を希望しないという人もいるかもしれない。人生のしまい方を決めるのは本人である。
医療の目的は、健康の増進によりその人の人生を良くすることである。その医療によって自分の人生が良くなるかを決めるのは本人であり、ナラティブ・ベイスト・メディスンが注目されるようになってきた。エビデンス・ベイスト・メディスンでは人間を生物一個体として捉え、客観的なデータにより治療法を決めている。しかし、ナラティブ・ベイスト・メディスンでは、その人の考え方や生活を尊重して治療方針を決定する。患者の生き方、考え方、社会的立場、家族関係などの物語(ナラティブ)を伺い、医師の物語(診断や推奨する治療法)を患者にお伝えする。その上で、患者と医師の物語をすり合わせ、「それぞれの方法には意味がありますが、どうしましょうか、あなたはどう思いますか」と対話をして、患者の意思に従って治療を決めていく。医師の物語を勧める上では、高齢者機能評価(geriatric assessment ,GA)などで、患者が有する機能を評価して推奨を決める必要がある。
高齢者のがん治療が、医療者や家族の思い込みや希望で決定されてはならない。本人の意思を尊重し、十分な判断ができない状況であれば意思決定を補助し、あるいは意思を推察するべきである。エビデンスを踏まえたナラティブ・ベイスト・メディスンが、真に患者の人生を良くするための医療に求められているのではないだろうか。医療は、医療を受ける本人のためのものである。
からさわ・くみこ
1986年東京女子医科大学卒業。東京女子医科大学放射線医学教室、順天堂大学放射線科、独立行政法人放射線医学総合研究所などを経て2015年より現職。東京女子医科大学前医学部長。専門はがんの放射線治療。
※ドクターズマガジン2020年12月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
唐澤 久美子
人気記事ランキング
-
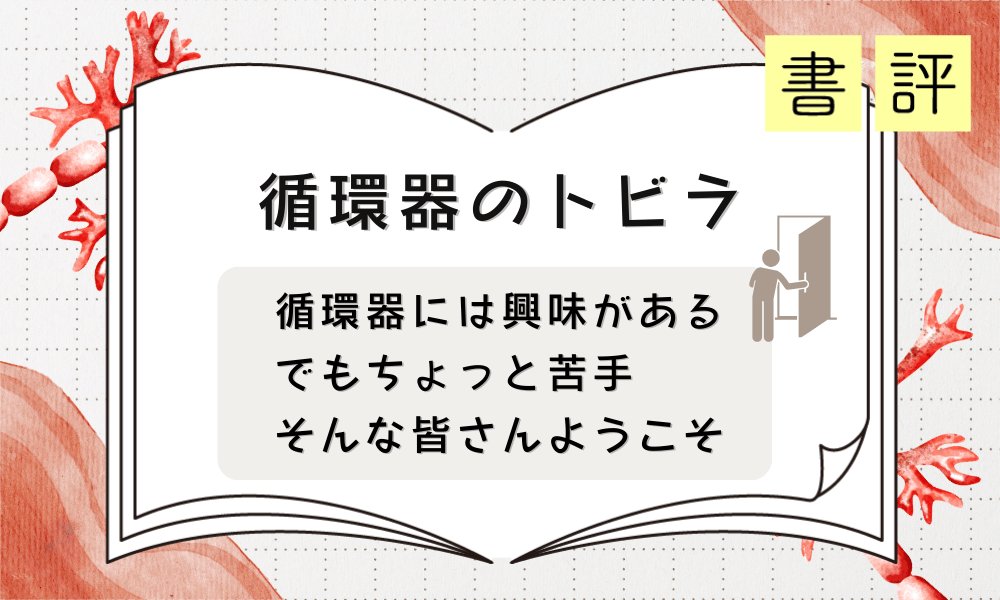
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
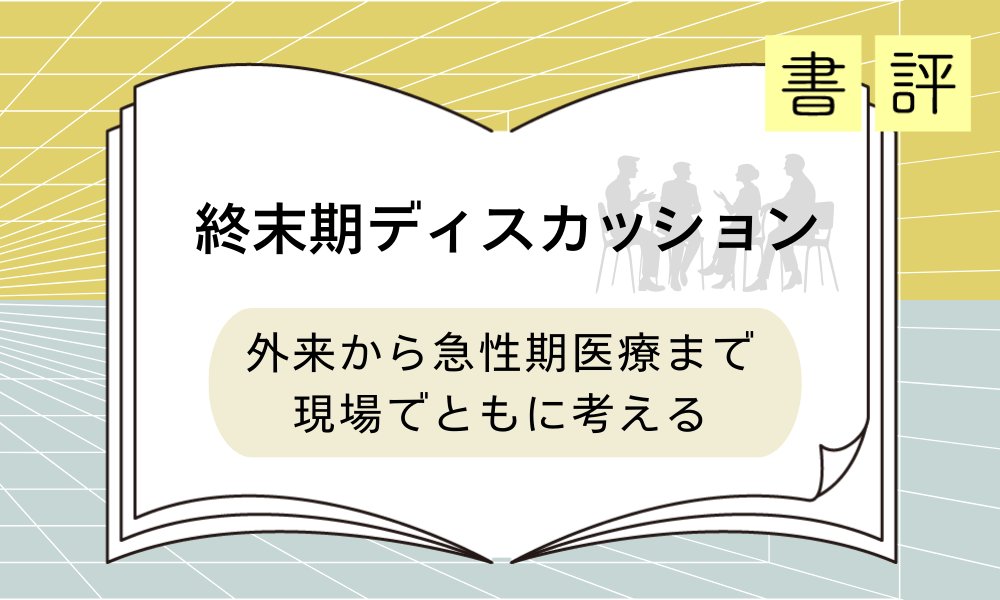
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
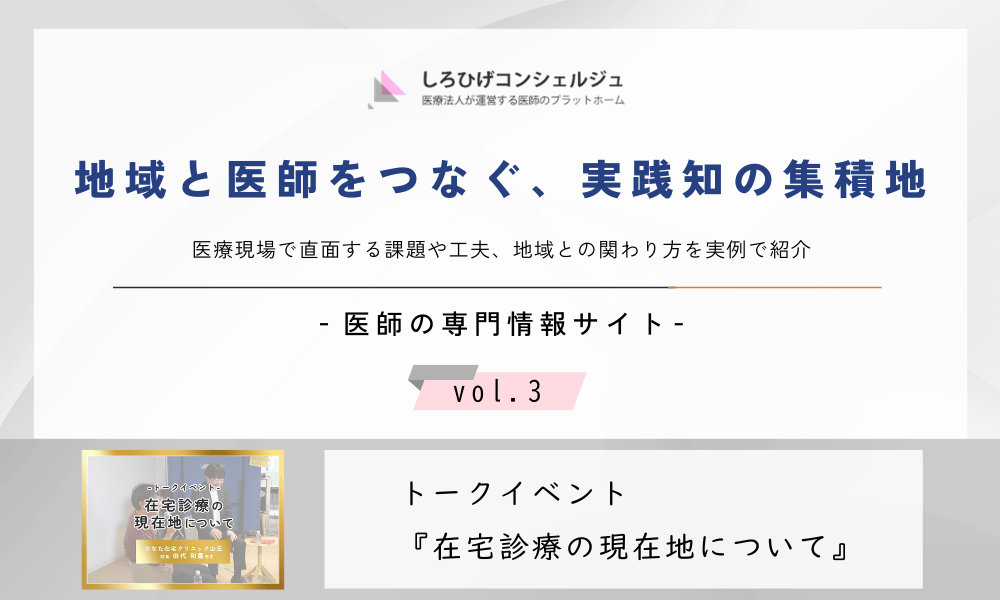
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
