記事・インタビュー
聖マリアンナ医科大学病院 病院長
北川 博昭
入院中の子どもの笑顔を取り戻すにはどうすれば良いか。私たち小児を預かる病棟ではいつも考えさせられる課題である。1年を通じて病棟看護師、保育士たちが豆まき、ひな祭り、七夕、夏祭り、クリスマス会等いろいろな催しを行っているが、本物の笑顔が見られない子どもたちもいる。小児腫瘍の患者は入院すれば点滴や抗がん剤で髪の毛が抜け、口内炎で味を失い、食事も摂れず、ベッドから起き上がることも出来ない。その後は手術を受け、大きな傷が体に出来てしまう。この治療の繰り返しは見舞いに来る家族にとっても辛いものである。長期入院患者の笑顔を取り戻すにはどうすれば良いか。長年悩んできた課題である。
大学病院に勤務犬を導入したきっかけは、入院中の白血病患者の書いた一通の手紙だった。彼女の家族は子犬を育てるボランティアをしていた。入院によって犬と会えなくなった彼女は、日本で「犬」が勤務する小児病院に「犬に会いたい」と手紙を送った。そして、通常は施設外に出ることのない犬が、特例で当院にやって来たのである。彼女は抗がん剤の治療中にもかかわらず、花を飾り、絵を描き笑顔で準備を始めた。この取り組みが勤務犬導入のはじめの一歩となった。
医療従事者の管理下で、患者の治療に対する補助療法として行われる動物介在療法(AAT:Animal Assisted Therapy)は、当時全国で2施設しか行われていなかったが、我々の病院にも取り入れられないか考えるきっかけとなり検討を重ねた。病院内を犬が普通に歩くことが出来る環境をどのように整えるか。まずは公益財団法人日本盲導犬協会、社会福祉法人日本介助犬協会に所属するPR犬に病棟を訪問してもらい、犬がいることに違和感がない病院作りを目指した。資金に関しては同窓会である聖医会にお願いし、地方の同窓生には直接お願いに出向いた。聖医会主催の同窓会でonecoin box を会場に設置したところ、箱は瞬く間にコインでいっぱいになった。
多くの方のご協力によって、日本介助犬協会から待望の犬の貸与が実現した。犬の調教師であるハンドラーは医療資格者で、かつ専門プログラムを受講しなければならない。私の小児外科医局員と病院の看護師長が専門プログラムを受け、緩和ケアチームの一員としてハンドラー業務を兼務している。地道な啓蒙活動や署名活動で賛意を確認し、明石理事長はじめ大学法人として認めていただくことが出来た。職員一丸となった取り組みから2年経過した2015年4月に勤務犬「ミカ」が大学病院として初めて誕生した。
 勤務犬「ミカ」の右となりが筆者
勤務犬「ミカ」の右となりが筆者
なぜ大学病院で動物介在療法が必要なのか。医療は進歩し、人は長期生存が出来るようになったが、我々医療者は治療に専念し、新しい発見を求めたため何かを忘れてしまった。手術室に行きたがらない子どもを無理に連れて行くことをやめたら、照れくさそうに「ミカ」の後ろをついて手術室に入って行く子どもの姿があった。ベッドに「ミカ」が寝転んでいると子どもに自然と笑顔が戻ってきた。子どもの心の声に今一度耳を傾けたとき、高度先進医療を担う大学病院が忘れていたことの一つに気付くことができた。稼働率、在院日数、収支バランスを見ながら病院経営を行い、殺伐とした医療の中で本当に患者の気持ち、子どもの気持ちを理解した医療を行う事が出来ていたか。近い将来これらの取り組みや努力に対し保険診療面でのサポートや病院機能評価の視点からも推進されることを願っている。
きたがわ・ひろあき
聖マリアンナ医科大学卒業。小児外科専攻。1984年から神奈川県立こども医療センター レジデント、1988年から米国Los Angeles小児病院Research Scholar、1995年からNew Zealand Wellington病院で臨床医として勤務。帰国後、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、2006年聖マリアンナ医科大学小児外科教授就任。2012年から外科学講座代表、2017年4月より現職。
※ドクターズマガジン2017年7月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
北川 博昭
人気記事ランキング
-
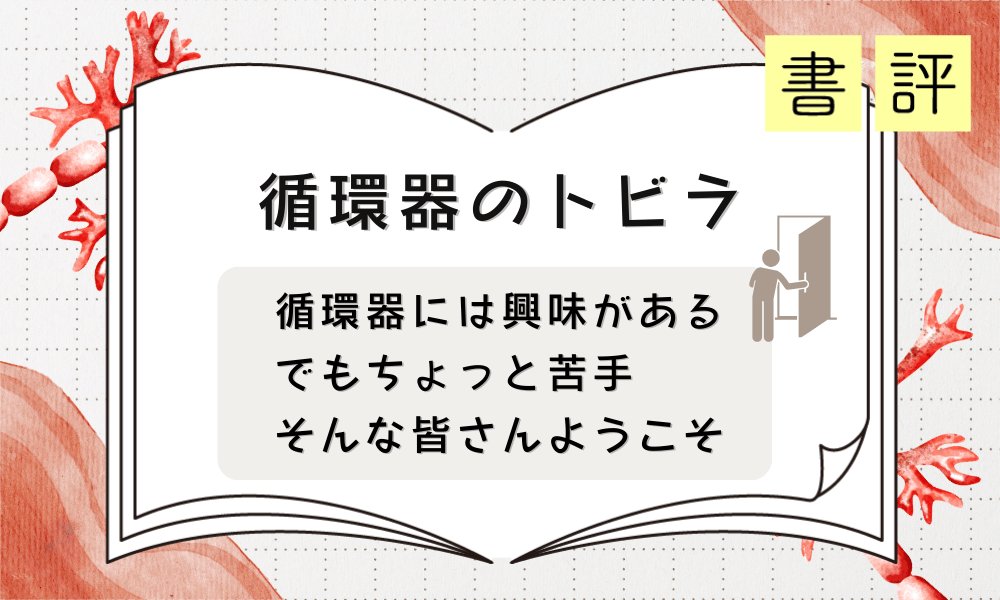
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
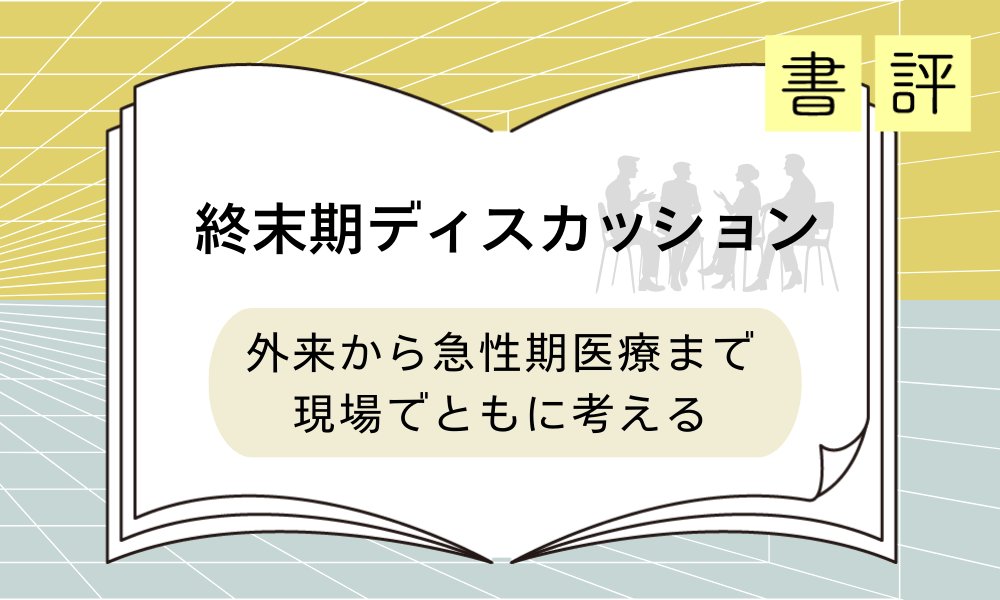
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
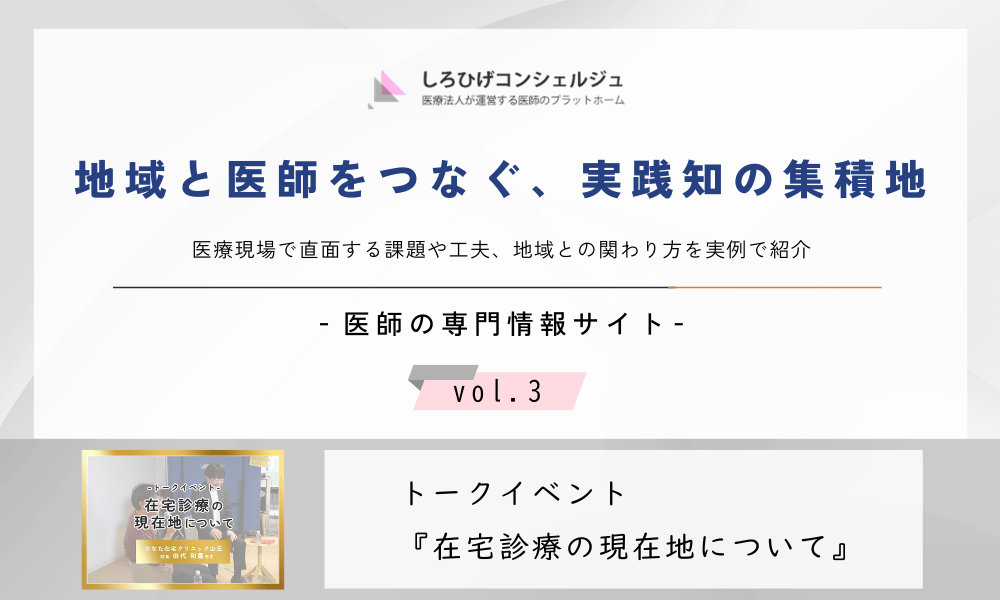
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
