記事・インタビュー
国立病院機構 長崎医療センター 院長
米倉 正大
最近、起こった話題を一つ。がんの治療のため入院した友人から、苦情をいただいた。すでに他院でがんの告知がされている友人が、若い担当医からがん治療の説明を受けた時、不安ばかりをかき立てられて、脅迫されているように感じた、と言うのである。現在のインフォームドコンセントの取り方は、マニュアルに従って説明したことは必ずカルテに記録しておくこととなっている。担当医はがん治療に伴う副作用を事細かに、教えられたとおり忠実に実行したのであろう。
もう一つ、立て続けにやはり友人の娘さんから苦情をいただいた。友人が初期のがん治療のため入院となった。歩いて入院した友人の娘さんに、若い担当医の、「もしお父さんが急変して状態が悪くなったとき人工呼吸を付けますか」という質問にショックを受けたという。治療効果を期待して入院した家族への第一声が、娘さんの意表を突いたのである。病気ばかりに気を取られて、相手の気持ちを読もうとしなかったという事なのだろうか。
たまたま2人は私の友人だったので耳に入ったが、これは氷山の一角ではなかったのか。多くの理論的記憶を優先して教育されてきた医師たちの総合判断は、どのようになされるのか、脳の働きに興味を持ってきた脳神経外科医の思いで分析してみたくなった。
医学の進歩で、学生の頃から覚えなければならない記憶量が多くなり、覚えるのに費やす時間も比例して多くなっている。それ以上に医師になって教科書から覚える記憶量は、私たちの頃とは、比べようもないくらいに大量になっている。その分、経験に基づく記憶量は確実に少なくなっている。というより、少なくならざるを得ない状況である。特に、最近の教育では、マニュアルなどの使用が多くなった。決まりごとが多い世の中で、問題を起こさずに効率的に仕事をしていくためには、手っ取り早い方法である。先輩の背中を見て学ぶという効率の悪い、掴みどころのない方法は、消滅してしまった。
人間の考えや行動は、すべてその根源がその人の過去の記憶に基づいている。記憶と言ってもその種類は多く、いろいろな分け方があると思うのだが、大胆に分けると、勉強などで記憶する理論的な記憶と経験に基づく記憶の2種類である。この2つの記憶の決定的な違いは、脳の中では理論的記憶に比べ経験的記憶(周辺記憶)の量が圧倒的に多いという事である。
理論的記憶を中心に多くの周辺記憶の中のどれを関わらせるかという時に、第六感が働き、総合判断を行う。総合的な判断をする時に重要な役割を発揮するのが、第六感という各個人が持っている能力で決まる。第六感と言うと、言葉では言い表せない、いい加減な判断と思われがちであるが、洞察力あるいは知恵と置き換えられるかもしれない。
先輩の背中を見て学ぶ中には、先輩の情熱的な仕事ぶりや仕事に対する誠実さなどに関わる周辺記憶も含まれる。先日の朝日新聞で東京大学総長の浜田純一氏は、「かつては知識をたくさん持っていることが、力になりました。その点、東大生はタフかもしれませんが、これからは、物事の弾力性、あるいはしなやかな考え方を身に付けるようにしないといけない」と言っています。この物事の弾力性やしなやかな考え方というのは、私が言う理論的記憶に周辺記憶が加わった、あるいは第六感が働いた総合判断という事ができる。マニュアルを作った先輩たちは、理論的記憶に多くの周辺記憶を加えて作成している。これを教えられる後輩たちは、周辺記憶を学ぶことはなく、理論的記憶のみで行動することになる。
平成16年に始まった初期臨床研修の必修化は、2年間でいろいろな診療科でまんべんなく多くの種類の疾患を経験させ、OSCEなる試験でその達成度をチェックしている。2〜3ヶ月毎の各診療科の研修は、多くの病気に対処し、知識と技術の伝達で理論的記憶量は効率的に飛躍的に増加し、ある意味では貢献したが、果たして全人的医療ができる医師に育ったかは疑問である。このために若者の脳の何を犠牲にしているかという事も併せて考える必要がある。
先輩の背中にある熱意や誠実さを横目で学びながら、患者さんに対する先輩の思いの周辺記憶を蓄積させ、第六感を育てることも考えないと、前述した友人の苦情にこたえることは難しいのではないか。
※ドクターズマガジン2012年3月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
米倉 正大
人気記事ランキング
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “03 スライド準備の時間を劇的に短縮! 院内勉強会のためのChatGPT 活用新常識
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “03 スライド準備の時間を劇的に短縮! 院内勉強会のためのChatGPT 活用新常識
白石 達也
-
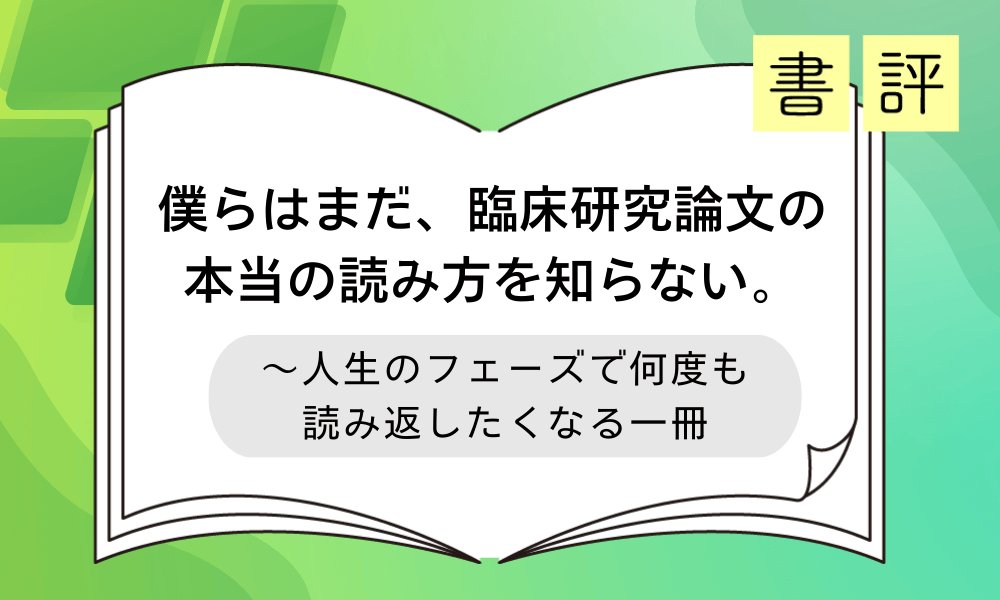
書評『僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。』
- 研修医
- 医書マニア
書評『僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

未経験歓迎|頼れる存在であるために。在宅医療をともに支える医師募集
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
未経験歓迎|頼れる存在であるために。在宅医療をともに支える医師募集
金沢ねいろクリニック
-
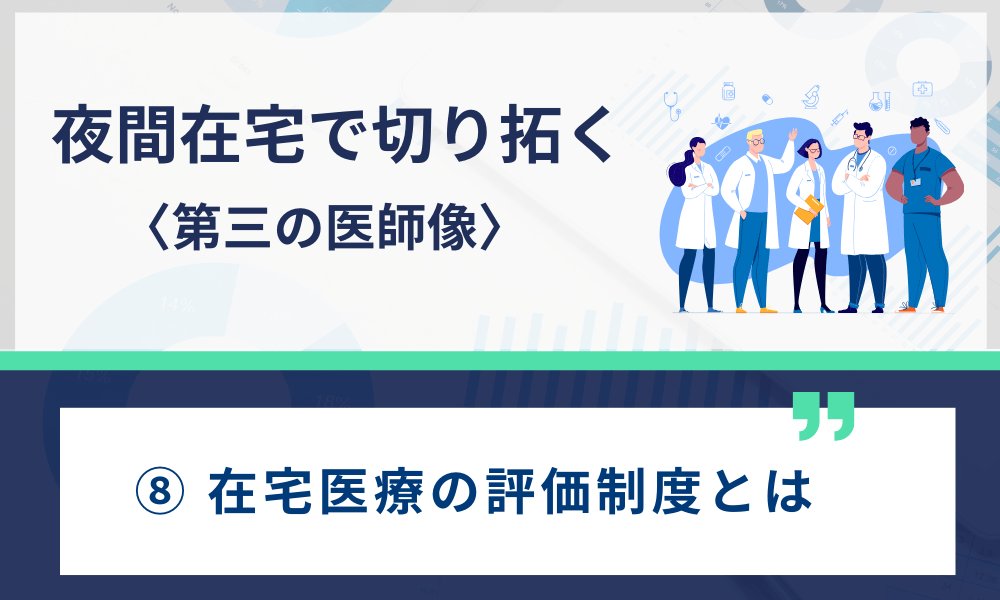
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑧ 在宅医療の評価制度とは
- イベント取材・広報
夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑧ 在宅医療の評価制度とは
株式会社on call
-

医師の声を活かす現場で育む、ジェネラルに診る力と専門性
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 専攻医・専門医
医師の声を活かす現場で育む、ジェネラルに診る力と専門性
大阪みなと中央病院
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-
会員限定

瞬速レクチャー~救急編~「意識障害」
- 研修医
瞬速レクチャー~救急編~「意識障害」
-
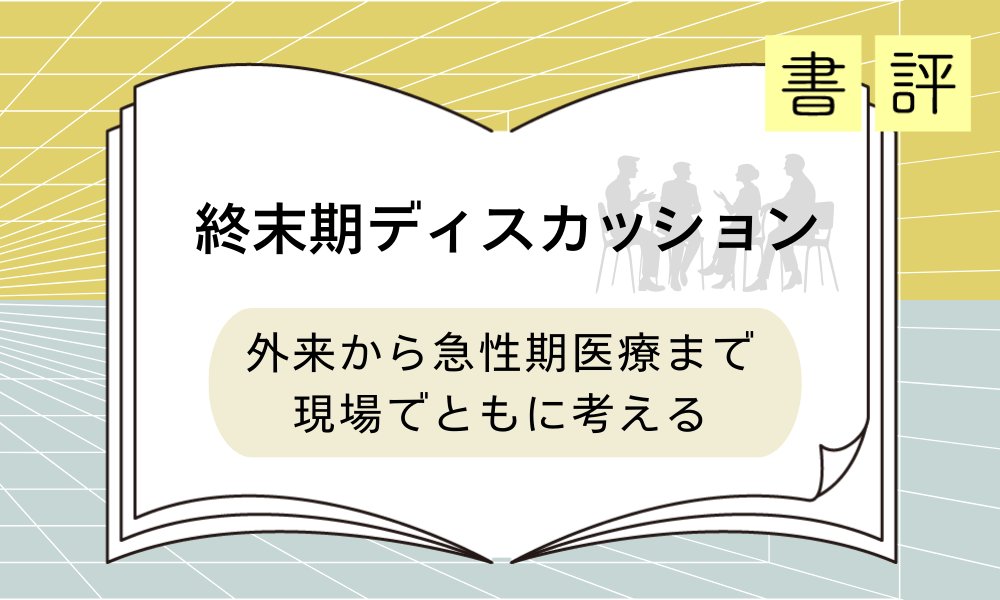
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

先輩に聞いた! ④初期研修を充実させるためのアドバイス
- 研修医
先輩に聞いた! ④初期研修を充実させるためのアドバイス
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
