記事・インタビュー
沖縄県立中部病院
総合内科
金城 紀与史
(フィクション)患者Aさんは75歳男性で、半年前に肺がん(転移もあり)と診断された。抗癌剤で治療していたが腫瘍が増大していた。今回は2日前から発熱と息切れで来院。呼吸不全状態で意識障害あり。マスク全開酸素投与でも低酸素状態で呼吸数は40回/分である。レントゲンは肺がん自体1ヶ月前と変化なしだが、それとは別に大葉性肺炎があり、痰の染色で肺炎球菌が見える。呼吸状態からは挿管が必要だが、がんという致死的疾患を持っている高齢のAさんに挿管すべきか悩ましい。呼吸器をつけても助からないかもしれない。たとえ肺炎を乗り切っても呼吸器から離脱できない状態になる恐れもある。しかし肺炎を治療すれば元の状態に戻る望みもある。
終末期医療をめぐる問題点はたくさんある。本人の意思をどこまで尊重することが許されるのか。治療拒否により死ぬことは自己決定権の発露なのか。自殺との区別はつくのか。本人の意思が明確でない場合には、患者当人の意思が明らかに推定される証拠がなければならないのか。治療の中止や差し控えにおいて、確実に「ターミナル」でなければならないのか。社会的・法的コンセンサスが得られていない領域である。本稿では「始めない」と「止める」の区別、冒頭の患者に挿管せずにみること(始めない)と、呼吸器をつけて治療したが治療効果が乏しいために本人や家族の希望も考慮して抜管する(止める)ことに差があるのかどうか考察したい。
人工呼吸器を始めないことは、医師は消極的に病気に成り行きを任せるだけであるのに対して、一度始めた治療、人工呼吸器を外すのは積極的に患者を死に追いやる行為のような印象を抱く読者も多いのではないだろうか。我が国では人工呼吸器外しが「殺人事件」や「業務上過失致死」として立件されるリスクがあり、川崎協同病院事件、北海道立羽幌病院事件、射水市市民病院事件などマスコミでも取り上げられた。とくに川崎協同病院では患者の回復の見込みがなく死が目前に迫っており患者が治療中止に同意している証拠がなかったことを一審・二審は有罪判決の根拠としており、治療中止の要件は非常に狭き門になっている。とはいえ、あくまでも裁判所の判決であって上記の要件を満たせば治療中止は容認されるという法律があるわけでもないし、人工呼吸器を外すことは犯罪であると明示した法律があるわけでもない。一方冒頭のケースで医師が人工呼吸器を付けない(=始めない)判断をしたとしても、違法性が問われるリスクは明らかに低く、始めないことと止めることの法的なギャップは大きい。
米国では「始めない」「止める」の区別の是非について1976年にニュージャージー州最高裁で歴史的判決が下された。若い女性が薬物中毒により低酸素脳症となり人工呼吸器が装着されたが、娘カレンから呼吸器の取り外しを両親が要求して裁判となったのである。判決はカレンの自己決定権を大きく持ち上げて、(たとえ結果として死に至っても)患者には治療の拒否権があると判断した。「始めないのは容認されるが、一度始めたものを外すのは許されない」という議論も却下している。理由としては、①患者は原病によって死亡するのであって人工呼吸器を外すことが死の原因ではない。②一度始めた治療を決して止められないとすると、しばらく治療し反応をみて助からないことが明らかになった時点で外すという選択肢がなくなり、助かる可能性があるのに最初から積極的治療を諦めざるを得なくなる。③始めないという判断も、呼吸器を外すということと同様の重みのある積極的判断である。この判決以降米国のICUでは人工呼吸器を含む治療の差し控え・中止が患者・家族との協議の上で日常的に行われるようになった。
米国での議論が我が国でも説得性を持つかどうかはわからないが、日本老年医学会が1月に発表した高齢者医療に関する立場表明で「患者本人の尊厳を損なったり苦痛を増大させたりする可能性があるときには、治療の差し控えや治療からの撤退も選択肢として考慮する必要がある」と述べている。始めないことと止めることの区別があるのかないのか、終末期医療の常識・非常識が少しずつ動き出しているようだ。
監修:岸本 暢将[聖路加国際病院アレルギー膠原病科(成人、小児)]
※ドクターズマガジン2012年6月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
金城 紀与史
人気記事ランキング
-
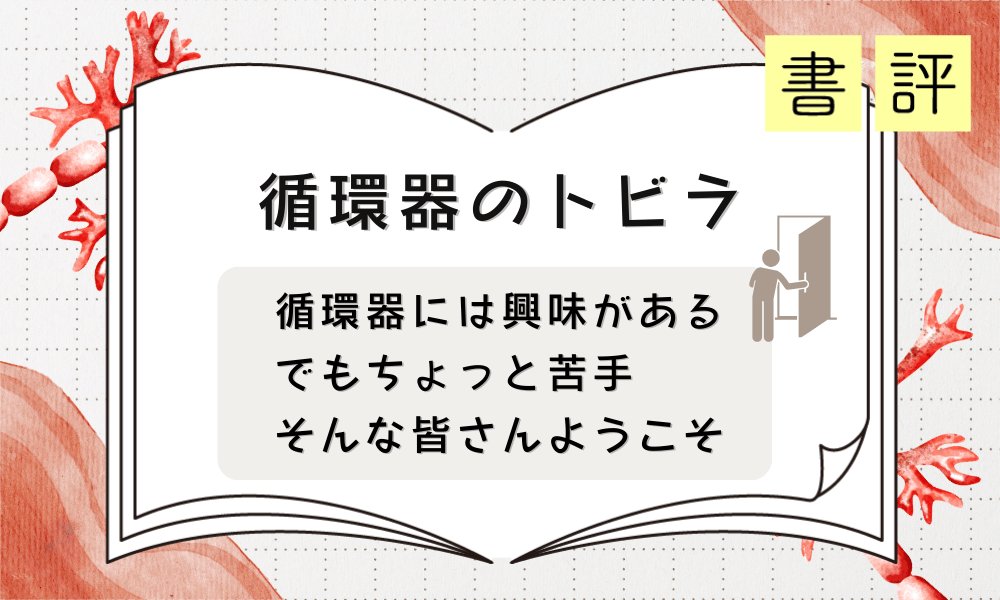
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
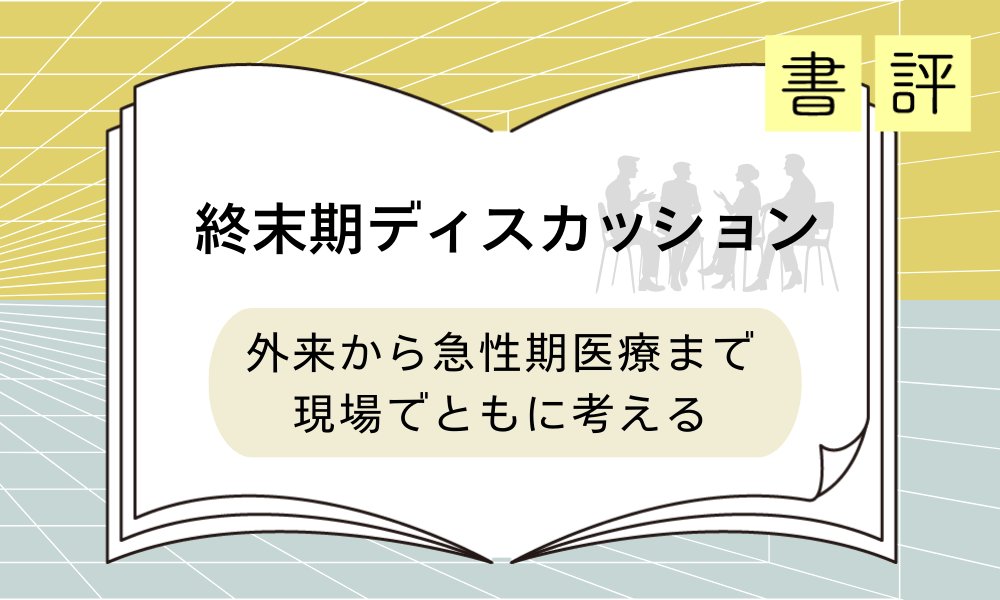
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
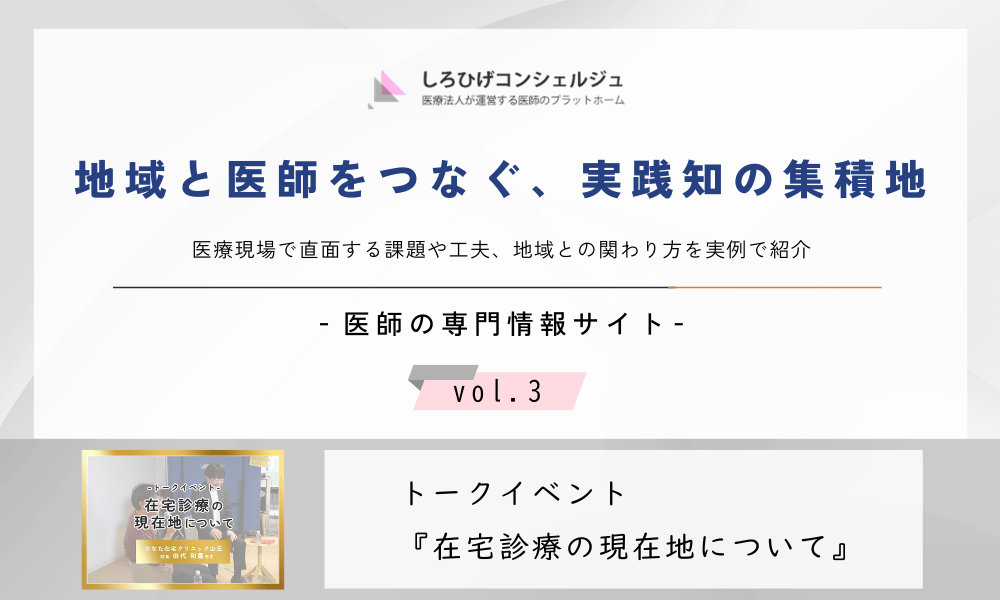
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
