記事・インタビュー
 ▲2018年 テネシー大学 ルボーナー小児病院「小児神経科に関わるスタッフ陣」
▲2018年 テネシー大学 ルボーナー小児病院「小児神経科に関わるスタッフ陣」
現在、アメリカのミシガン小児病院(Children’s Hospital of Michigan)で、小児神経科指導医として勤務されている桑原功光先生。どのような少年時代を過ごして医師を目指すことになり、海外で働くまでに至ったのか。その軌跡について語っていただきました。
<お話を伺った先生>

桑原 功光(くわばら のりみつ)先生
ミシガン小児病院
小児神経科指導医
Q:どんな少年時代でしたか。
私は、北海道砂川市で生まれ育ちました。砂川市は旭川市と札幌市のちょうど中間に位置しており、炭鉱業が盛んだった昔は交通の要所として栄えましたが、今は高齢化と人口減少が進む田舎町です。
最近ではNHKプロフェッショナルでも取り上げられた「一万円選書」で全国に知られた「いわた書店」のある市として知られています。車の整備士で子煩悩な父、助産師で勝気な母、私には全くないファッションや料理の才能を兼ね備えた年子の弟という4人家族で育ちました。
 ▲出生時写真 「旧砂川市立病院前で母と」
▲出生時写真 「旧砂川市立病院前で母と」小中学生時代は、どちらかというと物静かで、本や漫画ばかり読んでいる少年だったと思います。小学校時代、周囲の友人の多くがコロコロコミックに夢中になるのと対照的に、私の愛読書は「コミックボンボン」。80年代に小学生男子の間で大ブームとなったガンプラ、ファミコン、ラジコンの人気を牽引した月刊雑誌で、その看板漫画であった「プラモ狂四郎」「ファミコン風雲児」「ファミ拳リュウ」「ラジコンキッド」などを毎月楽しみにしていた小学生でした。
小中学校時代の成績は学年で常に上位でしたが、中学三年から柔道にのめり込んだこともあり、隣町の滝川高校に進学してから成績はガタ落ちでした。
高校一年生だった時か、授業を全く聞いておらず、いくつかの科の期末試験を白紙で提出したところ、校長室に呼び出されて「君は留年という言葉を聞いたことがあるか」と叱責されて、初めて事の重大さに気づきました。でも不思議と、父と母に「勉強しなさい」と言われた記憶がありません。きっと、やらなくてはいけない時には、きちんと机に向かう子だったのでしょう。
Q:医師を目指すきっかけについて教えてください。
母が助産師であったのに加え、私が幼少期にぜんそくやアレルギーなどがあり病院へ行くことが多かったことや、高校生時代に父が買ってきてくれた手塚治虫氏の漫画『ブラックジャック』を読んでいるうちに、無意識に医師に憧れを感じるようになったのかもしれません。高校三年になってから、医師を目指そうと思い必死に勉強をし始めたのですが、時すでに遅し。結局、一浪して旭川医科大学に入学しました。
私より年上の親戚で大学まで進学できた人は誰もいません。父は戦後の貧困のために高校にすら行くことができず、最終学歴は中卒。自動車整備工場で日曜日以外は休みもなく、一年中忙しく働いていました。母は高校に入学した途端に、母方祖父が炭鉱事故で亡くなったため、高校を一旦中退せざるをえなく、働きながら通える高校に再入学しました。そこから勉強して、准看護師、正看護師、そして助産師の資格を取って、最終的には砂川市立病院の産婦人科で定年までずっと勤務しました。
私が旭川医科大学に入学して、何より不思議だったことは、同級生の親に医師など高学歴の方が多かったことです。「なぜこの人たちの親は戦後の貧しい時期に大学に行ける余裕があったのだろう?」という素朴な疑問を感じたことは今でもずっと覚えています。
ずっと後になり、母が「お父さんは中卒であることを職場でずっとからかわれていたけど、あなたが医学部に行った途端に誰も言わなくなったって喜んでいたのよ」と一度だけ話してくれたことがあります。父はそんなことを私に漏らしたことは今だかつてありません。きっと父なりのプライドだったのでしょう。私もこの年齢になって、そうした当時の父母の思いを、少しずつですが、やっと理解できるようになりました。
 ▲現在「鬼滅のアイスホッケージャージ姿」
▲現在「鬼滅のアイスホッケージャージ姿」旭川医科大学では決してクラスの主流でなく、むしろ傍流。学業も突出せず、目立つタイプではありませんでした。部活はアイスホッケー部に入りましたが、大学までスケートをしたことが全くなかったため、上手ではありませんでした。
さらに当時はアイスホッケー部内の人間関係がギスギスしており、私はなかなか部内の雰囲気に馴染めませんでした。しかし、アイスホッケー部以外でもさまざまな人と出会い、大学生活を彩ることができました。大学の先輩であった牧野洋先生(現 浜松医科大学麻酔・蘇生学講座 講師)には北海道各地の山登りに連れていっていただき、さらに一緒にカヌー部を創立して北海道中の川を巡り、知床半島をシーカヤックで一周したのは生涯忘れられない思い出です。
また、今や医学英語教育で日本を代表する押味貴之先生(現 国際医療福祉大学 医学教育統括センター 准教授)は私の医学部時代の同期です。押味先生と一緒にコピーバンドしたこともありました。押味先生はボーカル、私はキーボード。今となっては黒歴史ですが(笑)。
Q:研修医時代のエピソードを、お話しいただけますか。
私が医学生の頃(1995年〜2001年)は、2004年からスタートした新研修制度(マッチングシステム)より前であったため、ほぼ全ての医学生が卒業後に医局に入る時代であった反面、インターネットが徐々に普及して卒後研修への意識が少しずつ変わりつつあった過渡期でもありました。
医学部6年生の時に進むべきかどうか最後までずっと迷っていた科は「小児科」「産婦人科」「精神科」の3つ。しかし、そんなデジタル情報の技術革新時期の中で、コンピューターを生かした画像検査は将来さらに発展すると感じて、「放射線科」に入局しました。
ところが、次第に「やはり自分は、ベッドサイドで患者さんを診る医師になりたい」と強く思い始めました。まずは、総合診療マインドを持ってローテーション研修できる病院で、医師としての基礎力を築くことを目指したのですが、当時は北海道内でそのような病院はほとんど存在しなかったため、北海道を飛び出す意思を固めました。
私がまず面接に向かったのは京都府の市立舞鶴市民病院でした。当時、優れた教育モデルとして燦然と輝く松村理司先生(現 洛和会ヘルスケアシステム 総長)がいたことを始め、さらに海外からの「大リーガー医」が定期的に訪問していたことで全国に名を馳せた研修病院です。松村先生に会いに北海道から舞鶴まで行きましたが、その翌年に至るまで研修医の受け入れ枠がすでに埋まっており、舞鶴は断念しました。ただ、松村先生から「ここまで来た人は皆、海外に行くから、君も必ず行く人だ」と言われたことは、今でも覚えています。
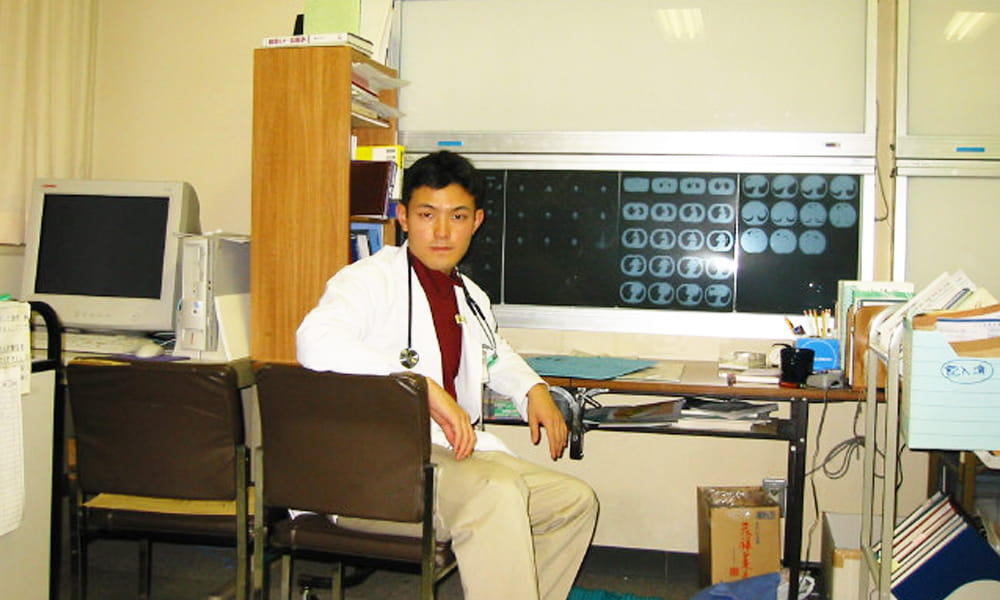 ▲2001年12月 「旭川厚生病院 放射線科」
▲2001年12月 「旭川厚生病院 放射線科」その後、旭川で開催された徳洲会の説明会に参加したことがきっかけとなり、岸和田徳洲会病院で研修することとなりました。本当は湘南鎌倉総合病院に行こうと内心決めていたのですが、その説明会で、私の席のとなりに座ったのが、岸和田徳洲会病院の救急部長でした。
その救急部長の「北海道の人間は結局、関東を越えて関西にくる気概のある人間がいない」という売り文句に、まだ若かった私はお酒の勢いもあり「じゃあ、オレが行きますよ」と明言してしまったのです。そうして、岸和田に行くことが決まりました。行く前は「だんじり」という言葉すら知りませんでした。そこで、理学療法士であった現在の妻と出会ったのですから、これも運命だったのでしょう(笑)。
Q:USMLE合格へ向けた勉強はいつ頃、始められたのですか。
関西国際空港が近くにある岸和田徳洲会病院は、海外の患者さんに出会うことも多く、私が常に「海外に行きたい」と口にしていたため、ガボン共和国の大使が突然訪問された際は、院長から直接、院内の案内を任されたことがあります。
このような体験があったことや、当時、流行していたアメリカのテレビドラマ『ER救急救命室』の影響を受け、この頃から少しずつUSMLE合格を目指して勉強を始めました。すでに卒後5〜6年が経過しており、遅いスタートでした。
 ▲2003年7月 岸和田時代「ガボンからのゲスト」
▲2003年7月 岸和田時代「ガボンからのゲスト」
「小児の専門病院で、幅広い小児科疾患を学びたい」と思い、旭川医科大学の放射線科医局を除籍したのは、岸和田徳洲会病院に勤務して2年経った頃です。
岸和田で研修した後は、小児内分泌代謝科、小児腎臓科の領域で日本のトップランナーであった東京都立清瀬小児病院(2010年に東京都立小児総合医療センターに移転統合)に入職しました。
同病院に勤務している間にUSMLE STEP2CSを受験したのですが、結果は不合格。英語力をもっと磨かないとSTEP2CSには合格できないと考え、横須賀か沖縄の海軍病院を経てから海外に行こうと決断しました。横須賀と沖縄の海軍病院のインタビューを受けましたが、1年目は不合格。翌年の2回目の応募で沖縄海軍病院にかろうじて合格し、そこで1年間、英語力を磨きました。
桑原 功光
人気記事ランキング
-
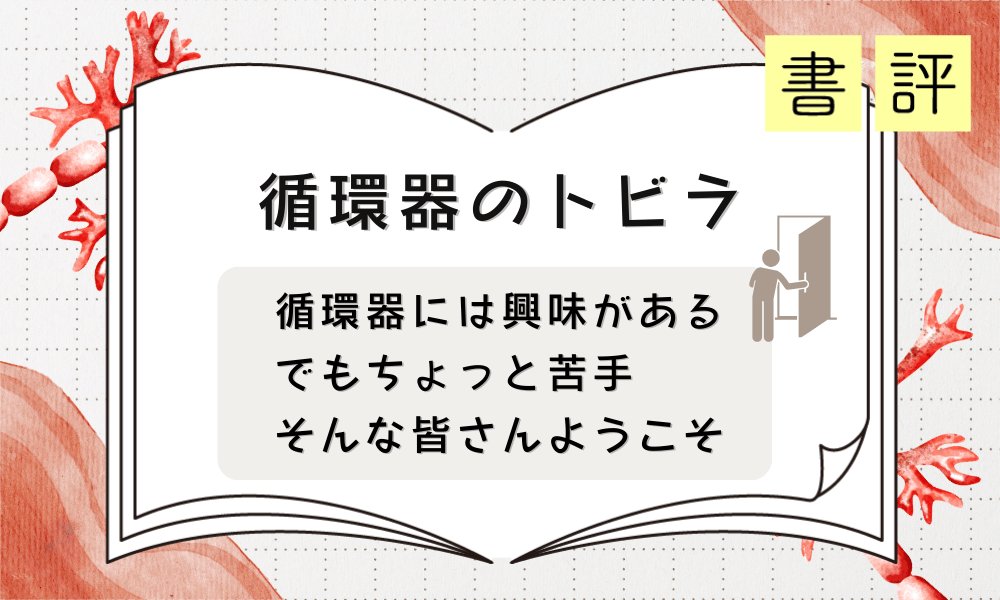
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
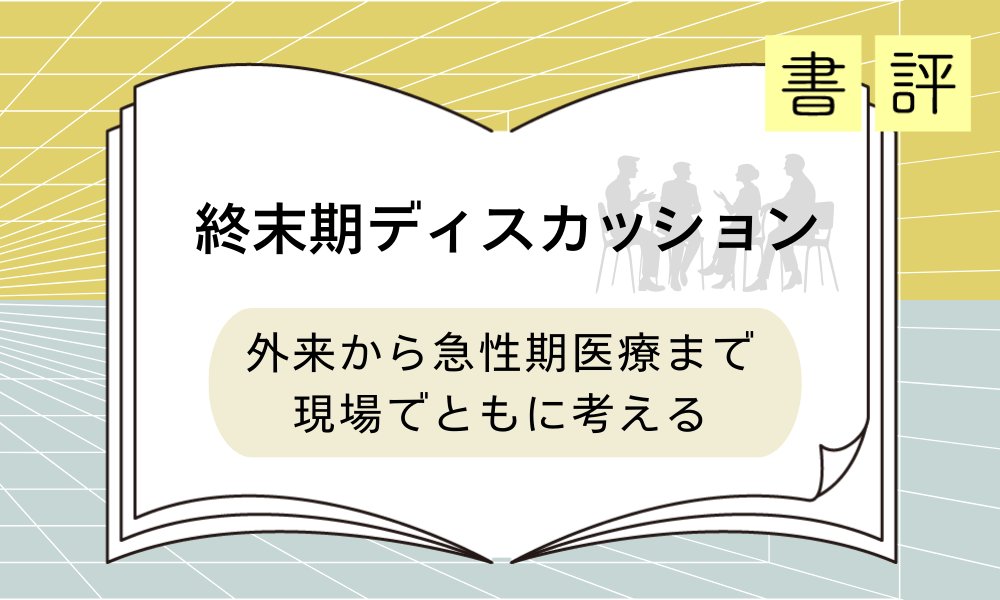
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
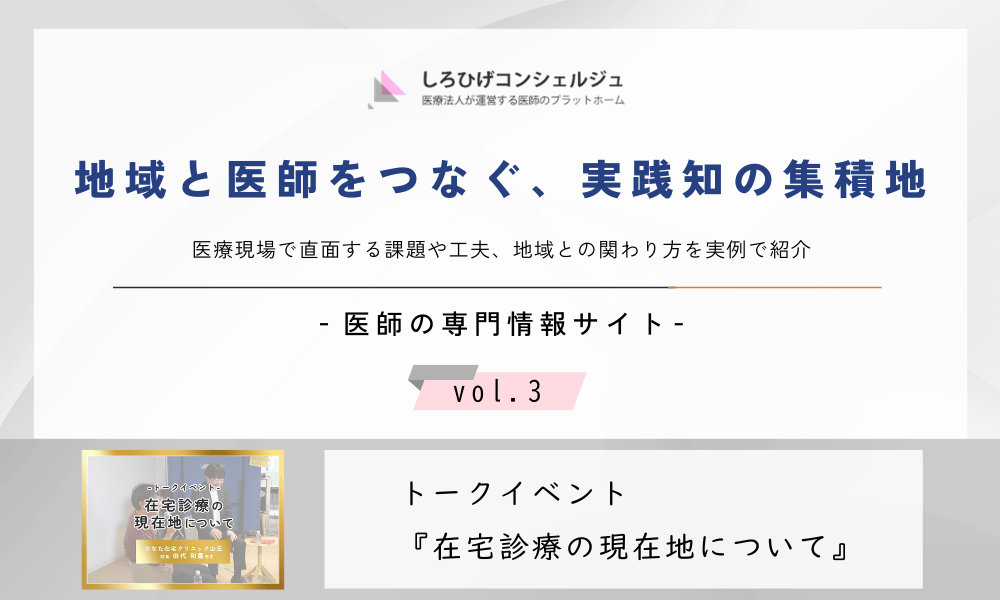
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
