記事・インタビュー
岐阜大学医学部附属病院長
同救急・災害医学分野 教授
小倉 真治

1995年1月17日未明に阪神・淡路大震災が起きた。当時私は、香川医科大学麻酔・救急医学講座の助手として日々の診療に没頭していたが、震災当日は自宅で眠っており、寝ていた布団ごとおよそ1メートル飛ばされたのを覚えている。
私は香川医大からの災害医療班第2班を引き継ぎ、長田保健所を拠点として避難所の診療を行った。今でも、避難所の患者の皆さんが口々に、「目の前で死んでいく人々を助けられずにつらい」ということを言っていたことが忘れられない。
災害医療と救急医療の違い
皆さんは救急医療と災害医療はきわめて近いものだと思っているだろう。この認識は一面では正しいが他面では大きな誤りである。救急医療は目の前で苦しんでいる患者を何としてでも助けるという医療の原点に立った診療を行っている。これは患者の数に対して医師数や薬剤等の医療資源が潤沢にあることを前提として行えるのである。
救命救急センターの救急外来では1人の患者に医師5人、看護師3人、技師3人などの多くの医療従事者が関与することが当たり前であり、資源投下型のビジネスモデルである。
一方、災害医療の現場では多くの患者が存在するために、医療資源が絶対的に足りなくなる。1人の患者に医師5人から1人の医師に患者が100人もありえない訳ではない。この100人を順番に見ていけば、順番が最後のほうになれば手遅れで医療が間に合わない方が出てくるため、思考を切り替える必要がある。
したがって、災害医療は救急医療の延長線上にはない。心臓が止まった患者をみんなで助けるが、それをやれない状況下にあるのが災害医療である。言葉を変えると、絶対多数の患者を助けるためには、切り捨てるべき人を早めに切り捨てないと最大多数の人を助けることはできない。そのためにするのがトリアージの作業である。
トリアージは、救急医療者にとっては、非常に苦痛を伴う瞬間である。人を助けるという単一の目的のために動いている人たちが、患者の中であえて治療を行わない患者を選定するという正反対のベクトルの作業をやらなければいけない。苦渋の決断であり、心理的な障害は想像できないほど強いものである。その意味で、災害医療が救急医療の延長線上にあるというのは間違いであると考える。
よくメディアは災害医療というとトリアージを取り上げ、その問題を話題にするが、それは一面では災害医療の特殊性を際立たせるものであるが、トリアージという言葉を独り歩きさせては問題の本質を見失うということは明確である。
災害急性期と慢性期
初期の72時間は、災害医療において、医療のサイズが足りない段階であり、急性期医療が最も必要な段階で、すべての領域の医師が狩り出されている。72時間を過ぎると、慢性疾患の対応が大きな課題となる。心理的なサポートを含めた慢性期診療ができる医療者が必要になる。
災害というのは、長く尾を引くものであり、到底2、3週間で終わらない。整理すると、時期によって、2つに分かれる。初期の段階では、外傷を含む急性期疾患が問題になるが、時期が落ち着くと、慢性疾患が問題となる。
私たちが阪神・淡路大震災で救援隊として、避難所で医療活動を行っていた時期は、フェーズが第1フェーズから第2フェーズになるころだった。持病の慢性疾患が悪くなったり、精神的なトラウマから抜け出せなかったりする。応急救護所でも、風邪をひいた人が多かったが、それ以上に、「閉じ込められたまま焼かれた人たちの悲鳴が耳について離れない」という話をよく聞き、抗不安薬や精神的な薬が必要であった。
最初はサイズが大きくなり、後はスパンが長くなる医療に変わる。ここにおいて登場する診療科も当初の救急科、外科系から内科系、精神科に変わっていくことも特徴であり、全てのフェーズで全ての診療科のニーズがあるわけである。
おぐら・しんじ
1985年岐阜大学卒業、1996年米サウスカロライナ医科大学客員研究員、1997年香川医科大学救急部助教授を経て、2004年より岐阜大学救急・災害医学分野教授。 2014年岐阜大学医学部附属病院長就任。救命救急センターを2回立ち上げた実績を持ち、日頃から救命のために一般への蘇生教育の普及を図っている。
※ドクターズマガジン2016年4月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。
小倉 真治
人気記事ランキング
-
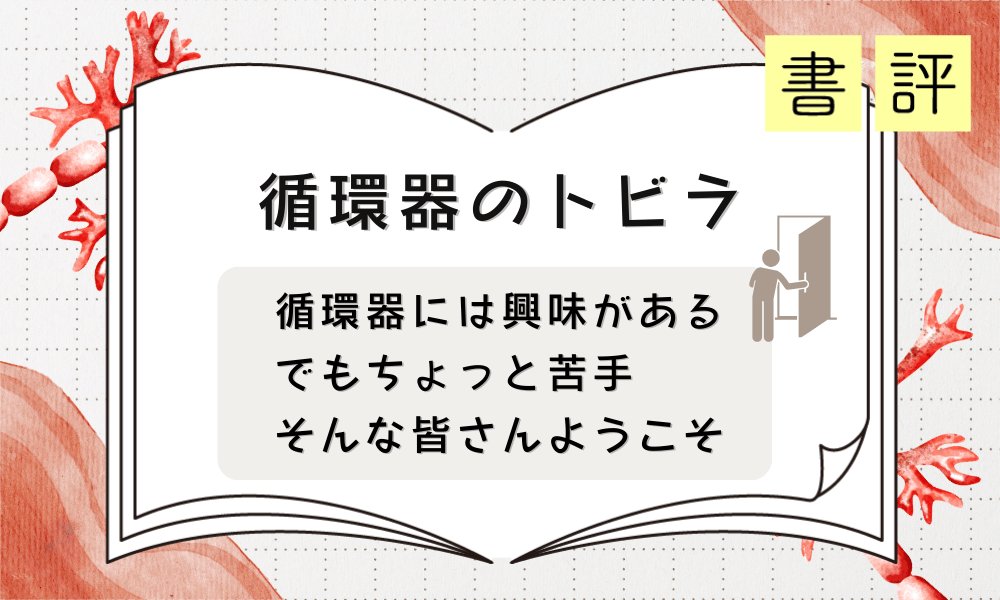
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』
三谷 雄己【踊る救急医】
-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
- ワークスタイル
- 就職・転職
- 病院以外で働く
臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環
株式会社ヒューマンダイナミックス、
-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』
松下隼司、オクダサトシ
-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
- Doctor’s Magazine
それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成
白石 達也
-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
- ライフスタイル
- 専攻医・専門医
- お金
医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!
-
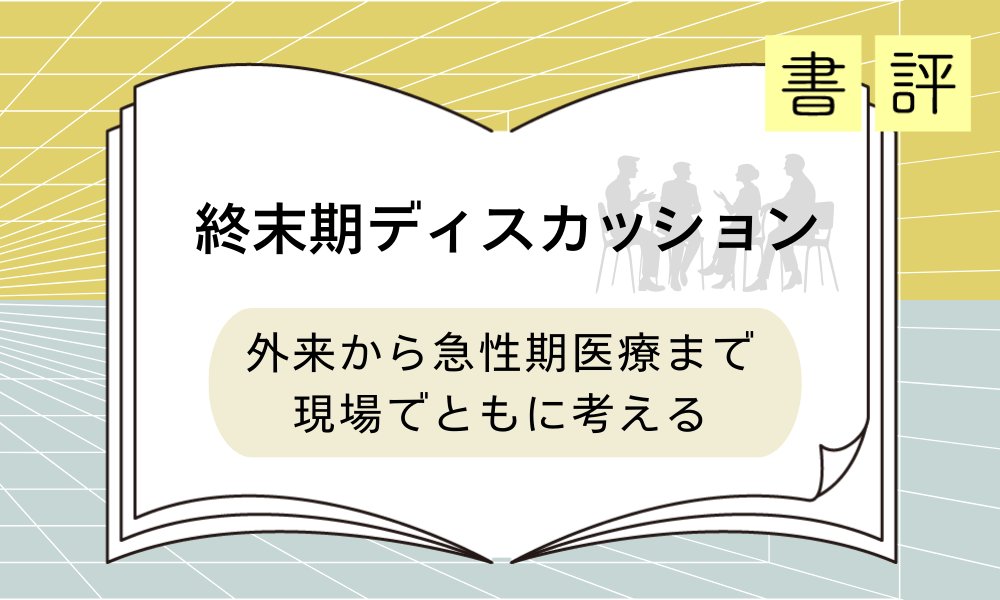
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』
三谷 雄己【踊る救急医】
-
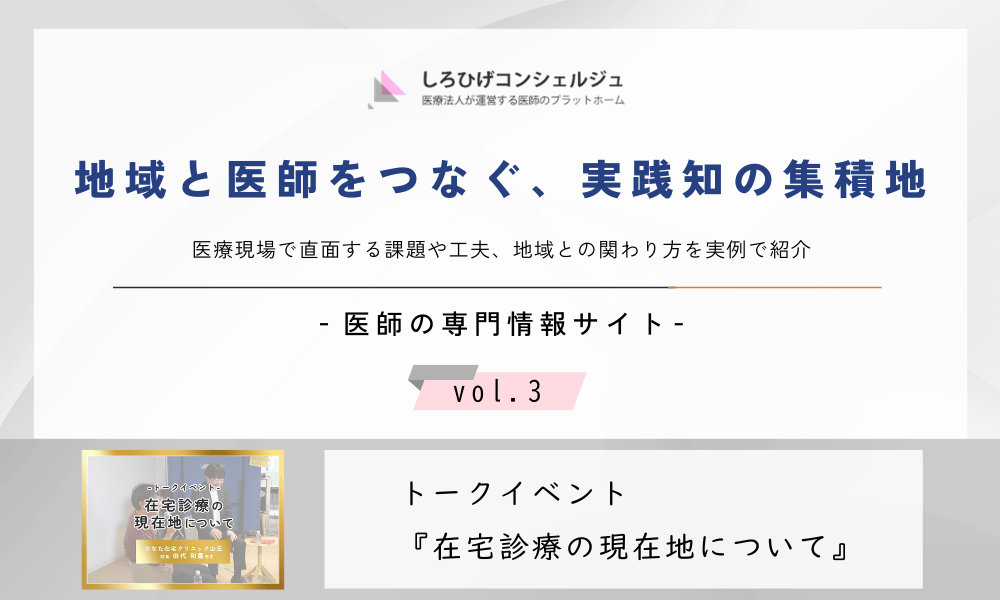
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
- ワークスタイル
- ライフスタイル
- 就職・転職
医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】
しろひげコンシェルジュ
-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』
山田 悠史
-
会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
- 研修医
- ワークスタイル
- ライフスタイル
ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―
-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
- 新刊
- 研修医
- 医書マニア
著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』
中島 啓
